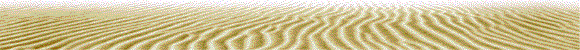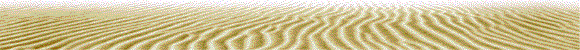
仏教は、さまざまな説き方があります。
南無阿弥陀仏の教えは、その中の
一つです。
仏説無量寿経に説かれる阿弥陀如来の
本願のはたらきで、すぐれた功徳を、
すべての衆生に与え、「南無阿弥陀仏」
一つで、救われることを、教えてくださった
のが親鸞聖人です。
親鸞聖人を、宗祖と仰ぐ、浄土真宗の
本願寺派。
そこに所属する九州・佐賀の一寺院で
製作しているのがこのホームページです。
「南無阿弥陀仏」の味わいを、電話で
お話ししています。毎週木曜日に、
内容を変更しています。
法話原稿をこのページに掲載して
います。ここで、「見て、聞いて」 ください。
メールマガジン始めました
「こんな話を聞きました」。
0952
|
記憶してください。)
24はニシ、西。 本願は、18願。
そこで、24-1800は、西本願 短いお話(動画)
第1725回 たのむ 頼む 憑む
令和8年 2月19日~
蓮如上人のお書きいただいた「御文章」には
「たのむ」ということばが、沢山出てきます。
如来をたのむこころの、本願たのむ決定心を たのむべきは弥陀如来
阿弥陀仏を一向にたのむによりて、ただ弥陀一仏をたのむうちに
如来をたのむ身になれば 弥陀をたのむ機を
弥陀をたのめば、
南無とたのむ衆生を
などなどです。
ところが、ここでは弥陀に たのむのではなく、
弥陀を たのむとなっています。
「に」ではなく「を」なのです。
親鸞聖人の教えの中には 弥陀「に」は出て来ずに
みんな弥陀をたのむとなっています。
今 私たちが使っている「たのむ」は 依頼する お願いすると
こちらの希望を頼み込む言葉です。
念仏するから助けて下さいという 取引の心です。
見返りを期待している。信じるから助けて下さい、苦しみを除いて
金が儲かるように、病気が治るようにと・・・・、
ところが、ここでは
こうした依頼の「賴」ではなく、「憑む」という意味だというのです。
さんずいから 一つとって にすいに 馬、その下に心と書く、憑むです。
この「憑む」は、「ああしてください、こうしてください」と
お願いや 注文の心をすべて捨てて、すべて阿弥陀さまに
おまかせし切って安心して日々を重ねることだと言うのです。
思い通りになっても、ならなくても、この人生を
ありのままに受け入れて歩ませていただくということです。
私たちの人生には、よいこともあれば、悪いこともあります。
それを一喜一憂するのではなく、すべて受け取って行こうということ。
歎異抄には、「よきことも、あしきことも、業報にさしまかせて、
ひとえに本願をたのみまいらすればこそ、他力にてはそうらえ。」
とあります。
よきことも、あしきことも業報におまかせする。
これが本願をたのむ、如来をたのむ、他力をたのむと
いうことなのですが、 私たちは どうしても、わが身を頼み、
力んでしまいます。
それが 迷いの根本であることを教えていただいているのです。
すでにおさめとられている私自身であったと目覚めるさせる、
お呼びかけが「弥陀をたのめ」のみ教えなのです。
第1724回 みんな平等に
令和8年 2月12日~
お寺にご縁の薄い方とお話をしていると、なかなか話が
咬み合いません。どうしてなのか、今はやりのAIに聞きました。
浄土真宗の教えは、能力がある特別の人だけではなく
「すべての人が平等に救われる」という独自の信仰で、
しかも、人間の努力ではなく、仏さまのはたらきで
救われると説かれています。
自己責任や自助努力が強調される中、現代人にとって
理解が難しく誤解されることもあります。
「他力」とは「他人任せ」や「努力しない」という
ネガティブな意味が強いものの、自分の力で悟りを開く
「自力」に対し、阿弥陀如来の慈悲にあふれた力(本願力)
仏のはたらきで救われるということで、自分の力ではなく
「他の力」で、仏さまの力で、これを他力の念仏で
救われるといいます。
阿弥陀如来(阿弥陀さま)の、どんな人でも必ず救う
という願い(本願)は、「南無阿弥陀仏」というお念仏を通して、
私たちに届くといいます。
ですから、阿弥陀如来の本願の話を、繰り返し繰り返し
聞き、南無阿弥陀仏を口にする生活を始めると、生きることの
意味や命の大切さに気づかされていくのです。
そして、日常の苦しみや悲しみを通して、心がだんだんと育てられて、
人生の迷いや不安を、これまでの損得や、勝ち負けの
価値観ではなく、新たな視点で受け止める力が育てられ、
これから私が、進むべき道が明らかになってきて、
こころ安らかな気持ちで日々を過ごせるようになるのです。
普通の宗教のように 私が努力して変わっていくのではなく、
仏さまの話を聞いて、新たなものの見方ができるようになると
世界が変わって見えて来て、悩み苦しみも、乗り越えていくことが
出来るようになるのです。
ですから、病気の人でも、高齢者でも 動けなくても、努力出来なくても
みんな平等に、一人残らず問題を解決することが出来るのです。
聞くだけで 誰でもみんな 安心が得られるのです。
第1723回 迷惑をかけるので
令和8年 2月5日~
「子どもに、迷惑をかけたくない」と、よく聞きます。
子どもたちに遠慮しながら生活している方が多いようで、
年忌法要なども、若い方の姿は少なく、年配者だけでお勤めする
ケースが多いものです。
浄土真宗では、「迷惑」という言葉を、少し違った意味合いで
捉えます。
「人に迷惑をかけたくない」という気持ちも大切にしつつ
誰もが「迷惑をかけずに生きられない」という視点です。
私たちは、生まれてからずっと誰かに支えられ、助けられて
生きています。
赤ちゃんは一人で何もできませんし、成長し自分で食事が
出来るようになっても、他の命をいただいて生きています。
生きるということは、誰かの助けによって成り立っており、
人は一人では生きていけず、知らず知らずのうちに
多くの人に迷惑をかけながら生きている、誰にも迷惑を
かけずに生きることは不可能と考えるのが浄土真宗の教えです。
一方 他の多くの宗派では、自らが修行を行い、戒律を守ることで
煩悩を克服し、悟りを開くことを目指します。
このプロセスの中で、他者に迷惑をかけないように
努力することが重視されるのです。
ある方は、「迷惑をかけるな」と教えるのは道徳
「迷惑をかけている」
と教えるのは宗教であるとおっしゃっています。
ところが、段々と都市化して迷惑を「かけたり」
「かけられたり」することが苦手になっていますが、
老いや病気、死といった苦悩に直面すると、誰かに迷惑をかけたり、
かけられたりする時が必ず訪れてくるものです。
お互いが支え合い生かされている生命であることを、
子どもや孫に、はっきりと教えるのは親の責任であると思います。
子どもたちが将来、あわて悩み苦しむことのないように
ちゃんと伝えておきたいものです。
近頃、葬儀や通夜も、遠慮して密かに行われることがありますが、
この世は、いかに多くの方々のお陰で生かされているのか、
親たちが迷惑をかけ、掛けられた方々を 多くの参列者を通して、
教えることが出来る最後のチャンスが、お葬式だといえるのでしょう。
第1722回 造花? 生花?
令和8年1月29日~
寒い中 多くの方が お墓参りにおいでになります。
月二回 一日と15日とか、大切な方の命日など
枯れ花にならないうちに、連れだってお参りになっています。
浄土真宗では、亡くなった方はすぐに阿弥陀如来のお導きによって
お浄土に往生し、仏様となると考えられています。
そのため、お墓は故人の魂が宿る場所と考えるのではなく、
故人を偲びながら、仏に成った亡き人からの声なき声をご聴聞する、
阿弥陀如来の教えに出会う聞法の場所であり、
教えに照らして自身の生き方を省みる場所として大切にされてきました。
たくさんの命をつないで 私は今ここにいる、
たくさんの命を受け継いでいることを感じ、
命を伝えてくださったご先祖様に感謝し、受け継いだ大切な命を
精一杯輝かせて生きることを誓い、自身の命の有限性を味わう場
とされています。
お墓参りは、日々の忙しさの中で忘れがちな自己や
人生を振り返る貴重な機会であり、自身の命のあり方を
見つめ直す大切な機会といえましょう。
ですから、お墓参りは故人やご先祖様に対して
何かをして差し上げる「供養」というよりは、
阿弥陀様とともに、ご先祖様が仏となって私たちを
見守ってくださっていることへの「感謝」を伝える場であり、
家族の歴史を語り継いだり、つながりを感じるための
大切な場所なのです。
そこで、他宗派で行われるような、故人の魂を清めたり
喉の渇きを癒す意味での墓石への散水や、仏前へのお水や
お茶のお供えすることはしません。
お花や灯明は、限りある命を仏様から教えていただくための
手立てとしてお供えします。
そのために、必ず枯れる生花を供え
「生きて、やがて死を迎える」すべてのいのちの
はかなさと尊さを教えていただくため、造花ではなく
生きている生花をおそなえするのです。
お寺の境内地にあるお墓や納骨堂の場合は まずは、
本堂の阿弥陀如来にお参りしたあとで、墓地に向かいます。
節目節目には、庫裏に立ち寄り ご挨拶をし、お寺を維持する
ためのご懇志をお届けする伝統が、浄土真宗にはあります。
まずは、ご家庭での何気ない会話や行動を通して、
お墓やお寺を身近に感じてもらうこと
特別なこととして構えるのではなく、生活の一部として
幼い頃から一緒にお墓参りに行く お墓参りを習慣化して
自然に接する機会を増やしたいものです。
第1721回 いつも私と一緒に
令和8年 1月22日~
元気だった母親が ちょっと病院に行ってくると出かけ、
帰りが遅くなって心配していましたら、乳がんだと言われたと
はにかみながら帰ってきました。
早速手術ということで、慌てて準備をして入院しましたが、
いつも台所に貼ってあった紙を持っていき、病室の壁に、
母親が貼りました。
岩本月州という、大変お念仏を喜ばれた方の言葉ということです。
「常に居ますを佛という。此処に居ますを佛という。
共に居ますを佛という。この佛を南無阿弥陀仏という。
このいわれを聞いて歓ぶを信心という。
称えて喜ぶを念佛という」。と、そこにはありました。
「常に」「ここに」「共に」ということは、
「いつも私と一緒に」ということなのでしょう。
これから手術、手術はうまくいくのか、どこかに転移はしていないのか、
とても不安な時に、南無阿弥陀仏の如来様が いまここに、共に
涙してくだっていると味わうことで、母は まったく不安な様子を見せず
平然と 堂々とした姿をしているのだろうと感じました。
後は、おまかせするだけ、人間の力では、患者の力では
どうすることも出来ない、専門家のお医者さんに、
そして、阿弥陀さまに お任せするほか 方法はありません。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と ,母親は 不安を乗り越えようと
しているのでしょう。
病院には 沢山の方が 手術や治療を待っています。
ここにいるすべての人が、皆 同じように、今後の不安を
抱きながら 入院していることだろうと思いました。
人間の苦しみ 四苦八苦 どんなに立派な人でも、どんなに
お金がある人でも、若く元気でいる人も、やがては
すべての人が 受け取る苦しみがあるのです。
その苦しみ悲しみを いつも一緒にいて、分かってくださる方が
阿弥陀さまという 仏さまなのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 と耳に聞こえる
仏さまが、いつもここに、いらっしゃると味わい
かずかずの苦しみを乗り越えていくことが出来るのだよと、
母親を通して阿弥陀さまは 教えていただいているのでしょう。
第1720回 お育ていただく
令和8年 1月15日~
浄土真宗の特徴的な言葉の一つに お育ていただくという言葉があります。
今はやりの AIで、聞いてみましたら 次のような内容が出てきました。
「お育ていただく」とは、仏様の教えや はたらきによって、
私たちが宗教的な、人として成長していくことを指します。
これは、親鸞聖人の宗教観をよく表している言葉と言われます。
この言葉には、私たちが自力、自分の力で成長するだけでなく、
阿弥陀如来(仏様)の慈悲深い願いと はたらきによって、
あるがままの私たちが受け入れられ、育まれるという意味合いが
含まれています。
つまり、仏様が私たちを「お育てくださる」という心温まる感覚です。
これを、如来のお慈悲に抱かれるという表現もします。
浄土真宗での「お育ていただく」ことは、単に知識や教養を身につけ、
立派な人間になることではありません。
むしろ、日々のできごとや事柄など、日常の出来事を通して、
「あなたはどんな人間として生きていますか?」といった、
自分自身への問いかけを受け取ることを意味します。
南無阿弥陀仏 と お念仏を口にしたり、仏様の教えを聞こうとする
気持ちが起こるのは、本来の自分にはない姿であり、仏様の純粋な
願いが自分に表れているのだと、親鸞聖人は味わっておられたそうです。
この「南無阿弥陀仏」のお念仏そのものが、如来の願いとはたらきであり、
私たちをお育てくださるものとされています。
幼い頃からお寺とのつながりがあったり、近くにいるお念仏の人
はじめ、多くの人に支えられて、生かされていると感じたりすることも、
お育てをいただくことと関連しています。
特に、人生の節目で出会う人々や、子どもの言葉やまなざしからも、
私たちが育てられていると感じる機会は多いでしょう。
幼稚園での「ののさま教育」のように、幼い頃から合掌や念仏、
礼拝といった行為を通じて、自然と仏様の心が育まれ、
いのちの尊さや倫理観が培われることも「お育て」の一環です
第1719回 未来は 後ろ 過去は 前
令和8年 1月8日~
これから迎える「未来」は 前にあるのか 後ろにあるのか
どちらにあるのでしょうか。
いつも 前を向いて 歩いていますし、車で走っていると
景色は どんどんと後ろに消えていきますので、
これから訪れる未来は 前方にあり 過去は 後方にあるように
考えています。
ところが、言葉の上では 逆で、未来は後ろ 過去は前として
使っています。
「それでは三日後にお会いましょう」とか、「ひと月後には
完成する予定です」などと、これから来る未来は
後 と言っています。
反対に、過ぎ去った過去は、一昨日のことは、2日前といい、
去年のことも、なんと一年前にといっています。
過ぎ去った過去は 後ろではなく 前と表現しているのです。
どうも未来は、前ではなく、後ろにあるようです。
ですから、前を向いて生きている私たちには、過去は見えても
未来は なかなか見えてこないものなのでしょう。
その証拠には、過去のこと、昔はこうだった、あの時は
ああだったとよく憶えていますが、あしたのこと、明後日のことは
まったく見えず、何も分かってはいません。
私たちは、生まれてからこのかた 前向きではなく、
後ろ向きに、後ずさりしながら生きてきたようです。
後ろ向きだったために、人とぶつかったり、人を傷つけたり、
見えないために、迷いの人生を生きているのでしょう。
そんな私たちに 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏を聞かせ
進む方向を、目的地を教えていただいているのが阿弥陀さまです。
見えない未来を 迷わないように お念仏で導いていただいているのです。
近頃の自動車には、バックするときには、後ろの様子を映してくれて、
カメラが付いていて、少しは安心です。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は、後ろ向きに進んでいる私たちに
迷わないよう、ぶつからないよう、教えてくれているのです。
目的地は お浄土であることを、お聴聞すると、カーナビのように
間違いなく誘導してくださるのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏に お任せすれば、見えていなくても
もう安心です。
どんなに迷っていても、どんな障害物があろうとも心配なし、
間違いなく お浄土へ、父も母も行ったお浄土に、間違いなく
到着することが出来るのです。
第1718回 念仏相続
令和8年 1月1日~
新しい年を迎え、今年も喜び多い一年でありますよう、
お念仏を確かに相続していただきたいものです。
ところで、昨年秋の巡番報恩講には、たくさんの皆さまに
お参りいただきまして、誠にありがとうございました。
その時にもお話ししましたが、近頃「相続」という言葉を
よく聞くようになりました。
相続というと、大切な方を亡くされて、その財産やお金を
受け継ぐことだと思っていますが、元々は「念仏相続」という
言葉から始まったもののようです。
この世に誕生し、生きていくには 財産があろうがなかろうが、
男であれ女であれ、誰もがみな様々な苦難に出あい、それを
乗り越えていかねばなりません。
これは、今生きている私たちだけではなく親や先輩達もみんな、
大きな悩み苦しみを持ち、必死にその問題を解決して、一生を
終わられたことでしょう。
そして、その苦悩を解決するのに、もっとも確かな方法が
あることを知り、それを次の世代の子どもや孫たちに伝えようとして、
お念仏の教えを残していただいたのだろうと味わいます。
すべてのものを必ず救いたいという阿弥陀さまの願いである
お念仏、南無阿弥陀仏を口に力強い生活をしていくことで、
辛い苦しい生活は転じられていき、味わい深い豊かで喜び多い
人生となることを、自分が経験し、それを、私たちに残して
いただいているのだろうと思います。
毎日毎日が、老・病・死と向き合い、これから何が起ったとしても、
南無阿弥陀仏のお念仏さえあれば、間違いない、大丈夫であると、
お仏壇や お寺やお墓を通して、伝え残そうとされているのでしょう。
どうか、税金のかかる財産やお金ばかりを受け継ぐだけでなく
親たちが最も残したかった宝ものを、お聴聞することで、気づき
間違いなく、確かに受け取っていただきたいと思います。
南無阿弥陀仏さえあれば、心配ない問題なし、希望に満ちた
明るい未来が開かれてくることを、聞き取り、受け継いで
いただきたいものです。
それには、お聴聞を繰り返して、南無阿弥陀仏を口にする生活を
することで、生き甲斐ある味わい深い、喜び多い生活が
はじまるのです。
ですから、お念仏を口にする生活をすることこそが、
最高の親孝行になると思います。
いくら病院に通っても、医療では解決できない問題が沢山あります。
その根本的な人間的な苦し悩みを、お寺に通い間違いなく治して
いただき、今年も力強く喜び多い毎日をお過ごしいただきたいものです。
第1717回 仏さまにないもの
令和7年 12月25日 ~
こんな話を聞きました。
仏さまにはあって、人間にないものはいろいろあるが、
逆に、人間にあって 仏さまにないものは 何ですかとの質問です。
「苦しみ」「欲望」「怒り、不安、病気や老い 生身のカラザ」
いろいろと考えましたが、
答えは、人間には、背中があるが 仏さまには背中がないということだと
いうのです。
善導大師の般舟讃に「仏心円満無背相」 という言葉のことでしょう。
私たち人間は 都合のよい人には、その正面に向かって和やかに近づき、
頼み事や願いを伝えるものです。
ところが、都合が悪くなると 向き合おうとはせず、すぐに背中を見せて
逃げてしまします。
すべての人を一人残さず救いたいと、はたらき続けておられる仏さまが
あると、聞いても、その仏様に向き合うとはせず、自分には関係無い、
もっと大事な事がある忙しいと、背を向けています。
我を忘れて育ててくれた親に対してでも、いつも背中を見せて
向き合おうとはしていません。
ところが、仏さまは どんな人にも真正面に向き合って、
何としてでも救い取りたいと、呼びかけ、はたらきかけておられると
いうのです。
無視して逃げていくものも その正面に立って、南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏といつも真正面から、呼びかけていただいていると言うのです。
どんなに沢山の人が居るところであっても、この私のためだけに
正面に来て、見守っていただいているというのです。
そのことに気づくことが出来るのか 出来ないか、それで
私の人生は大きく変わってくることでしょう。
誰の世話にもならず、一人で生きていると、我が儘勝手な私ですが、
いつも私の前に 真剣に向き合っていただいている眼差しがあることが
味わえてくると生き方が大きく変わってくるのでしょう。
子どもの頃を思い出してください、演台に立って 発表するとき、
舞台の上で 歌ったり踊ったり演技をするときのように、
私をちゃんと正面から見つめ 応援していただいている方がある、
私は期待され 心配され 感心を持って見つめられているのだと、
そのように味わえてくると、誰も見ていなくても、仏さまだけは
いつも私を正面から じっと見つめ応援していただいているのだと。
どうか緊張せずのびのびと 思いのままに、これまでの成果を 今
ここで 充分に表現していきたいものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏は 私を見つめ応援して
いただいてありがとうございます。
ちゃんと見て聞いていただいて、いかがでしたか
これでいいのでしょうかとの、問いかけでもあるのです。
今日という1日を、この瞬間を 阿弥陀さまの前で 精一杯
自分の出来ることを励みながら、南無阿弥陀仏とともに
力強く、活き活きと生活していきたいものです。
第1716回 忘れてしまっても
令和7年 12月18日~
こんな話を聞きました。
父方の祖母を、家族そろって見舞いました。
90歳を過ぎ、介護施設で生活している茶目っ気な 明るくチャーミングな
祖母を訪ねました。
部屋に入ると、よく来てくれたねと大変喜んでくれるましたが、
しばらくすると、あなたはどちらさんでしたかね。とにこやかに尋ねます。
孫であることを名乗ると ああそうそうと、懐かしそうに喜んで
くれるのですが、しばらくすると、また どなたさんでしたかねと、
質問します。そのたびに みんなが大声で笑います。
笑い声の絶えない明るい時間でしたが、父親だけは窓際に立ち、
外ばかり見て、その会話の輪に入ってはきません。
楽しい面会が終わり、また来ますね。ありがとありがと
また来てねと、明るくお別れをしましたが、
帰りの車の中で、父親がぽつりと言った一言を、忘れることができません。
実の親に、忘れられてしまうのはつらいなあー、その時は、痴呆症になった
実の母親が、自分のことを忘れてしまっていたことが、大ショックだったの
だろうと、受け取っていましたが、今、思い返すと、そればかりでは
なかったのかもしれません。
もし、自分が母親と一緒に生活することが出来ていたならば、
介護施設ではなく、自宅で一緒に生活していたのなら、あのように
自分のことを、忘れることはなかったのではないかと、悔しく
つらい思いをつぶやいたのではないかと、気づきました。
痴呆症になれば、一緒に生活していても、だんだんと分からなく
なっていくものなのでしょうが、息子とすれば、一緒に生活していたなら、
自分のことを忘れずにいたのではないかと、悔やんでの言葉だったのだろうと、
味わっています。
人間は いかに頑張っても 忘れてしまうことがあります。
どんなに可愛い子供のことでも 年を取ると、やがて忘れてしまうものです。
ところが、阿弥陀さまという仏さまは、こちらが忘れてしまっても
決して忘れることのない 仏さまです。
忘れて 無視していても、決して見捨てることのないのが
阿弥陀さまです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 声に聞こえる仏さまが
阿弥陀さまです。
自分で口にし 自分の耳で聞き、阿弥陀さまが、今 ここに
一緒であることを、どこか、遠くではなく、ここに一緒であると
味わいながら喜ばせていただきたいものです。
私が忘れても、忘れずに 私を励まし、導いてくださるのが
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の阿弥陀さまなのです。
第1715回 気づくか 気づかないか
令和7年12月11日~
お父さんに続いて 94歳のお母様が亡くなられました。
一人っ子のお嬢さんが、笑わせて撮られた笑顔の遺影に、
「良い写真ですね」とつぶやいてしまいました。
お父様の法名を見ると 院号が着いています、
「お母様もお父様のように院号頂きましょうね。」と言うと、
従姉妹の方が、「どういう意味ですか」と聞かれます。
ご本山の護持に貢献された方に贈られるもので、法名の釈○○の前に
着いているのが院号です。
お念仏の教えが今後も伝わっていくようにと、宗門の護持発展に
貢献された方に贈られるものです。
自分のお寺が繁栄するための祠堂料に加えて、ご本山もお守りしようとの
有り難い思いの方に贈られる敬称です。
院号は 生前に頂戴される方もありますが、いのち終わって
お浄土へお生まれの時に、今生最後のお布施をされることです。
ところで、同じご懇志でも、境内の墓地を整理して、離檀される方が
あります。
今回は、お子さまの無かった方の甥っ子姪っ子が、遠隔値に
お住まいで、墓じまいをされました。
合同の墓と、永代墓とありますが、どこが違うのですかと聞かれます。
永代墓は、門徒数が減ることで、お寺の維持する人数が減って、
残された皆さまにご苦労をかけますので、今後10年20年分ぐらいの
お布施をまとめてお預けしようという有り難い行いです。
一方 合同の墓は、残されたご門徒の方々への思いやりなどはなく、
これでご縁を終わらせてくださいという、どちらかというと、
自己本位の方のお考えのように思えます。
十個近くあったご遺骨を、合同墓に捨てるように立ち去っていかれました。
お寺の法要によく参加し、ご両親の年忌法要を、ちゃんと勤め
される方がある一方、まったくご縁の無い方もあります。
先祖が立派なお墓を建てていても、こどもや孫達がまったく
ご縁の無い方があります。
ちょんとお勤めをされる方々は、経済的にも精神的にも豊かな
生活をしておいでの方が多いように感じますが、
まったくご縁の方々は、暗く辛い人生の方が多いように見受けます。
ご先祖さまのはたらきかけが、あるかないかの違いなのかとも思いますが、
どうも自分を取り巻く多くのはたらきかけに、ちゃんと気づくことが出来て、
それらに感謝し対応する能力がある方と、損得勘定だけで、
自分に有利な方々には、ちゃんと向き合うものの、
静かにそっとした はたらきかけには気づかず、感謝することもなく
無視して日常を送っておられる方は、やはり、どうも、この世の中でも
うまくいかないのだろうと思います。
亡くなった父母、祖父母は、声もなく過去のことで、気づかず
無視している生活、こんな無味乾燥な生活では、人生は、生活は
うまくいかないのだろうと味わっています。
やるべきことは、ちゃんとやった方が、人生は、豊かで
有り難く喜びに満ちた生活になるもののようです。
第1714回 憶えていますか
令和7年12月4日~
ごく自然に お仏壇の前に座って 手を合わせていますが、
その最初はいつ頃だったか憶えていますか。
きっと、おじいちゃんや おばあちゃんに連れられて、いただいたお土産の
お菓子やお年玉を、お仏壇にお供えしたのが最初だったのかもしれません。
朝、学校に行く前に、仏さまにご挨拶をして、帰って来た時も、
仏さまにご挨拶をと、言われ、通信簿をもらってきたときも、
仏さまにまず報告してと、いつも、仏さまとのご縁を結んでくださった方が
おられたからなのでしょう。
生きている人だけではなく、仏間に飾ってある写真の祖父母 曾祖父母、
そして、顔をしらない多くのご先祖様達が みんな阿弥陀さまといっしょになって
この私を守り、導いてくださっているのだと、いつのまにか知らされていました。
私の人生は、自分の力の及ぶことばかりではありません。
人間の力の及ばないことがたくさんあり、自分で出来ることは一生懸命頑張り
力の及ばないことは、思い通りにならないことは、お任せする
しかないことを、先輩達は教えようとしてくれたのでしょう。
そのことを、知らなければ、自分の努力不足を嘆き、能力のないことを
悔やみ苦しんでいたことでしょう。
世の中には、多くの人がいて みんな違った考えを持って生きています。
しかし、共通する部分は 必ずあるものです。
それを、阿弥陀さまの願いとして、私たちに教えていただいているのでないか
自分の我が儘通りなるのが幸せではなく、みんなが喜べること、
皆が納得いくことがあることを、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の教えとして、
私たちに残してくれているのでしょう。
自分の行いの結果は 必ず自分に帰ってくること、地獄にいくような
生き方をしていても、必ず お浄土へ生まれさせ、仏にして活躍させる。
自分の幸せを優先させるよりも、皆んなが幸せであることが、
本当の喜びと、教えてくれているのでしょう。
自分が努力した以上に 親や兄弟や先輩 太陽や空気や自然、あらゆる力が
私を生かそう 生かそうとはたらきかけていることを、気づかせ感じさせ
感謝できる、喜べる人間に育てようとする、はたらきかけを
気づかせ 味あわせ、感じさせ、喜ばせていただているのです。
気づけ 気づけとの呼びかけが 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の
呼びかけ、はたらきかけ、
私の周りにはいらっしゃった御影です。
有り難いことです。南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1713回 何を聞くの ?
令和7年11月27日~
浄土真宗は お聴聞の宗教 聞くことが大事、聞くこと一つと言われますが、
いったい何を聞くのでしょうか。
普通 聞くというと これから何をすればいいのか 何が
必要か、ああしなさい、こうしなさいと、私が行うべきことを
聞くことだと 考えます。
ところが、お聴聞というのは、私がやるべきことを聞くのではなく、
私のために、仏さまがすでにはたらきかけていただいていることを、
聞かせてもらうのだというのです。
多くの人が、今さら聞く必要などない、もう充分にやるべきことを
やってきたと、思っています。
そこで
しかし、私がこれからやるべきことではなく、すでに、
私のためにしていただいたことを 私のためのはたらきかけ、
仏さまの願いを、知らせていただくのだというのです、そしてそれを
確認することだと言われます。
例えは余りよくありませんが、これから新たに宝くじを買いましょうではなく、
すでに当選している宝くじをいただいているのに、気づいていない私に
当選くじを持っていますよ、当たっていますよと、教えていただくようなものです。
気づかずにいる私に、すでに、私のためにはたらきかけがあり、
沢山のものをいただき、素晴らしい能力をもっていることを
気づかずにいるこの私に それを教え気づかせていただくのです。
今は人間として悩み苦しんで生きていますが、やがて
必ず 仏になって、すべての人々が 喜び多く 生き甲斐をもって
生きていける、お念仏の教えがあることを、それを伝え知らせることが出来る
仏になるのだと、教えていただいているのです。
ただの平凡な人間と思っていますが、そうではなく間違いなく
やがて仏さまになって みんなのためにはたらく未来があるのです。
そして、先だった先輩達は、阿弥陀さまといっしょになって、ずっと、
はたらきかけていただいている、
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 を口にして、堂々と生きていきなさい
あなたはもう 仏になる仲間 間違いなく仏さまになる人なのですようと。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏のお念仏ですよ。
間違いなく 仏に成る人なのですよと、呼びかけていただいているのです。
第1712回 ぼんやりしないで
令和7年11月20日~
暑さ寒さも彼岸までといいますが、ひと月遅れで やっと
暑さがおさまってきたようです。
急に冷え込んだお陰で、柿の葉やモミジなどの紅葉が、今年はいつも以上に
鮮やかです。
折角の色どりを尚一層輝かせようと、山門に近い一部分だけ
ライトアップをはじめました。
寝る前に その消灯に出て つまざき倒れ、左ひざ頭、手の平、
顔の左ホウの一部を、参道の石畳に、強く打ち付けてしまいました。
しばらく、立ち上がることが出来ずにいましたが、顔が腫れ上がるのは
さすがにみっともない、イヤだなあと思い、なんとか起き上がり、
まっすぐ冷蔵庫に、保冷剤を取り出し、近くにあったマスクを当て、
その上から、顔を冷やしはじめました。
そのうち、だんだんと本当に痛い部分がはっきりとしてきて、
顔よりも、どうも手のひら、左ひざ頭のお皿の部分が最も痛く感じます。
お皿は割れてはいないようですが、その痛い部分を見下ろすと、
ズボンが血で赤くそまっています。
おそるおそる覗いてみると、かなり出血しており、このままでは
布団に入るわけにもいかず、どうしたものかと悩みました。
膝小僧のしわしわの部分に、かさぶたができると、正座したときに
出血しそうで、固まらないように、シワをしぼめたり 伸ばしたり
しながら、眺めていると、どんどんと変化していき、傷があるのは、
三カ所のようで、そこが、黒くなっていき、やがてピンクに変わり、
出血は止まったようです。
膝小僧から、くるぶしまで 流れていた血も、赤から黒に
変化してきて、自分の体が、一生懸命に傷を治そうと頑張っている様子が
有り難く感じられてきました。
自然は、本当に素晴らしいものだと、感じながら、痛さを我慢して
しばらく眺めていました。
そして、いつまでも若いと思うな、つま先をちゃんと上げて
いるつもりでも、上がっていないもの、つまずき易くなっていることを、
改めてハッキリ知らされました。
とともに、この程度のケガですんだことに、有り難く、これが、
阿弥陀さまに守られているということだろうと、深く感じ、あじわいました。
ぼんやりとし、不注意に、行動していることを、痛さとともに
はっきりと味わわせていただき、気づかされ、有り難く、感謝の、
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を、傷が治まっていくのをじっとながめながら
お念仏させていただきました。
第1711回 阿弥陀さまのはたらきかけ
令和7年11月13日~
十年半に一度担当しお勤めする 佐賀組の巡番報恩講 先月、
10月の初旬に、五日間お勤めすることが出来ました。
そのお疲れさん、ご苦労さま会を、総代会、壮年会、婦人会の
メンバーに加えて、連日お手伝いしていただいた方々をお招きして、
日曜日の夕方に開きました。
いつものように机に椅子を置いての会では、なかなか交流ができだろうと、
本堂に机を置き それぞれに、オードブルやお寿司 おでんなどをならべて、
各自が自由に取って食べる、立食パーテー形式にしましたが
予想以上に みるみるとお料理がなくなっていき
その食欲のすごさにびっくりしました。
会の途中で、プロのカメラマンに撮ってもらった、
雅楽が入った法要三日目と、稚児が出た4日目の写真、700枚近くを
スクリーンに大きく映して、皆で見ました。
そこには、日頃なかなか見せない笑顔やご法話を聞き入る真面目な顔、
おやつの時間の、にぎやかで楽しい様子などが写っていましたが、
見ていくうちに、気づいたことがあります。
本堂になかなか座っていただけない方が、お手伝いに来て、
活躍しておられる姿が、あちこちに写っているのです。
見慣れたお顔の中に、これまでお寺では、拝見することのなかったが
方々のお顔が、沢山あり、感激しました。
仏さまの御はからいという言葉がありますが、黙々とはたらいて
いただいている多くの姿を見て、私の周りには、いろいろの
はたらきかけがあるのに、それに気づいていなかったのだけだと、
改めて味わいました。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 耳に聞こえるお念仏とともに
阿弥陀さまは 数々の多くの人を通して、あらゆるところで、
さまざまに はたらきかけていただいているのに、それを見落として、
まったく気づいていないことがいかに多いのだろうと、感じました。
いつもお世話いただく皆さま、そして、今回初めてご苦労いただきました
皆さま、本当に有り難うございました。
そして、その方々も、自分の力だけではなく、阿弥陀さまの
はたらきかけで、先だった親たちの導きで、こうしてお寺にお参りし、
法要に参加いただいたのだろうと、有り難く有り難く味わっています。
仏さまの多くのはたらきに、気づかせていただき 感激し、
感謝しております。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1710回 おかげさま お影さま
令和7年11月6日~
「ご家族はお元気ですか」と ひさしぶりに会った人から
尋ねられたときに、「おかげさまで元気です」と答えて、
いいものでしょうか。
直接には、お世話になっていないのに「おかげさまで」と言うのは
どうも抵抗を感じる人がいるのではないかとの疑問に
NHK放送文化研究所が調査したところ「おかげさまで」という
言い方に、抵抗があるのはほんの少数で、ビジネスの世界などでも
広く使われていると言うことです。
この「おかげさま」ということばは 近江商人が、
全国に行商する中で、こうして商売をさせていただけるのは
阿弥陀如来の「御蔭」であると、「おかげさまで」ということばを
大切にしながら全国を巡ったので、この言葉が広まったのだと、
司馬遼太郎さんが『街道をゆく』という紀行文集の中で
おっしゃっています。
また大阪商人は「儲かりまっか」「まあ、ぼちぼちでんな」
という挨拶を交わすと言われますが、昔は「儲かりまっか」と
聞かれると「おかげさんで」と必ず言っていたそうです。
「おかげさんで」とは仏さまのご加護によってなんとか
生きていけることを〈お陰〉と感じて、その〈お陰〉を
感謝する思想なのでしょう。
大阪商人も 非常に宗教的な心をもった人たちであると
思われます、有名な御堂筋は、東西本願寺の別院、御堂が
ある通りのことです。
「おかげさま」という言葉を言い換える 日頃からお力添えをいただき、
誠にありがとうございますなど、 “お力添え”の“お力”は、
相手の力のことを指し、”助けていただいて有り難うございます。
との意味でしょうし、
物事がうまくいっていることを“おかげさま”と同様に、
“ありがたいことに”とも、使っています。
また、スピーチや挨拶状の中では、“ご協力のたまもの”
“ご支援のたまもの”という表現を使って大勢の相手に対して
感謝の意を伝えるために
京都の西本願寺には 阿弥陀堂と 御影堂とがありますが、
御影堂の御影は、「おかげ」とも読めます。
ですから、お陰さまという漢字より、
お影さまの方が浄土真宗では 良いのではないかと感じます。
また「させて頂きます」も、阿弥陀さまのはたらきの「お影さま」と
感じる浄土真宗の教えから生まれた言葉だともいわれます。
第1709回 おまかせ おまかせ
令和7年10月30日~
お寺の坊守さんで 47歳の若さで亡くなった
鈴木(すずき)章子(あやこ)さんという方がおられました。
ガンが見つかって、5年間の闘病生活の後、昭和63年に命終られました。
鈴木さんは、入院してガンの治療に取り組まれましたが、
限られたいのち前では、世間一般の価値観が通用しなくなることに
気づかれて、「お先真っ暗」となり、ここで、はじめて
「生死」の問題と向き合うことになり、悩んでいた時、
次のような手紙を受け取ります。
八十歳を過ぎた実家のお父さんからの手紙には、
「あなたは、一体何をドタバタしているのか。
生死はお任せ以外にはないのだ。人知の及ばぬことは
すべてお任せしなさい。
そのためにお寺に生まれさせてもらって、お寺に
嫁いだのではないか。
生死はあなたが考えることではない。
自分でどうにもならぬことをどうにかしようとすることは、
あなたの傲慢である。
ただ事実を大切にひきうけて任せなさい」とありました。
(『癌告知のあとで』二一頁)
お父さんの言葉に、誰にも代わってもらえない人生であることに
はっきりと、気づいたと言われています。
仏教は、人生の苦悩を克服するために、煩悩をなくしていくことを
本来は 教えるものです。
しかし、煩悩をなくすことなどとても不可能です。
そこで、心の持ち方を転換し、視点を変えることによって、
少しでも苦悩を克服できる方法があると気づかされ、そのことを、
四人の子供達へ伝えるために たくさんの詩を残しておられます。
その中に『変換』と題する詩には
死にむかって進んでいるのではない 今をもらって生きているのだ
今ゼロであって当然な私が 今生きている
ひき算から足し算の変換 誰が教えてくれたのでしょう
新しい生命
嬉しくて 踊っています “いのち 日々あらたなり”
うーん 分かります
人間の力の及こと、及ばないことがある。
自分で やれるだけやったら 後は お任せすればいいだけ、
間違いなく
後がないと、残された日を、1日1日 引き算していくのではなく、
毎日毎日を精一杯生き抜くだけ、いのち終わってもすべてが
終わりではなく、
未来があるのです。
大きな 確かな あしたがあるのです。
第1708回 愚者になりて 往生す
令和7年10月23日~
あるお寺の掲示版に
「よい人になろうと、お寺に通ったのに、どうしようもない
人間だと知らされた」とありました。
私たちは、子どもの頃から、よい人立派な人になろうと、勉強し、
社会に出ても一生懸命に頑張ってきました。
お寺に行くのも、よい人、立派な人になれるようにと、足を運びました。
ところが、浄土真宗のお話を聞いていると、これまで気づかなかった、
自分自身の本質に気づかされてくるのです。
あの人のここが問題、あの人は、間違っていると、
周りの人を批判するばかりで、自分自身の姿は見ることは
出来ていませんでした。
親鸞聖人は、関東の門弟たちに、たくさんの消息、お手紙を
京都から書き送っておらえれます。
その中に、最晩年の88歳の時、書かれた中に
故法然聖人は、「浄土宗のひとは愚者になりて往生す」と
候(そうら)いしことを、たしかにうけたまわり候いし
(今は亡き法然聖人が「浄土の教えに生きる人は愚者になって
往生するのです」と言われたことを確かにお聞きしました)と。
親鸞聖人は、29歳から35歳までの若い間に、東山の吉水で聞いた言葉を、
それから50年以上たって大切な教えとして、関東の門弟たちに
伝えようとしておられるのです。
ここで言う「愚かさ」とは、賢いとか愚かという相対的な意味ではなく、
人間、誰もが持つ根源的な愚かさのことを指しています。
たとえば、欲望にとらわれて自分を見失ったり、自分にとって
都合の悪いものを排除しようと、他者を傷つけ悲しませたり
するような愚かさです。
「愚者になる」とは、そのようにして生きている自分自身を、
他者を見るように、はっきりと見つめ、愚者の自覚を持つことこそが、
仏の教えに出会え、まことに生きることが出来るのだと述べて
おられるのです。
自分の愚かさを自覚するということはなかなかできることでは
ありません。
私たちは少しでも自分の姿をよく見せようとし、自己弁護して
正当化して、自分自身の本当の姿からつい目を背けてしまうからです。
自分の愚かさを認めるところから、他の人を理解し、人々との
深い関わりを持つことが出来、仏の願いが聞こえてくるようになるのです。
浄土真宗は 立派な人間になって救われるのではなく
愚者になって救われる教えであると知らされると、不安がなくなり
なんと有り難いことかと喜ばれるものです。
南無阿弥陀仏の呼び声に答えて、南無阿弥陀仏とお念仏が口にし
先輩達が勧めて頂いている 真実の教えを、素直に、心ゆくまで
味わわせていただきたいものです。
第1707回 裏のはたらき
令和7年 10月16日~
こんな話を聞きました。
明治時代のことでしょうか、京都の西本願寺にお参りした人が
はじめて、水道というものに出会いました。
ひねるだけで 水が出てくるのに驚いて、旅館の人に尋ねました。
これは、どこで買えるのですかと、これは職人さんが
取り付けてくれましたが、金物屋さんにあるのではないでしょうか。
金物屋さんに立ち寄り、水道の蛇口を幾つか求めて帰りました。
帰ると早速、壁に取り付けて、みんなを集めて、蛇口をひねりますが、
当然、水は出てきません。
水道の蛇口だけで、出るわけかがないのに、それを知らなかった
という話です。
これを聞いて、素直に笑ってはおれません、同じような生活を私たちは
毎日送っているのかもしれません。
まどみちを さんの詩に
「水道のせん」というのがあります。
水道のせんをひねると 水が出る 水道のせんさえあれば
いつ どんなところでも きれいな水が出るものだというように
とおい谷間の取入口も 山のむこうの浄水池も 山の上の配水池も
ここまでうねうねと土の中を はいめぐってきているパイプも
それらのすべてを つくった人も いっさい関係ないかのように
牛乳びんさえあれば 牛乳がやってくるかのように
電灯のたまさえあれば 電灯がともるかのように
水道せんひねると 水が出る
とあります。
私たちは 表面的な目に見えることしか感じていません。
そこにつながる大きな働や力、さまざまなご苦労があったことに
気づくことなく、あれもこれも、みんな当たり前になって、感謝も
喜びもない、無感動な生活をしています。
気づくのか、気づかないか、見えるか見えないかで、人生の味わいは
大きく違ってくるものです。
そして、こうしてお念仏を口にすることが出来ているのも、沢山の
はたらきが、ご縁があってのことです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏に出あい、お聴聞することで
表だけではなく、その裏に隠れている多くのはたらきに、
思いに気づかせていただき、はじめて
感動的な有り難い豊かな人生を受け取ることが出来るのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のはたらきによって、
私に届いている大きなはたらきかけを感じ、気づかせて
いただくことが
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1706回 無税の相続
令和7年 10月9日~
おかげさまで 10年半に一度の 佐賀組の巡番報恩講は
10月1日から 五日間 多くの方にお参りいただき有り難い法要となりました。
日頃は 一日だけ法要にお参りして、それで終わりの方が多いのですが、
今回は 連続してお参りいただく方が多かったように感じました。
ご講師の渡辺崇之先生の軽快なお話に、笑いと笑顔が絶えることのない
明るく賑やかな法要となり、有り難いことでした。
ところで、毎日の法座の最後に、総代と住職が挨拶していますが、
今回は、こんな話をしました。
それぞれのお宅に上がり込んで、月忌参りや法要に伺って30年あまり、
お念仏にご縁があるお宅と、まったくご縁の無いお宅とでは、まるで
違うことをつくづく感じます。
相続という言葉がありますが、相続というと今、税金のかかる
ことばかりをイメージされる方が多いと思いますが、もともとは、
念仏相続という言葉から出てきものではないかと思います。
昔は、長男が家を継ぎ、財産も家も家業も 全部一人で受け継いでいました。
他の兄弟には、その権利はありませんでした。
現代では 兄弟がみな平等に遺産を相続できるようになってきました。
財産は、分配すれば、段々と少なくなっていくものですが、
お念仏の教えは、全員に平等に伝えても 減ることはなく、子どもや孫へ
いつまでも、そのまま受け継ぐことができるものです。
物は、使えばすぐなくなってしまうものですが、お念仏の価値観は
どんなに分けても、減ることはなく、代々伝えていくことができるものです。
税金のかかる相続ばかりではなく、先だった親たちが最も喜ぶ、お念仏を通して
感じる力、思いやりのこころ、感謝の気持ち、喜びを受け取っていき
それを確実に次の世代へ伝えていただきたいものです。
どんな宝ものにもまして、このお念仏の価値観は 有り難い財産です。
歳を取っても、病気をしても、どんな災害に見舞われても、これほど
価値があり確かなものはありません。
それを、次の世代に受け継ぐには、まず、大人の私たちがお聴聞をして、
喜ぶ姿を見せること、あんな生き方が理想だと思えるように、
力強く、明るく活き活きとした姿を見せてあげることでしょう。
それには、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏を、確かに受け取り
味わう力を身に着けることがまずは第一です。
この秋には、秋の法座も予定しています。
一月は ご正忌報恩講 そして、3月には 次の真覚寺さんでの
巡番報恩講 まずは、大人がお聴聞をして、その喜びを、感じ取って
いくことが、お念仏相続の もっとも早道だろうと、思います。
第1705回 みんな 一人残らず
令和7年 10月2日~
テレビを見ていると、観光地や事件事故でも、スマホを
手に撮影する人々の姿をよく見かけます。
今は、写真や動画を、誰でも簡単に撮ることが出来るようになりましたが、
カメラ好きで、展示会をよく開いている方からこんな話を
聞いてことがあります。
子どもの運動会で写真を撮りたいので、カメラを貸してくれと ずっと昔に
友だちから頼まれたことがありました。
そこで、誰でも簡単にとれる簡易なカメラを準備すると、友人は
初めての子どものためだから、もっと良いものを貸してくれとの注文です。
自分が日頃使っているカメラは 扱いが難しいから無理だと
いっても聞いてくれません。
無理矢理、大きな望遠レンズの着いた高価なカメラを持って友人は
運動会へ行き、大量の写真を撮って意気揚々と帰ってきました。
ところが、どれもピントや絞りがうまくいかず、まともに写った
ものは一つもなかったということです。
どんなに高級なカメラでも それを使う知識や技能がないと
何の役にも立ちません。
見かけはヤスっぽい全自動のカメラですが、
知識のない人にとっては、それが一番ありがたい立派なカメラです。
これと似て、どんなに立派な教えがあっても、
その教えの通りに修行したり、戒律を守ったり出来ない人にとっては
何の意味もありません。
すべての人を必ず救うというお念仏の教えだから、技能や知識を
持たず、努力することも出来ない人でも、間違いなく
救われることが出来るのです。
これこそが、最も立派で有り難い教えと言えるでしょう。
ある運動会でのこと、やっと歩けるようになった子どもたちの
かけっこで、わずか10メートルほどの決勝点に向かって、
すぐに走り出す子どももいれば、ゴールではなく親の方に、
来てしまう子ども、大きな声の応援に驚いて、
スタートラインの上で 泣き動けなく成った子どももいます。
いつまでたっても、泣くだけで、動けない子どもに、先生が
抱き上げで、ゴールまで走ってくれた姿を見て、あああれが
阿弥陀さまの一人も漏らさず必ず救うということだなあと、
有り難く見せてもらったという 話も聞きました。
阿弥陀さまは、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏となって、
一人も漏らさず救うと、今、はたらいていただいているのです。
いろいろ有り難い立派な教えがあっても、この私には
お念仏で救われる教え これしかないのです。
第1704回 世界中が雨の日も
令和7年 9月25日~
こんな話を聞きました。
10年ほど前の 朝の連続テレビ小説 「とと姉ちゃん」が
現在 お昼休みの時間に 再放送されています。
その主題歌は、宇多田ひかりさんの 「君に花束を」という曲です。
すばらしい歌だと聞いていますが、ある音楽番組に
この宇多田ひかりさんが出演、 司会者が質問して
「ご自分の歌で好きな歌は何ですか」との問いに、
この「君に花束を」が
「その中でも 好きな部分はどこですか」との質問に
世界中が雨の日も
ですと答えていました。
世界中が雨の日も 太陽とは
どこかで聞いた言葉のように思えますが、日頃お勤めしている
正信偈の 譬如日光覆雲霧 雲霧之下明無闇 を思い出しました。
私たちは貪りや憎しみ、愚痴などの煩悩に覆われて、
阿弥陀様のはたらきに、なかなか気づくことができませんが、
たとえ雲や霧が覆っていても、雲や霧の下にも明るさが
届いているように、阿弥陀さまのはたらきは、届いているのです。
空が、どれほどあつい雲におおわれていても、雲の下に闇はないように、
どれほどの愚かさを抱えた凡夫であっても、阿弥陀さまのはたらきは、
その愚かさが障りとならないと親鸞さまは仰っています。
自分の力で 煩悩を無くすことが出来なくても、
決して煩悩が妨げにはならないということ。
しかし親鸞さまは、
雲の上を見ようとするのではなく、雲の下に闇のないことを
驚かれました。
光はとどいている。どれほど私の愚かさの雲霧があつくとも、
阿弥陀さまのみ心は届いてくださっていた。そのことに驚かれたのです。
宇多田ひかりの 「君に花束を」
世界中が雨の日も
「その歌詞の君の笑顔の 君とは 誰ですか」との問いに
今はなき 母親 藤圭子だと、答えていました。
母親の愛 そして阿弥陀さまのはたらき どんな雨の日も
霧の日も、そのままの私を いつも見守ってくれる
そのはたらきに、気づくことができる時、ありがたさが
沸いてくるものです。
どんな時も、見守り続けてくださる はたらきがあるのです。
第1703回 あなたは どちら
令和7年9月18日~
秋の彼岸法座のご案内に、こんなことを書きました。
ある念仏者の言葉に、「人生いろいろというが、
私は二つしかないと思う、阿弥陀さまのお慈悲を聞くか、
聞かないか」の違い。
聞くことが出来れば、有り難く恵まれた人生だったと喜べるし、
聞かねば、苦しく辛い無価値な人生だったと感じられてしまうもの。
あなたは どちら・・・。
との葉書を出しました。
阿弥陀さまのお慈悲 はたらきを、お聴聞するか しないか
そのチャンスが あるか ないかで、
人生は まるで違って見え、感じられるのです。
周りから見れば、同じような人生を送っていても、有り難かったと
喜びながら 充実した生き方ができる人と、こんなに努力したのに
苦労したのに 誰も分かってくれない。
いいことは 一つもなかった、悔しい 腹が立つ と
憤りながらの苦しい人生を送る人との、違いが出てくるのです。
仏さまの話を聞くことができた人は、自分の努力 頑張りばかり
ではなく、周りの人々の努力 頑張り 思いやりなどが少しづつ
見え感じられるようになるのです。
見る目が 感じる力が育ってくると、私の努力よりも
私に対する もっともっと大きな、多くの はたらきかけがあることに
気づくことが出来るのです。
そうすると、もったいない こんなことでは 申し訳ないと
感謝とともに もっと頑張ることができるようになるものです。
お聴聞のご縁がなく、周りが見えない人は 自分のことしか
見ることができず、ひとり孤独で、悪戦苦闘する感覚ばかりで
感謝も 喜びも 生き甲斐もなく
苦しい つらい人生であると感じられてしまうのです。
そうした 感じる力 知る力を身につけるには、
仏さまの話を 仏さまのはたらきを、お慈悲を聞いていくことで、
いかに有り難い人生であるか、何と 多くの人々が 私のために
はたらきかけていただいているかに、気づき はっきり感じ
喜び、感謝の気持ちが起こってくるのです。
そのお聴聞のご縁、この 10月 1日からの巡番報恩講の五日間
またとない 尊いチャンスです。最後のご縁です。
仕事を休んでも 大事な用事を後回しにしても
このご縁にあうことは、もっとも価値があることと思います。
聞いてくれ 聞いてくださいと
先だった父母 祖父母 多くの先輩達が そろって南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏 呼びかけていただいているのです。
今しかない あしたでは遅い 今 聞いてくれと
願われているのです。
そして、 豊かな有り難い人生を 受け取って、
喜び多い感謝の毎日を送ってほしいと。
第1702回 誰も皆 86,400
令和7年9月11日~
一周忌で、「よくお聴聞されておられたご主人は、仏さまとなって、
今も 私たちのためにはたらいておられることでしょう。」
と、お話をし、最後の合掌をした後、床の間に置かれた遺影の前に、
ご本人のものと思われる腕時計が、置いてあるのに気づきました。
のぞき込んで、「あら、ちゃんと動いていますよ。」というと、
年配の妹さんが、「あらあーと」と、驚きの大きな声を出されました。
「この腕時計だけではなく、今、ご本人もちゃんと働きかけておられるのに、
こっちが気づかないだけなのでしょうね」
「そうやろね、そうやね・・・」 との高齢の妹さんの感動の声を
聞きながら帰ってきました。
時計、時間といえば、こんな話を聞きました。
すべての人に、86、400円、毎日毎日お渡ししますと言われると
とても、嬉しく有り難いものです。
だだ、次の日に持ち越すことはできず、その日のうちに
使い切ってしまわなければならないというのです。
自分の好きなものを、自由に買えて、うれしいものですが、残すことが
出来ない、使い切ってしまい貯金が出来ないのは、残念なことです。
同じように、私たちすべての者に、毎日毎日、86、400秒、
分にならすと1440分、24時間が
与えられているのです。
誰もがみんなが頂いている、86、400秒の時間ですが、
当たり前になって、感動もなく、余り喜んでもいません。
そればかりか、意識もせずにぼんやりと、無駄に使い切っています。
時には 誰かの行動や、言葉に腹を立てて、くやしい、
許せにないと、イライラ くよくよと、そのことばかりに心奪われて、
長い時間、悶々と無駄な時間を過ごすることもあります。
折角いただいている毎日毎日の86、400秒、無駄遣いをすることなく、
出来れば、喜び多い時間を多く持ちたいものです。
お金と同じく 自分の為だけに使うのではなく、
誰かの役立つこと、喜びを分けてあげることにも、挑戦するなど
意味ある使いかたを 考えて見ることも大事なことでしょう。
もし、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏を口にするご縁があれば、
平凡で 当たり前の毎日が、意味深く、有り難く、喜び多い、
素晴らしい価値ある時間であることが確認出来ることでしょう。
つらいこと、苦しいことで悩み続け、時間を無駄に使い切るより、
仏さまも 亡き父母も喜んでくださる、南無阿弥陀仏、
南無阿弥陀仏を口に、味わい深い、喜び多い、豊かな時間を
味わいたいものです。
第1701回 見る 感じる力
令和7年 9月4日~
ご本山の朝のお勤めのご法話で
私たちは見えるものだけを大事にしていますが、見えないものも
有り難く大事なものがあることに、気づいていないのではないかという
お話です。
見えないものもあるというと、金子みすゞさんの「星とたんぽぽ」の詩を
思い出します。
青いお空のそこふかく、 海の小石のそのように
夜がくるまでしずんでる、昼のお星はめにみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。
ちってすがれたたんぽぽの、かわらのすきに、だァまって、
春のくるまでかくれてる、つよいその根はめにみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。
本当に大事なもの 有り難いものは 見えないものが多いようです。
親の愛や思いやり、優しさなどを、見ること、感じることができるか
出来ないかで、 その人の人生は大きく違ってくるものでしょう。
見る力がないのか 見ようとしないのか。
それが、見えるように 感じられるようになってくるのは、
学校教育などの知識の教育だけでは不十分で、
仏さまのお話、ご法話を聞かせていただくことで
今まで気づかなかった大事で、有り難いものに気づき、
見過ごしていることに気づき、感じられるようになってくるのでしょう。
仏さまのお話を聞かせていただく中で、少しづつ
変化が訪れてくると、人生はまるで違って見えてくることに気づきます。
見る力 感じる力、味わう力、それを育てていただくことが出来きるのが、
仏法に出遇うということだと、思います。
まわりが少し見えるようになってくると
いかに多くの力に守られ育てられているか、なんと有り難く
素晴らしことかに気づかせていただけるのです。
どうか、次の世代へも この見る力、感じる力を 伝え残して
行きたいものです。
それには、南無阿弥陀仏のみ教えを受け継ぐことが、もっとも確実で
近道だと味わいます。
第1700回 感謝・喜びの効果
令和7年 8月28日~
こんな話を 聞きました。
龍谷大学の臨床心理学の先生から「感謝の効用」のお話を聞きました。
その先生は、自分の講義を受けている学生さんたちに、3カ月間、
小さな習慣を続ける実験に参加してもらったそうです。
それは、寝る前に「今日も おかげさまで 一日を 終えることができました。
ありがとうございました 」と、感謝の言葉を 3回繰り返すことです。
そして、実験に参加し学生さんには「 もし 何か 生活に 変化があれば、
メモして おいてください 」と、頼まれたそうです。
毎晩 3回 感謝の言葉を唱えることに、どんな意味があるのだろうかと
半信半疑だったようですが、3カ月たった頃、学生さんたちからは、
「 笑顔が増えてきた 」「 憂鬱な 気分が減った 」「 家族関係や
人間関係がよくなった 」「 身体的な 疲れが減った 」「 バイト先で
気遣いができるようになった 」などの 報告が あがってきたそうです。
どんな人にも、辛く苦しいことばかりではなく、うれしいこと、
感謝すべきことが必ずあるものです。
毎日 毎日 感謝の言葉を口にする、この習慣がきっかけとなって、
うれしいこと、感謝できることに 目が向くようになってくると、
神経伝達物質やホルモンのバランスよくなることが、いろいろの実験や、
研究でだんだんとわかってきたといいます。
「 幸せだから感謝するのではない。感謝できることが幸せである 」
という言葉があります。
幸せは、地位や名誉や財産などだけで決まるのではなく、ものの見方、
感じ方によって大きく変わってくるものです。
これまでの長い人生の中では、苦しいこと悲しいこと、つらいこと、
いろいろと困難なことに、どなたでも出会われたことでしょう。
しかし過去ではなく、今の自分を喜ぶことが出来る人こそ
幸せといえるでしょう。
思えば親鸞聖人のご生涯は、大変ご苦労の多いものでした。
大飢饉を何度も経験され、罪人とされ流罪にもなり、晩年には息子さんを
義絶するという悲しい出来事もありました。
社会一般のものさしでは、とても幸せとは言えない人生だったでしょうが、
もし聖人にお尋ねすることが出来れば、きっと「いろんなことがあったが、
多くの尊いご縁に よって 阿弥陀さまの ご本願に遇わせていただけた。
私ほど幸せな人生はなっかた 」とおっしゃるのではないでしょうか。
お念仏を称えることは、お念仏を聞くこと。お念仏を聞くとは、
阿弥陀さまの願いに遇わせていただき、阿弥陀さまのお慈悲の中に 今
私が生かされていると 知らされることです。
〝 感謝の言葉 〟でもある〝 お念仏・南無阿弥陀仏 〟を、称えて生きる
人生とは、まさに導かれ 護られている 有り難く、喜びいっぱいの
幸せな人生であることに、はっきりと気づかされ、味わう生活です。
親鸞聖人は 念仏者に恵まれる精神的喜びのことを「心多歓喜の益
( 心に よろこびが多いという利益 )」「 知恩報徳の益( 如来の恩を知り
その徳に報謝するという利益 )」そして最後に(やがて仏になると定まった
正定聚の位に入る )「 入正定聚の益・にゅうしょうじょうじゅのやく」との
十種の利益があると、『教行信証』に、お念仏を 口にする人が感じる喜びを
はっきりと示していただいています。
(本願寺新報二〇二四年七月二十日号掲載) 高田 文英師
龍谷大学教授 福井県鯖江市・西照寺衆徒を参照しました。
第1699回 スパイスをきかす人生
令和7年 8月21日~
電話法話の原稿を 大きな活字で印刷しようとしていますが、
その2冊目の校正をしていて、20年以上前のこんな 文章に出会いました。
お参りした時に、こんな質問を受けました。
「宗教は、どうして必要なんでしょうかね」と。
お料理が、得意そうな方でしたので、こんな答えをしました。
私たちは、毎日毎日食事をしています。
ところが、それを、いつも喜んで食べている方と、何の感動も持てず
淡々と食べている人、中には、文句をばかり言う人、
昔食べてあれは美味しかったと、目の前のものを
味わえない人など 様々な人がいます。
同じことなら、喜んで美味しく食べたいものですが、
中には、お世辞にも美味しいと言えない料理もあるものです。
どんなに高価な材料を使った料理でも、どうももう一つ
美味しさに欠けることもあります。
人生もおなじことではないかと思います。
周りからみれば、何不自由のない恵まれた生活、経済的にも
社会的にも、何の問題もない生活なのに、何か一つ足りない。
ちょうど高い材料を使って料理していながら、もう一つ味わいの少ない
お料理と共通するところがあるようです。
お料理なら、ほんの少しのスパイスをきかすだけで、もっともっと
美味しく魅力的になることもあります。
おそばには ワサビ、うどんには七味、そうめんにはショウガと、
おなじ麺類でも、違いがあります。
それぞれの料理を引き立たせて、尚一層美味しくするものがあるものです。
それを、ちゃんと知っている人と知らない人。
折角、誰かが薦めてくれるのに、大丈夫大丈夫と、いつもお醤油だけを
かけて食べているような生活を送っている人もいます。
人生でも、ほんのひと工夫、見方を変えることで 大きく
味わいが変わってくるのに、それを知らずに一生を終わって
いく人も多いようです。
宗教とは、多くの経験し、さまざまな失敗や過ちを
繰り返した先輩たちが、同じ誤りをしないように、もっと喜びを感じ
味わいを深める生き方があることを、伝え教えようとしたものでは
ないかと思います。
南無阿弥陀仏のお念仏を口にすることで、ものの見方が変えられて
同じ人生でも、ひと味違う、味わう力、味覚が育てられることを
先輩、ご祖先たちは伝えようとしているのではないかと感じます
同じ人生ならば、先輩のすすめを受け取って、味わい深い人生を、
喜び多い 感動的な人生を、送りたいものです。
第1698回 有り難い方の お通夜で
令和7年 8月14日~
先頃 いつもお参りいただいた有り難い方が 亡くなられまいした。
そのお通夜の席で こんなお話をしました。
〇〇さん 92歳の堂々とした ご一生でした。
子どものころ、鳥栖で空襲を受け苦労した話を、先日新聞に語って
おられましたが、成長後、〇〇会社に勤務 定年後は、地元で
自治会活動で活躍され、その誠実なお姿は、ここに参加されている
皆さんお一人お一人が、それぞれの場で充分にお感じになって
いることでしょう。
私が存じ上げる 〇〇さんは、お父様のご命日にご自宅に伺い
一緒にお勤めしていただく 真面目でありがたいお方でした。
お手元にお経さんの本が渡っていると思いますが、その本を
いつも持って、六ぺージからのお正信偈のおつとめしておられました。
ご自宅でばかりではなく、お寺でお彼岸や報恩講など 行事の折りには
必ずお参りになり、いつも大きな声で ご一緒に、
もう何百回と、お勤めをしておりました。
出来ますれば これから、みなさんも、〇〇さんとご一緒の
つもりで、お勤めをしていただければ有り難いことです。
お勤めの内容は、 お釈迦様が説かれた仏教ですが、それぞれの能力に
見合って、具体的にさまざまに数多く説かれています。
その中で、親鸞聖人という方が、これこそが、私のために説かれた教え
この教えでこそ、人間らしく堂々と生きていくことの出来る有り難い
教えであると、ご自分で味わい、私たちに勧めていただく内容で、
この教えこそが、お釈迦さまがもっとも説きたかった内容であると
まとめていただいているものです。
これから、みんな必ず老病死を迎えますが、その苦しみ
悩みを、乗り越えていくことの出来る 人間らしく生きぬく事のできる
南無阿弥陀仏の教えが説かれています。
このお勤めの後をした後で、毎回、必ずお話していたことが
ありますが、それは お勤めのあと、また お話しいたします。
まずは、〇〇さんとご一緒のつもりで、お勤めいたしましょう。
◎ 正信偈のおつとめ
ご一緒に おつとめいただきまして、ありがとうございます。
こうして、いつもお勤めした後、必ずお話していたことは
毎回 同じこと、ただ一つです。
お手元の経本の表紙に 浄土真宗とあります。
私たちの 科学的な頭では いのちが終われば、すべて無くなると
思っていますが、お釈迦様は この世だけではなく、自分の行いによって、
次の世界へ生まれていくのだと、教えていただいいます。
ほとんどの人は、自分で作った罪で、地獄へ生まれることになるのですが、
南無阿弥陀仏の人は お浄土へ生まれて 仏さまになって 活躍すると
教えていただいています。
ですから、もう〇〇さんは、仏さまとして 今すでにここで
はたらいていただいているのです。
残された私たちが出来ることは 仏さまになられた方が、喜んで
いただけるような生き方をすることでしょう。
それには、お念仏の教えに出あい、喜び多い生活をさせて
いただくことでしょう。 ・・・・・
このような お話をしました。
第1697回 見ていない 見えていない世界
令和7年 8月 7日~
悲しい事件が 起こりました。
外国から技能実習生として日本に来ている 青年が 住まいの近くの人を
傷つけ、殺害するという、どうしようもない悔しい事件です。
今、近くのコンビニの店員さんも、その多くは外国の若い人で
親切、丁寧で 日本人の若者には、とても出来ないほど、
立派な対応をしてくれます。
日本は 現在大変な、労働力不足だそうで、農業 工業 水産業
製造業あらゆる部門で、日本人が働きたくない、
大変な仕事を、彼らが受け持ってくれています。
技能実習法という法律では、「技能実習は、労働力の需給の調整の
手段として行われてはならない」とあるものの、現実は そうは
いかないように見受けます。
残念なことは、生活習慣の違いから、住居地で深夜まで騒いだり、
生活ゴミの出し方で、近所とのトラブルがあったりもするようですが、
受け入れる企業によって、生活の環境は大きく違っているようです。
どうも、私たちは、自分とは関係無い、余所のことだと
無関心で見て見ぬふりをしています。
お念仏の生活とは、自分の立場からだけで世間をみるのではなく
仏さまの目に 気づかせていただくことだとうと味わいます。
日頃、利害関係、知り合いかどうかなどを基準に、
世間を見ているようで、本当に狭い目でしか、世の中を見ていません。
自分に代わって、大変な仕事を、日本人が嫌がって逃れている
ことを、暑い中汗をかき、早朝や深夜、危険な仕事を
外国の若者が、最低賃金で頑張ってくれていることに、気づき、
こころに留め、見守ることが、出来るようになりたいものだと、思います。
私はちゃんと世の中を見て、何でも分かったつもりになって
いますが、仏さまから見れば、自己中心で 傲慢などうしようもない
人間に見えていることでしょう。
悲しい事件でしたが、そのことを私に気づかせてくださるため、
ご苦労だったのだと、受け止めさせていただいています。
観無量寿経が説かれるご縁となった 提婆達多が阿闍世をそそのかして
頻婆娑羅王を害させるという王舎城の悲劇、そのご縁で釈尊が
韋提希をお導きになって、阿弥陀仏の浄土を教えてくださったように
私のためのご苦労くださった方々であったと 味わえてなりません。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1696回 無駄な いのちは一つもない
令和7年7月31日~
8月が近づき、朝の日差しは、少しだけ柔らかく感じらます。
朝食の前に、墓地の草取りをしていますが、雑草の生命力の
強さに驚嘆しています。
腰を落として、手で一本ずつ根から抜き取っていけばいいのですが、
効率を求めて、カミソリで、ひげを剃るように、鍬で削ぎ取っていますので
すぐにまた伸びて、大汗をかいています。
仏さまのお話を聞いて、すこしは思いやりのある人間に育った
つもりでいますが、折角一生懸命に生きているのに、雑草だと
邪魔者扱いし、取り除き、良いことをしていると思っている自分に
気づきながらも、やめられません。
私にとっては、価値のない厄介な草ですが、仏さまの目かみれば
懸命いきているかわいい植物の一つと見えていることでしょう。
美しいものや、売れるもの 誰もが価値があると認めたものだけが
大事で、そうでないものは、無駄で邪魔だと、徹底して取り除く私、
みんな平等の いのちをいただいていると、聞きながら、
自分の都合で生きていることを感じます。
もしも、この草たちが思う存分成長し、地球を覆い尽くすことが
出来たなら、温暖化した地球は、少しは涼しくなるのかもしれませんが、
仏さまの気持ちに逆らって、悪者あつかいし排除している、人間中心、
自分中心で、生きていることに、思い当たります。
雑草だけではなく、人間を見る目も、価値のある人 ない人
私に都合のよい人 悪い人、仕分けして付き合っていますが
仏さまから見れば みんな我が子のように可愛い存在なのでしょう。
そして、仏さまは、どうか、正しく ものを見る力を身に着けてほしい、
みんなそれぞれに、なくてはならない貴重な存在であり、
無駄のもの、意味のないいのちは 一つとしてないことを 知ってほしい
気づいてほしいと、はたらきかけていただいているのでしょう。
この私のことも、今は、正しく見る目を持たない人間ですが、やがて
お浄土に生まれ、仏となって、人々に、正確に見る目を
真実を感じ取る力を、一人でも多くの人に、気づかせるために、
はたらいてほしいと、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と呼びかけ、
見守っていただいていることでしょう。
私の周りの、どんないのちも、一つとして無駄ないのちはない、
そのことに、はやく気づいてほしい、感じてほしい。
見る目が開かれてくると、この世界は この人生は なんと豊かで
なんと有り難く、すばらしいものに、見え感じられてくるものですよと。
第1695回 感じる力 知る力
令和7年 7月24日~
やっと 蝉が鳴き始めました。
いつもより 梅雨が早くあけて 暑い日が続きましたが、
その暑さの中に、聞こえてくるはずの蝉の声が 今年は
まったく聞こえてきませでした。
あまりの暑さに土壌が乾燥し、難くなって蝉が地上に
出てこれないのではないかと、心配をする声も聞かれました。
しかし、学校が夏休みになるころ、忘れることなく、地上にはいだして、
今は朝から うるさい声が響き渡っています。
蝉の一生は とても波乱に満ちています。卵から幼虫になるまでは
一年は木に留まり、梅雨のころ地上に落ちて、土の中に潜り込んで
いくのだそうです。
このとき多くはアリなどに食べられてしまうそうで、
無事生き延びたものが、それから、地中で何年もの間、生活し、
暑い夏のほんの僅かの間だけこの地上に這い出して、精一杯泣いて
泣いて、やっと子孫を残し、あっという間に、この世を去って
いくのだそうです。
暑い暑い 夏の間の僅かの間だけしか知らない蝉は、秋の紅葉の
季節や、冬の寒い時期、そして、春の新緑の様子にも気づかず、
知らずに一生を終わっていくのです。
今、子どものころを思い出すと、小学生の頃は、小学校生活がすべてで、
やがて来る中学の生活も、大人になることも、意識せず生きていました。
若く元気な時には、歳を取り老いていくこと、
病におかされて、痛かったり苦しかったりすることも、
想像できずに生きてきました。
今から思えば、その瞬間瞬間を精一杯生き、
次に来る世界があることを、意識することなく生きてきました。
蝉と人間の違い 動物と人間の違いは 前の世代の人が体験し
感じたことを、次の世代に伝え残していくことができることです。
ああすれば良かった、こうすれば良かったと、気づいたことを
感じたことを、次の世代へ伝え残すことができることです。
ところが、その先輩達の声、言葉、教えを、素直に聞き
受け取ることの大事さに、なかなか気づかずにいます。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏は、この僅か100年の人生だけが
すべてではなく、やがて生まれて往く世界があること。
蝉のように短い一生を終わっていくのではなく、次の世界があることを
教えてくださる言葉です。
その言葉を、聞き取る力が 感じ取る力があるか、ないかで、
私の一生は
今この世界がすべてではなく、次に来る世界があること、
先輩達の願いが、期待が、はたらきかけがあることに、気づく力
感じ取る力が 育ってくると、この人生は まるで違ってくるものです。
夏の短い間だけ泣き続ける蝉のように、短い一生で終わるのか
それとも、先に生きた人々の願いを聞き、この人生の大事な
意味を、有り難さを感じ取ることができれば、私の人生は
まるで違ってくるものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を聞き、口にし、願いを感じとって
素晴らしい有り難いこの人生を、精一杯生き、味わいたいものです。
第1694回 未来を開くことば
令和7年7月17日~
この体は 食べたものでつくられ
心は、聞いた言葉で育てられ
そして、未来は口にする言葉で開かれる
こんな言葉を聞きました。
たしかに、口にする母乳からはじまって、
食べることで、体は成長し 人間になることができました。
そして、人間のこころは、耳から入ってきた言葉 目で見るものを
認識することで、育てられてきました。
動物的な本能の、勝ち残ることだけではなく、協調して生活することを
学び、それそれの能力を生かし、生き甲斐と喜びを味わう力を育てられ、
生きています。
私たちは、いろいろの言葉を口にして生きていますが、もし、
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と、阿弥陀さまの与えてくださる言葉を、
口にして生きていくことに出会えた人は、これからの老病死の
苦しみに泣くのではなく、やがて仏になって、はたらくことの出来る
自分であることを知らされるのです。
どんなに丈夫な体に育っても、どんなに豊かな知識を持つ
立派な人間になっても、わずか100年の限られた人生で終わるのでは、
むなしい人生となってしまうことでしょう。
同じ人間に生まれても、口にする 南無阿弥陀仏
導かれて、永遠のいのちを、仏になることのできる
いのちを受け取ることが出来なければ 悲しい人生となってしまうのです。
頭で理解するだけではなく、口して 耳で聞くことで、
人間に生まれた目的や、親や祖先の願いに気づくことが出来
はじめて、有り難い 喜び多い 永遠のいのちを 受け取ることが
出来るのです。
たとえこの体が 高齢になり、病気をし、いのち終わっても 大丈夫な
人生を歩むことができるようになるのです。
病院に通い、薬をのむ、体のことばかり心配するのではなく、
この心のことを考えると、仏さまの願いを 仏さまのはたらきを
耳で聞かせていただくことで、はじめて、人間らしい、永遠の未来を
希望の多いありがたい人生を受け取ることが出来るのです。
それを確かにしてくれるのが、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏
自分で口に出し、自分の耳で聞くことで、 素晴らしい限りない
人生であることを味わわせていただけるのです。
この体は 食べたものでつくられ
心は、聞いた言葉で育てられ
未来は、口にする言葉で開かれていくのです。
第1693回 水道の蛇口 電灯のたま
令和7年7月10日
こんな話を聞きました。
山奥で生まれ育った青年が、はじめて街に出て水道を見てびっくりしました。
蛇口をちょっとひねるだけで、大量の水が出てくるのに感激し
おみやげに、水道の蛇口を沢山買って帰りました。
ところが、自宅で、蛇口をひねってみても
まったく水が出てこなかった。という お話です。
無智を笑っていますが、私たちも 同じようなことを
しているのかもしれません。
詩人「まどみちお」さんの詩に、こんな詩がありました。
水道のせん
水道のせんをひねると 水がでる
水道のせんさえあれば
いつ どんなところででも
きれいな水が出るものだというように
とおい谷間の取り入れ口も
山のむこうの浄水池も
山の上の配水池も
ここまでうねうね土の中を
はいめぐっているパイプも
それらすべてを つくった人も
いっさい関係ないように
牛乳びんさえあれば
牛乳がやってくるかのように
電灯のたまさえあれば
電灯がともるかのように
水道のせんをひねると 水が出る
こんな詩です。
何事も みんな当たり前、お金を払っているから、大丈夫と
思い込んで生きていますが、この私に届くまでに
多くのはたらきが ご苦労が、思いが 詰まっていることに
まったく気づかずに生きています。
私が見ている日常の景色、その背景に目を向けると、
目には見えない さまざまな力によって支えられていることに
気づかせてもらう、そのことを「ご恩」を知るといいます。
自分が称えて、自分の耳で聞く 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は
当たり前になって 無感動に生きている この私に 何事も
当たり前ではなく、有り難いご縁があることを
気づかせてくださる、呼びかけの言葉ではないでしょうか。
毎日 毎日に、不安なく お浄土への道を
一歩一歩 歩ませていただいている、多くのご縁の
お陰であったと、ありがとうございます。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 お念仏とともに
喜ばせていただきたいものです。
第1692回 ヨシ 間違いなし
令和7年 7月3日~
たとひ大千世界に みてらん火をもすぎゆきて
仏の御名をきくひとは ながく不退にかなふなり
というご和讚があります。
ご本山のお晨朝の法話で こんな話を聞きました。
自動車の運転があまり上手でない人に、上達するコツを
教えるテレビ番組がありました。
講師の先生は、自分の目で見たことを、口にだしながら運転してみて
下さいと、指導されました。
『あ 信号が黄色になった、ブレーキを踏もう』
『右側の 歩行者が横断しそう』
『後の車、車間距離が近い、無理なブレーキは避けよう。』
運転しながら 目に入ること、次に行うこと、注意すべきことなどを
声に出し、それを聞きながら運転すると、それまでと違って
とてもスムーズに運転できるようになったといいます。
人間は 目からの情報が多いものの、耳からの情報が
一番正確に伝わるといいます。
そこで、目で見た情報を 声にだすことで、確かめ、見落としやミスを
防ぐことができるというのです。
そういえば、電車の運転手さんや、工場での作業で、指をさし
声にだして、動作を確認する姿を見ますが、あれも同じように
声に出して、見落としやミスを無くそうとする工夫でしょう。
「スイッチOFF ヨシ!」、とか、「頭上 ヨシ!」
右腕を真っすぐに伸ばし、対象を見て、人差し指でしっかりと指さします。
右手の指でさしたら、右の耳元まで戻し、指さし確認したことが
本当に正しいか、本当に大丈夫かを心の中で、再確認するの
だそうです。
そして「ヨシっ!」と発声しながら右手を振り下ろす。
また、自分自身の体も、行動を起こすときには かけ声を
かけたほうがよいと、「さあ立ち上がろう」「よいしょ」と、かけ声を
かけた方が 動きやすくなるものですよと整体の先生に聞きました。
この話を聞きながら、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏も、
自分で声を出し 自分の耳で聞く、「間違いなく この私を 救いとる
仏にするぞ」、親たちは すでに仏になって私のためにはたらき、
導いておられる、そのことを、耳で確認しながら、間違いない、
有り難いことだと確認し 喜びながら 力いっぱい生きていくように、
阿弥陀さまは 勧めていただいているのでしょう。
人間は、目で見るだけではなく、耳で 聞くのが一番 安心
できるからなのでしょう。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 ヨシ 間違いなし 心配なし
ちゃんと確認しながら、今日も 元気で 自分で出来ることに
精一杯 取り組んでいきたいものです。
第1691回 尊いご縁で
令和7年 6月26日~
いろいろの価値観や宗教がありますが、他力念仏の教えほど
むずかしく、理解しがたい教えはないだろうと、ある先生は
お話くださいました。
子どもの頃から、努力こそが大事で ひとに頼らず自立することを
教え込まれて育てられ 今にいたっています。
その私が、いま、お念仏をして 他力の教えに出会えたことを
不思議とも、大変なことだととも思ってはいませんが、
これほど大変で 有り難いことはないのだと お話いただきました。
お念仏して お浄土に往生すると聞くと、ほとんどの人は
自分の努力で その努力の結果として お浄土へ生まれることが
出来るのだと 思い込んでいることでしょう。
ところが、自分の努力で 生まれる浄土は 方便化土の浄土、
疑城胎宮といわれ、お浄土に生まれても 蓮の花に
つつまれて、あたかも母親の体内にあるように、五百年の間、
仏に会わず、法を聞くことの出来ない方便の浄土に生まれると
いうのです。
『ご和讃』の初めに「冠頭讃」という和讃が二首ありますが
その一首目に
弥陀の名号となへつつ 信心まことにうるひとは
憶念の心つねにして 仏恩報ずるおもひあり
(「註釈版聖典」五五五頁)
阿弥陀如来の名号を称えながら、信心をまことに得た人は
「憶念の心つねにして 仏恩報ずるおもひあり」、
「憶念の心」というのは、いつまでも憶えていて、忘れないという心です。
いつまでも憶えていて忘れない……、そういう心が常に続いていく。
そして、それがそのまま「仏恩報ずるおもひ」になっていくと。
二首目は
誓願不思議をうたがひて 御名を称する往生は
宮殿のうちに五百歳 むなしくすぐとぞときたまふ」
浄土真宗の信心は、疑蓋無雑、つまり少しの疑いもないもの。
それを疑うと言うことは、自力の念仏になってしまう。
御名とは名号、南無阿弥陀仏のこと。
弥陀の本願を疑いながら、少しでも功徳を積もうとする、自力の念仏者は、
たとえ往生したとしても、その浄土は化土である宮殿の中に、五百年留まり
仏になることは出来ないと、大無量寿経には説かれています。
出家も出来ない 修行も出来ないこの私のことを 心配して
阿弥陀さまが、先にご苦労いただいて、南無阿弥陀仏を口にして
生きているものは 一人も漏らさずお浄土へ生まれさせ 仏にすると
はたらき続けておられるという お釈迦さまの教えを 弥陀の本願を
そのまま疑いなく、報恩の南無阿弥陀仏の生活を送らせていただくのです。
親も祖父母も 一緒に南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と
呼びかけていただいている、そのお陰で出会えたのだろうと味わい
この尊い有り難い ご縁をいただいたことを喜び、
報恩のお念仏の生活を送らせいただきたいものです。
第1690回 安心して堂々と生きる
令和7年 6月19日~
10年半に一度 当番が回ってくる佐賀組の巡番報恩講がこの秋、
10月1日から、私どもでお勤めしますので、いま準備を進めています。
佐賀組の新聞 「佐賀組報」に、当番寺院の紹介するコーナーがあり、
こんな文章を 今考えています。
父を病で亡くし、母(徳川家康のひ孫)は、叔父へ嫁ぎ、
母に代わり懸命に育ててくれた大伯母(小倉局)への感謝を
表し、鍋島藩二代藩主光茂が小倉山妙念寺を建立したと
「聞書・葉隠」にあります。
関ヶ原の戦いの後、新寺院建立禁止の法度を破り、他力念仏の
寺院を建立したのは、自力を頼む勇猛な武士から変革が
求められる中、念仏者で育ての親・小倉局の生き方のように、
報恩の生活を推奨する意図があったのかもしれません。
武士道を説く葉隠の後半、光茂の行動には、念仏者の
生き方に通ずる報恩の慈悲深い記述が随所に見られます。
そのお念仏は今も生き続いています。
婦人会手作りの記念品を準備しお待ちしています。
銀行やマンション等の中に、自然を緑を残し、安らぎの場をと。
字数に制限があり、意を尽くさない部分がありますが、
聞書といえば 蓮如上人御一代記聞書がありますが、
佐賀の葉隠という聞書は、光茂に仕えた山本常朝という家臣が
語ったものの記録です。
戦国時代の歴代藩主の伝承、記述からはじまり、平和になって
自分が経験したことを具体的に 語ったものですが、
武士道といわれるものは、浄土真宗の阿弥陀さまへ絶対的な信頼を、
阿弥陀さまに代わって、藩主への、お殿様への報恩の生活に
置き換えたものであると受け止めています。
お浄土は語られていませんが、自分がいのちを落としても、
子どもや孫は、藩主、仲間に守られるという安心感も、安心して、堂々と
死んでいける、後は大丈夫という、まるで仏教の教えを元にして
いるように感じられてなりません。
このことは、川上清吉という学者さんが半世紀前に気づき
書き残していただいています。
浄土真宗は 阿弥陀さまへの全幅の信頼、葉隠が説く武士道は
藩主への絶対的な信服、見返りを求めるのではなく、すでに
いただいているこの状況を受け入れ、報恩の生き方をすると
受け止めています。
戦国時代とは 若く元気で自分の力で努力出来ていた時代、そして
歳を重ねた今は 自分の力よりも、すでにいただいている現実を受け入れ
かみしめて感謝しながら生きる、お釈迦さまのお念仏の教え、
浄土真宗の教えが、武士道の下敷きになっているように思えてなりません。
第1689回 呼びかけ続ける
令和7年 6月12日~
朝出かける時「今日は 傘持っていって」そう言われると
こんなに青空なのに どうして傘が必要だろうかと 少し
疑問を持つこともあります。
しかし、帰る頃に 雨が降ってくると、傘の有り難さ
そして、傘を持っていくよう 声を掛けてくれた人に 感謝の気持ちが
わいてくるものです。
子どもを思って、天気予報をちゃんとチェックしてくれていた
親の思いのお陰です。
また、外出中に突然のにわか雨で 軒先に飛び込んだときには
雨宿りするその屋根の有り難さを感じつつも、雨が上がってくると
もうその有り難さは忘れています。
雨の時、傘のありがたさを感じていても、いったん家の中に
入ってしまうと、雨からずっと守り続けてくれている屋根の有り難さを
思うことはありません。
傘や 軒先の有り難さは感じても あまりにも大きなものに対しては
ほとんど気づかず 当たり前になって生きています。
友だちや仲間、先輩の小さな親切は感じていても 日常的な親の大きな
深い思いや 働かけには、なかなか気づかないものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏は 「傘を持っていって」と
呼びかけてくれた親の呼びかけに似て、経験少なく ぼんやりとしている
私のことを心配して、先手で呼びかけてくださる 仏さまの呼びかけです。
世の中のことは何事も見て、知っていると思い込み、
正確に見る力、知る力がないことに気づいていないこの私へ、
はたらきかけ呼びかけて、注意を喚起していただいているのです。
生きていくことの意味や、このいのちの行き先を、人生の本当の意味など
気づくことも、考えることもなく、ぼんやりしている
私に、心配してくださる親心の仏さまの呼びかけです。
損だ得だ、勝った負けたと、小さなものの見方で判断し
一喜一憂しながら、生きているこの私に、周りの仲間や、親の思い、
仏さまの思いに気づき 感じ取り いま自分が出来ることを
精一杯やりなさいと南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と、たえず呼びかけて
いただいているのです。
必ず救う 大丈夫 今できることを 精一杯つとめなさい、
応援しているよとの 呼びかけを聞きながら、お念仏と一緒に
力の限り生きていきたいものです。
やがて仏となって、自分のためではなく すべての人を救うはたらきをする。
先だった先輩達は もう仏となって、この私へ 南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏と 呼びかけ、見守り 応援し続けて
第1688回 言えば 良かった
令和7年 6月5日
七日七日の中陰のお勤めの時に お嬢さんが 仰いました。
「そのうち、そのうちと 思っていたのに あまりにも急なことで
言葉を交わす間も無く別れ、一言 言っておけば 良かったと
悔やまれます」と。
お母さんを若くして亡くし、お父さんに育てられたお嬢さんでしたが、
そのお父さんが突然に、息を引き取られ、お礼も別れの言葉を交わすことが
出来なかったことを残念に思う言葉なのでしょう。
若さも健康も親も 無くして、はじめてその有り難さに気づくものです。
若いときには その有り難さなど、まったく感じることはありません、
若さが むしろ悩みや苦しみの種だったりしますが、少し老いを
感じはじめる時、若いことの有り難さに 気付かされるものです。
健康も 病気になって その有り難さに気づくもの、
同じように、親が生きている間は 当たり前で、時にはやっかいな存在ですが
いざ亡くしてしまうと、はじめて、その存在の大きさ、有り難さに
気付くものです。
でも 気づいた時は、もう遅い、無くした後のことです。
親が元気な時に、生きて居る間に「本当にありがとう、迷惑かけたね」
と、一言 お礼をいって置けば 良かったと、悔やまれて
ならないものです。
私たちが、持っている科学的な知識、価値観では、
いのちが終われば、すべてが無くなってしまうというもの。
別れれば、もう永遠に会えなくなると 思っています。
しかし、お釈迦さまが説いていただている教え 仏教では
この世がすべてではなく、いのち終わっても 生まれて往く世界が
あると、あります。
自分の行いによって、その行き先は決まるといいますが、ほとんどの人は
多くの人を苦しませ、悩ませたその報いで、苦しみの世界 地獄へ
いくことになるといいます。
しかし、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と阿弥陀如来のはたらき、
「必ず救う お浄土へ生まれさせ 仏にする」との はたらきかけに
気付いた人は、
お釈迦さまのように 人々を救う はたらきをするのだと、説かれています。
ですから、お寺にお参りになり、阿弥陀さまのお話をよく聞いて
いただいていた お父様は 間違いなくお浄土へ生まれ、仏さまとなって
今もう はたらき掛けていただいていることでしょう。
「心配いらない、父さんは お浄土に生まれて仏として 活躍しているよ。
おまえの頑張りもちゃんと見ているよ。 どうか
今 自分で出来る事を、精一杯頑張りなさい、応援しているよ」と。
そのはたらきかけを 感じ取るには 仏さまのお話を、仏さまの
はたらきを、お聴聞することで 少しずつ気付かされていくものです。
その仏さまのはたらきに、気付くことが出来たならば
お父さまとは、悲しい永遠の別れではなく、いつも一緒に
いていただく 有り難い存在であると感じられてくるものです。
そのことに、気付けば 有り難い人生に 気付かなければ 悲しく
悔しい、ああすれば良かった、こうすれば良かったと、
取り返すことのできない、過去にこだわる、後悔の毎日となるものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 に出会えば、
大切な方が、いまも一緒にいていただく、明るい未来が
喜びの毎日が、訪れてくるものです。
第1687回 因果応報 自業自得
令和7年 5月29日
新聞やテレビを見ていると 重大な事件や事故が起ると、
「原因を究明して、再発を防ぐ」という言葉がよく聞かれます。
原因は何か。すぐ原因を探します。問題が起こったのには、
必ずその原因があると考えてのことです。
自分自身でも、腰が痛くなったのは、お腹が
原因は あれがいけなかったか
すぐ原因を考えます。
さまざまな出来事には、必ず原因があるというのが
仏教の基本です。 因果の道理ということ、
必ず原因があって 結果が出ている、
これが仏教の 基本的 考え方です。
「自業自得」、自分の行いは 自分に返ってくる。
「因果応報」悪いことをすれば 必ず悪い結果が出る
善いことをすれば、いつかは良い結果がくる可能性が高い。
良いことも 悪いことも 自分の行いの結果である。
自業自得 これが仏教
体に良くないものを暴飲暴食していれば やがて
必ず体に悪い影響が出てきます。
自分で原因を作って自分で、それを受け取っているのです。
良いことも悪いことも 責任は 自分にある という考え方です。
仏教は 奇跡ということは言わず、必ず原因があって
結果が出ているという考え方、因果の道理の教えです。
それも、自分で作る原因ばかりではなく、
親や兄弟 祖父母が作った原因の結果が
私に来ていることも多く、それに気づく、今のこの状態は、
自分自身の力だけでは無く 周りの誰かの努力のお陰で 私に
良い結果が出ている そのお陰である。そのご恩であると。
恩とは その原因を知るということです。
報恩講の恩、原因の因の下に 心がついています。
恩 原因に気付く 自分が作った原因ばかりではなく、
親や兄弟、周りの人々が 私のために はたらきかけて
いただいた、そのことに 気づくこと 知ることを、
恩を知る 恩を感じると言うのです。
自分中心で 親や周りの人のことを 気づかなければ
何事も当たり前、誰の世話にもならず
自分ひとりで大きくなったと思う人生になります。
恩を知り 恩に気づくと 感謝の心が芽生えてくるものです。
気付くか 気付かないか、知るか知らないかでは
その人生は大きく 違ってくるものです。
浄土真宗という教えは そうした有り難いはたらきかけだけではなく
これから何が起ころうと、どんな困難に遭遇しようと、最終的には
必ずお浄土へ生まれさせ、仏にするという阿弥陀さまのはたらき、
このご恩に気づき その恩に感謝し、報恩の生活が、出来るようになる、
有り難い 喜び多い、最強の最上 究極の教えです。
感謝出来ればありがたく、気付かなければつまらない人生で
終わってしまうのです。
南無阿弥陀仏は そのご恩に気付かせ 感謝を表すことば、
自分で口にしていますが,仏さまのはたらきの言葉です。
第1686回 期待され 待たれている私
令和7年5月22日~
お釈迦さまが教えていただいたのは、
ありとあらゆる仏さまが、南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏と
誉め称えておられる阿弥陀如来という仏さまのことです。
この阿弥陀さまは、すべての人を一人残らず 救いたい、
必ず自分の国であるお浄土へ生まれさせて、仏にしたいと
はたらいておられる仏さまであると言われます。
自分の力で、努力することが出来る、優秀な人だけではなく
この世を生きることで精一杯で、将来のことなど 考える余裕もない、
普通の人たちに、一人残らず、生き甲斐を持たせたい。
この世では、なかなか喜びを持ち、堂々と生きていくことは
難しい者でも、お浄土へ生まれさせることで、すべての人に
究極の喜びを与えたいと、口に称える南無阿弥陀仏の名号を与えて
自分の国に生まれさせ仏にしたいというのが、阿弥陀如来の願いです。
未来が明るく、確実なものとなると、今から生き甲斐を
持って、活き活きと生活できるようになるもの。
この世では、希望通りにはいかずに、嘆き悲しんでいても、
未来が明るい、明日が確実だと、苦難の今を乗り越えることが
できるものです。
必ず仏となし すべての人のために全力ではたらく
万能の力を持つ仏にするというのです。
自分の為に努力して成果を求めようとするのではなく、
人々の幸せを願い はたらきづづける仏になれるのです。
必ず活躍出来る場所があり、自分は期待され待たれている、
それが、間違いないと知ることが出来れば、
今から、生き甲斐が、喜びがわいてくるものです。
入学試験の合格通知を受け取り、春に学校が始まるのを
待っているように、会社から合格通知をもらって、
入社式を待つような
新しい役職を、新しい責任者の内示を受けた後の様に
未来が明るく、今から期待と喜びがわいてくるものです。
私が期待され待たれている、活躍する場所が
機会があることを知れば、今から生き甲斐があるのです。
お浄土は、のんびりと遊んで生活する極楽ではないのです。
仏になるとは、阿弥陀如来と一緒になって、人々を救う
はたらきに邁進する、活躍する仏になるのです。
自分の為に生きるのではなく、すべての人を救うはたらきをする
仏さまになる、未来があるのです。
私は 期待されて、待たれているのです。
南無阿弥陀仏を口にする私は、仏さまになる合格通知を
もらって、お浄土へ生まれるのを待っているのです。
明日に夢があると、今日から 喜びがあるもの。
明日孫が帰ってくる、何をしてやろうかと、心を巡らすように
やがて仏になる、何ができるか、どう働こうかと
こころ踊る毎日なのです。
第1685回 グッドタイミング
令和7年5月15日~
「熟す」という言葉があります。
機が熟すとか、成熟するというように、
物事を始めるのに、ちょうどよい時期が来る、
最高のタイミング、つまり
「ちょうど良い時期や状況になること」です。
これは、柿や梨など、果物が十分に熟して、食べごろになることに
例えて、新しい仕事などを始めようとするとき、社会の状況や
会社や組織の準備が整ったときなどに、よく
使われる表現でしょう。
「潮時を迎える」などともいいますが
潮が満ちてきて、船出するには
満潮を迎えるなど、物事を始めるのにちょうど良い時を
グッドタイミング、 時が満ちる チャンスが到来する。
今でしょう。
反対の言葉は
「青い」「未熟」「熟していない」などでしょうが、
「青い」は、人間や野菜や果物にも使います。
「未熟」は、人に、「熟していない」は物や時に使います。
どんなに有り難い立派な教えがあっても、
受け入れる体制が整わないと、なかなか出会えないものです。
若くて健康で、努力することで、自分の思い取りに
ことを進めることができると思っている間は、なかなか
気づかず チャンスがないものです。
病気をしたり、大切な人を亡くしたりして、
初めて、気づくことが出来るものです。
難しく、つらく、どうにもならない問題は、私にとって
初めての経験ですが、親や先輩達は、すでに何度も経験し、
何度も乗り越えてきた問題なのです。
お念仏の教えは、そうした先輩達の経験、体験した
解決法を集約して、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と
伝えていただいているのです。
必ず救う 心配いらない お浄土へ生まれさせ仏にする
それは、阿弥陀如来がすべての人を救うためには
この私が必要だから、一緒になって 人々を救うはたらきを
手伝って欲しい 仏になって、その力を充分に身に付けてほしいと
期待され、待たれていると言うことです。
老病死を感じるようになって その教えに出遇うタイミングが
機が熟してきたのです。
今がチャンスです。
南無阿弥陀仏の教えに出会えるには
一番いいタイミングです。 やっと機が熟してきたのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1684回 何が起ころうと 大丈夫
令和7年 5月8日~
すべての人の苦しみを取り除き、一人残らず必ず救い取ると
いう、大きなはたらきがあり、それが阿弥陀如来
お釈迦さまは説かれています。
ところが、多くの人は 自分は いま、
問題は無いので救われる必要などはないと
その教えに気づかずに、生活しています。
私たちの悩み苦しみの大きな原因となるものに、病気がありますが、
若く健康なときには、まったく関係なく、発熱したり、
痛みが出た時に はじめて 頼りにするのが 病院であり
お医者さんでしょう。
しかし、回復すると もう 忘れています。
ところで、近年は
病気の発症を防ぎ、
つながるようにする、
病気になってから、急いで治療を施し、
目的だった医療から、病気を 未然に防ぎ、心身ともに
病気になりにくい
方向が変わってきているようです。
医学と同じく仏教も、老病死の問題の解決を目的としています。
若く元気で、問題が少ない間は、まったく関係の無いものと
思われがちですが、人間
命を終えていかねばなりません。
突然、大切な人や、自分が、その老病死に出会った時、
慌てず悩まずに どのように対応すればよいのか。
老病死の問題が起こってからの、
病気になる前から、老いを迎えるまえから、どう受け入れ
対応すればいいのかを、お釈迦さまは説いて
いただいたのだろうと思います。
私たちが持っている現代の価値観では、若く 元気で
あることが
悪いこととの認識でいます。
この考え方では、刻々と、悪い方へ悪い方へと 向かっていき
最悪の状態で一生を終わることになります。
そうではなく、順調に年を重ね、順調に病気に出あい、
順調に、この一生を終わっていく、そう受け入ることの
出来る価値観をもてれば、不安も、心配も
恐れることもありません。
救うというのは、いかなる状態でも、それを受け入れ、
対応する能力を開発することを仏教では説かれており、
先輩達は、それを、ちゃんと伝え残していただいているのです。
やがて必ず来る老病死に、気づかずのんびりと生きて居る
この私に
終わっても大丈夫、人間らしく堂々と生きていく道が
あることを、常に、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と呼びかけて
知らせて
心配いらない やれることをやりなさい 後は
まかせておきなさい。一番良い方向へと進んでいきますよと。
老病死を受け入れていく力を
大丈夫、大丈夫 そう教えて
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は、何が起ころうと 思い通りに
なろうと成るまいと、順調順調 予定どおり 何の心配も要らないと
呼びかけ、教えていただいている、それを受け入れていく、
力を、身に付けることを、説き教えていただいているのです。
第1683回 よいいしょ 良い一生
令和7年 5月1日~
「よいしょ よいしょ」と かけ声をかけて 立ち上がる方があります。
腰や足が痛んで、なかなか体を動かすことができにくく、かけ声と
いっしょに、体を起こしている方が、身近には沢山いらっしゃいます。
「なさけないですね。声でも出さないと、動けません」と、
ちょっと照れながら、悲しそうな表情をなさる方もあります。
「よいしょではなく よいいっしょ、よいいっしょではないですか」と
言いますと、なかなか意味が通じないようです。
「よいいっしょ、良い一生、良い人生 だったではありませんか。
足や腰が痛くなるまでも長生きさせてもらって、本当に
良い一生、素晴らしい一生だったと思いますね。」と
「そんなことはありませんよ。本当に、辛いこと、苦しいこと、
悲しいことばかりでした。長生きすると、良いことは 何
一つもありませんよ、辛い、いやなことばかりでした」と、嘆き、
反発される方もあります。
中には、そうですね。言われてみれば、本当に有り難く
もっともっと喜んで、良いことばかりですよね。と、素直にうなづいて
今日まで、こうして生かされていたことは、本当に素晴らしい人生
良い一生であったといっても、いいのでしょうねと。」
言われる方もあります。
月忌参りなどで、一緒にお勤めをし、
阿弥陀さまのお話を聞いていただいた方は、
「そうでした そうでした、ほんとうに有り難いことでした、
いろいろなことがあったものの、皆さんのお陰で、多くの
方々のお陰で今日まで、生かされたのですね。
すばらしい一生でした」と。
どうせ、かけ声をかけるのならば、
よいっしょ、よいしょではなく、よいいっしょう 良い一生、
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と、声に出させてもらうことで、
当たり前で 平凡な、つまらない人生だと思っていたのに、
なんと有り難く、もったいなく、もっと喜ばせて
いただいてもいい、有り難い 尊い人生であったと
味わっていきたいものです。
よいしょではなく、良い一生、良い一生、有り難い
素晴らしい一生だったと、声に出す度に
この人生を、こころから喜ばせて
いただきたいものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1682回 実を結ぶために
令和7年 4月24日~
春 花が一斉に咲きほこっています。よく見ると小鳥や虫たちが
その花の周りで大活躍しています。
美しく咲く花だけに目を奪われていますが、私たちの食卓に出る、
多くの果物や野菜も、実は こうした虫たちのお陰で実を結ぶことが
出来ているのだといいます。
とこで、イチゴやトマトなどはビニールハウスで栽培されることが
多くなり、自然から隔離したハウスの中では、虫のはたらきを
人間が変わってやる大変なご苦労だろうと思っていましたら、
ビニールハウスの中には、ミツバチを、それも何千匹という
ミツバチの巣箱を置くのだそうです。
専門の養蜂家に頼むのではなく、農家が自身で買い求めて、受粉させ
美味しいイチゴやトマトが収穫出来ているのだそうです。
科学が進んでも人間の力、機械の力だけでは無理で、多くの
自然の力にたすけられていることを、知りました。
収穫までの話でなく、
収穫した後も、麹菌などの助けを借りて、味噌・醤油・酢、お酒
ワイン、漬物、パンなど、発酵させることで
味に変化をもたらし、おいしくいただいているものが多くあります。
私たち人間は、食事をすることで、外からエネルギーを入れ
肉体を維持していますが、こころ、精神面でも
外からのはたらきかけで、大きく変られていくものです。
お念仏の教えに出会えたのも、祖父母や両親、友人など、
周りの人々の はたらきかけのお陰で、物の見方、考え方が、
大きく変えられたのではないでしょうか。
ご縁に遇い、お聴聞を繰り返すことで、より一層、喜び多く、
不安がすくなり、堂々と生きていく力を受け取れるように
なったのです。
イチゴやトマトが、しっかりと実を結ぶように、この私もこの人生に
大きな花をさかせ、実を結ばせていただきたいものです。
若く元気で、自由に行動出来る時だけではなく、老病死が近づき
自分自身を自由にコントロールできなくなっても、
南無阿弥陀仏の力で生きていく智慧を受け取った人は、苦しみ悩む
ばかりではなく、感謝、感動、喜びと、生き甲斐を
手に入れることが出来るのです。
悩み苦しみ怒りの人生から、南無阿弥陀仏の力、はたらきかけによって、
新しい未来を、素晴らしい毎日を、受け取ることが出来、
人生は大きく変化し、平凡な人生が 有り難い、尊い
素晴らしい人生であると味わえるようになったのです。
第1681回 知恩報徳
令和7年 4月17日~
ご門徒のお宅にお参りすると 普段は 蝋燭と花、お香の三具足、
年忌法要などの場合、蝋燭 お花が一対の五具足で、お荘厳されています。
五具足の場合、蝋燭と蝋燭の間は、僅か 30㎝ほどのしか
離れていませんが、一つの箱から取り出した同じ大きさの蝋燭なのに
お勤めが終わるころになると、長く残っているものと
短くなったもの 大きな差がつくことがあります。
短くなったのは、より明るく燃え上がったためだけではなく
空気の流れが微妙に違っているのか、蝋がとけ出し流れ落ちている
場合が多いものです。
これを見て、人間も同じ家に、兄弟として生まれても、
あるいは同じ時代に同じ地域で誕生し成長しても、ほんのちょっと違う
環境にいるだけで、大きな違いが出てしまう不思議を、
その蝋燭を通して味わっています。
先輩達は こうしたお荘厳を通して、私たちに何を伝え、
何を感じ取らせようとしているのでしょうか。
お香も花も蝋燭も、仏さまの智慧と慈悲を表すものといわれますが、
もっと長生きし、自由に、思い通り、別の場所で活躍したいと
思っていたのかもしれません。
でも、自分の置かれたその場で、不満を言うこともなく、火が付けられ、
だまって、一生を終わっています。
ところが、私たちは、すく損だ得だ、他の人が
自分はイヤだと、我が儘ばかり言って生活していますが、
花も蝋燭も、お香もだまって自分の勤めを果たし、
我が身を焼き、その命を投げ出し、一生を終わっている。
お前の周りには多くの人々が、黙々と自分の役割を果たして、
精一杯生きていることを、はっきりと気づかせ、感じさせ、
何ごとも当たり前、無感動で過ごすのではなく、感謝することの
出来る力を身に付けてほしいと、こうしたお荘厳を受け継いで
きたのかもしれません。
知恩報徳という言葉があります。
感じ取る力、そして感謝する力が身につくと、この人生は、
とれも有り難く
伝え、教えようとしているのでしょう。
時々ではなく、毎朝 毎晩 お仏壇の前に座り、お荘厳を
目にすることで、大切な子や孫を目覚めさせよう、気づかせよう
育てようとして、代々受け継いできたものだろうと味わっています。
第1680回 相続していますか
令和7年 4月10日~
ある年配の住職さんから こんな話を聞きました。
境内にある墓地を掃除していながら、思ったというのです。
この大きなお墓、こんなに立派なお墓なのに、お子さんや
お孫さんたちは、ほとんどお参りになりません。
お墓を建立したおじいちゃんは、このお墓を通して
何を伝えたかったのか、何を残したかったのか
残念ながら、今は まだ伝わっていないようです。
そして、住職さんは、自分の力不足を、つくづくと
感じ、仏さまになられた方々に申し訳ないと思われたと。
折角、こんな立派なお墓をたて、そればかりではなく、
お寺を維持していくために沢山の御寄進をされ
次の世代へ残そうとされたのに、それが伝えたい子どもや孫へ
伝わっていない。住職の自分の責任だと思うと嘆かれました。
子どもの頃には、気づくことはできませんでしたが、
親になって、親というものは 自分のことよりも
子どもや孫たちのことを第一に考えるものです。
家を建てるときも、そこに住むであろう人々、そして、
訪ねてくる人々のことを考えて設計し建設するものです。
農家の人は、次の世代の子孫のことを思って、
荒らさないよう収穫量が増えるようにと守り育てていくものでしょう。
商売をされる方は、お客さんを大事にして、末永く取引が
続くように工夫努力されて、次の世代へ残したいと頑張って
おられることと思います。
それは、自分のことよりも、次の世代のことを考えてのこと、
境内にあるお墓もそうした先祖、先輩たちの思いがこもった
ものだろうと思います。
仏教の教えは、お釈迦様の教えですが、それに加えて
親たちの願いがこもったものです。
やがて誰にでも間違いなく、訪れる老病死の苦しみ、悲しみ
つらさを何とか乗り越えて、喜び多く生き甲斐をもって生き抜いてほしい、
そうした願い仏教の教えを通して伝えようとされたのだと思います。
お金や物などの遺産は、目に見えてはっきりして有り難いものですが、
目には見えないものの、親たちが残してくれたこの教えを
多くの時間や、費用をかけて守ってこられたその無形の遺産をどうか
しっかりと、受け取っていただきたいと思います。
文化財にも有形の文化財と、無形の文化財とがあります。
お寺やお墓やお仏壇などは、形があるものですが、その意味
はたらき効果、親の願いをはっきりと確認いただけなければ
親の思いがムダになってしまいます。
是非、親たちの願いを 有形だけではなく、無形の財産を
相続していただきたいものです。
第1679回 自分自身を 採点すると
令和7年 4月3日~
ある法座で、自分自身を採点すると 10点満点で 何点くらいですかとの
質問がありました。
日頃の自分の行いを思い起こして、多くの人が、5点を基準に
自分は 6点 いや 4点などと答える方が 大半のようで、
9点 10点などの高得点は たとえ思っていても人前ですからか
どうも少数のようです。
人並み以上に良くもなく悪くもなく 平均的な人間だと思って
おいでの方が、多いようです。
その後、質問の仕方を変えて、では、仏さまの前、阿弥陀さまの
前で、採点すると、あなたは何点ぐらいですかと、質問が変わると、
お聴聞をしている人たちは、1点とか2点とか
比較をする基準が違ってくると、その点数は
くるもののようです。
日頃は 周りの人間と比較しながら生活しているようですが、
仏さまのお話を お聴聞している人は、その基準が
時々変わってくる、自分の姿を客観的に見直すことが
出来るようになるのだろうと、思います。
長年生活していると、身体ばかりでなく心が痛かったり、辛かったり
悔しかったり 悲しかったりしますが、お聴聞することで、
そうゆう一面はあるものの 今の状態を見つめ直すと、何と有り難い
素晴らしい人生であるかが、再確認出来るものです。
それとともに、仏さまのように見返りも求めずに、親身になって
私のために はたらきかけてくださる多くの方々、大きな
力があることに気づくことが出来るものです。
自分自身を どう客観的に見つめ、どういう環境に自分が
置かれているのかを、理解し味わうことが出来ると、
人生は、有り難く素晴らしいものであることが味わえ、
感謝と喜びが感じられてくるものです。
ものの見方 味わい方で 人生は大きく違ってくるものです。
同じ人生ならば 南無阿弥陀仏と共に
喜び多い豊かな人生を受け取りたいものです。
第1678回 私と 仏さま
令和7年3月27日~
阿弥陀さま、如来さま、仏さま、
私たちは 目で見える ご本尊やお名号に手を合わせ、礼拝しています。
そこで、仏さまは、私の外にあって、いつも私を見守り、導いて
いただいているのだろうと、受け取っています。
しかし、仏さまは 自分の外ではなく 自分の内側 私と
いっしょであるとおっしゃる方に、出会いました。
その方は 「仏」という漢字と 「私」という漢字を書いて
どこが共通で どこが違うかと聞かれます。
私と 仏をよく見ていると、「のぎへん」と、
「にんべん」の横に 「カタカナのム」が書かれています。
ムの部分は共通です。
よく似ている 「私」と 「仏」
のぎへんの 横棒と下の八を消すと、にんべんになり、私が仏になります。
あるいは 仏に 一と八を加えると 私になります。
一と八 があるかないかの違い、この1と8は、 18とも読めます。
もし、貴方がお念仏の教えに出会って 第十八願の
阿弥陀如来の願いを、聞くことが出来れば、仏と 私とは
いっしょになります。
ですから、お念仏の人の仏さまは 自分の外にあるのではなく、
私といっしょの仏さまであと、気づくことができるのですよと。
その証拠には、お念仏の教えを聴聞した人は、口から
南無阿弥陀仏のお念仏、南無阿弥陀仏の仏さまが出てくださいます。
私の中の仏さまが 口を通して出てくださるのですから
お念仏の人の中には、仏さまがいらっしゃるのです。
その私は、損だ得だ、勝った負けたと必死に生きていますが、
時には、仏さまのように優しい心、思いやりのある行動も出来るものです。
こうした多様な、複雑な能力・性質を持つ私が、
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 仏さまが、私の口から
あふれ出て、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の生活をはじめると、
もう、仏となる仲間、今までの私とは、大きく違った生活が
はじまるのでしょう。
仏さまを 外に置かないで、仏さまは 私といっしょるとの
思いでの生活をしていく、これが、お念仏の生活、浄土真宗に生きる
有り難い人生であるのだろうと、味わいます。
第1677回 いつもいっしょ
令和7年 3月20日~
幼児番組で 「おかあさんといっしょ」 という長寿番組があります。
ユーチューブなどテレビ番組以外も見ることの出来る新しい型のテレビでは、
放送している時間だけではなく、いつでも 何度でも繰り返し、
幼児番組を見ることが、出来る時代になりました。
画面にくぎづけになって見とれている幼い子どもたち、
その子ども達だけにしないで、すぐ横には おかあさんがいつも、
いっしょにいてほしいものだという、そんな願いを込めての
番組のタイトルなのではないかと、画面の中には、お母さんが
どこにも登場しないのを見て、感じています。
こんな話を聞きました。
あるお宅に毎月のお参りにいくと、玄関まで4歳ぐらいの女の子が
出迎えてくれました。そして、お仏壇の部屋までついてきて、
住職さんの横に、ちょこんと座って言いました。。
「ねえ、ねえ、あたし 大阪に行くの」「そう大阪にいくの」
「うん、いくんだよ」「何でいくの」「え、知らない、大阪にいくんだもん、
だってお母さんがいっしゃだから・・・・」
こうした会話をしながら想ったといいます。
私たちも やがてお浄土へいくと、聞かされていますが、
どのようしてお浄土へいけばいいのか、よくわかりません。
子どもが、大阪にいくのに、どの列車に乗って、どこで降りるのか、
まったく分からないでいるように、私たちも お浄土へ行く路も
方法もまったく知りません。
しかし、阿弥陀さんがいっしょだから、何の心配もいりません。
任せておけば良いのです。
小さな子どもが 大阪に行くのと喜んでいるように、お浄土へは
阿弥陀さんといっしょにいくのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏が口に出るのは
阿弥陀さんがいっしょだからです。
風をひけば咳が出るように、南無阿弥陀仏がひとりでに口に
出てくださるのです。
「おかあさんがいっしょだから大丈夫」という小さな女の子と同じように
阿弥陀さんがいっしょだから、私も何の心配もいりません。
ただ、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏だけでいいのです。
お念仏の人は いつも阿弥陀さんがいっしょなのです。
何の心配いらないのです。任せておれば いいのです。
お浄土へ行けるのです。
第1676回 籠を水に
令和7年 3月13日~
「私は、仏さまの教えを聴いている時は、なるほどその通りだ、
ありがたいことだなあ、と思っているのですが、すぐにそのような
気持ちを忘れてしまいます。
まるで、穴だらけのかごで水を汲もうとしているようなものですね。」
と蓮如上人に言った人がいました。
それに対して、「かごで水を汲もうとするから大変なのでは
ないだろうか? かごを持ち上げずに、水に漬けっぱなしで
いたらどうだろか」と言われたと伝えられています。
ここでいう仏さまの教えとは、なんのことでしょうか。
私たちの心が、自分中心で自分勝手な、物差しを持って
我が儘に生きていることを教えてくださっているのです。
本堂でお聴聞している間は 自分のこの心の問題を知らされて
これではいけないと想っていても、いったん日常生活に戻ると
すぐ忘れてしまい、損得勘定で自分勝手な生き方、判断を
していることに気づいたからなのでしょう。
ここでいう「籠」とは、私のこと。
そして水とは仏法のこと。聴聞を重ねて仏さまの教えを
自分にため込もうと思っても、私が籠のように穴だらけなので、
そこから法がもれ落ちてしまう。
これではいつになっても法の水をためることができず、
自分はちっとも成長できない。どうしたらいいでしょうかと
いうことを 聞きたかったのでしょう。
それに対して蓮如上人は、
その籠を水につけよ、
つまり、「その籠を水の中につけなさい。わが身を仏法の水に
ひたしておけばよいのだ」と答えられたよ。
阿弥陀様の光は、いつでもどこでもみんなを照らしてくれています。
お寺で聴聞している時だけじゃなくて、ごはんを食べてる時も
テレビを見ている時も、友達とけんかしている時も、いつもいつも
照らしてくださっている。
私が忘れていても、私を忘れない阿弥陀様がいらっしゃる。
その光に、阿弥陀様のお慈悲にいつも心をよせることが、
「籠を仏法の水にひたす」ということなのでしょう。
どんなに聞いてもいい人にはなれない、そんなだめな自分にこそ
阿弥陀様の願いがかけられているのだよ。
そのまま来いよとの願いを聞いて、
阿弥陀様にお任せしていくこと、それを
蓮如上人は「籠を水につけよ」と教えてくださっているのでしょう。
第1675回 対治と 同治
令和7年 3月6日~
仏教に「同治」と「対治」という教えがあります。
「治」は、治療の治、政治の治、治めると書きます。
たとえば高熱が出た時に、氷で冷やして熱を下げようとするのが「対治」で、
逆に、温かくして汗をかかせて熱を下げるのが「同治」といい、
熱には熱をもって治すという、対照的なやり方があるといいます。
これは、悲しみ苦しんでいる人に、「ダメじやないか。
もっと元気を出しなさい」と、立ち直らせようとするのが「対治」で、
「辛いだろうね。よく分かるよ」と 悲しみを分かち合い、
相手の心の重荷を下ろしてあげるのが「同治」です。
「対治」は、現状を否定するのに対して、「同治」は、現状を
肯定するところから出発した考え方です。
現状を否定するか 肯定するかで 対応が違ってきます。
教育者で僧侶の東井義雄先生の著書『いのちの教え』の中に
こんな話があります。
小学校に入学以来ずっと登校拒否をしていた少年がいました。
担任の先生たちは、色々手を尽くし、「元気を出せ、頑張れ」と、
熱心に励ましましたが、どうにもならないまま六年生を迎えてしまいました。
六年生の担任になったのは、気の弱い一面がある若い先生でした。
その先生は
君も僕も、自分のことよりも、まず相手の気持ちを考えてしまうんだよね。
でも、これは、人間として一番大切なことじゃないかなあ、
お互いに、僕らのこの気の弱さ、もっと大切にし合おうね」と
呼びかけたのです。
この先生が担任になってから、登校拒否はぴたりとやんだといいます。
この先生の対応が「同治」です
一方、それまでの担任の先生たちは「対治」だったのです。
「対治」は、「登校拒否はダメだ」という考えから出発しています。
ところで、
阿弥陀さまには一切の否定がありません。
無条件で私を救いとって下さいます。
ありのままの私を受け入れて下さいます。
「頭が悪くても、気が弱くても 良いじゃないか」
「病気しようが 歳を取ろうが そのままでいい 大丈夫」
と、絶対的肯定、絶対的な許しこそが、阿弥陀さまの
大悲と呼ばれるお心なのです。
「一人漏らさず救う」といわれるのは、ここにあるのです。
これが「同治」の完全なあり方です。
そのままでよい。決して見捨てることはないからな」と。
これが私にとっては、この上もなく有り難いことです。
これは難度海(渡ることが出来ない)と呼ばれる人生を歩む
私たちに計り知れない大きな 支えになります。
阿弥陀さまは 今ここに 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と呼びかけ
はたらきかけていただいているのです。
第1674回 アリガトウ
令和7年 2月 27日~
二〇年前の電話法話の原稿を整理していましたら、こんな文章に出会いました。
千代田町の貞包哲朗先生がお書きになった御法話、その一部です。
私たちの生活は「こと、ひと、もの」で成り立っていると教えられます。
「こと」とは、毎日の世事一切の出来事、「ひと」とは、周りの人のこと、
「もの」は物品です。
周りの人への感謝の表現は、なかなか難しいものです。
そこで、先ず身近な「もの」つまり「道具」に「アリガトウ」ということから
始めようと思いました。
人は笑うかも知れませんが、ここは理屈なしに何にでも「アリガトウ」と
いうことから始めようと思い立ちました。
先ず朝、起き上がり毛布をたたむ時「一晩暖めてくれてアリガトウ」。
足を通すパンツにも「アリガトウ、一日たのむよ」
スリッパにも 「足を包んでくれてアリガトウ」。
とにかく手、足が触れるもの全てに「アリガトウ」を言う。
そのうち殊勝な自分がおかしくなって、つい笑ってしまう。
つまりひとりの時に笑顔が出ることになりました。
「これはいいなあ」とやっていると、自然に「わが身」にも「アリガトウ」が出る。
手や足、目や耳に「70年間よく助けてくれたのに今まで一度もお礼を
いわなかった。
スミマセン、アリガトウ」。
そのうち「他の人」へ、身のまわりに起こる「こと」にも、時にはアリガトウが
出るようになりました。
その結果、自然に分かって来たことが幾つかあります。
先ずは、「イライラ、セカセカ」がなくなってくることです。
何をやるにも無意識にせかせかする癖があったのが、「アリガトウ」を
言いながらすると自然にそれが消えています。
二つに、何故か心が和んで来る。すると、やることが失敗なくスムーズにできる。
三に、言っているうちに分かって来たことは「アリガトウ」と言うのが
アタリマエということ。
何故ならそれらの力添えで私の生活は成り立っている。
だから感謝の言葉はなにも特別の善い行為でも何でもない。
むしろ言うことで、自分が幸せな気分になる作用をもっていることに気付きます。
四に、不思議に、周りの人を責める気持ちが少なくなっている。
五に、何よりも面白いことは、考え方が積極的になる。
例えば、朝目覚めて神経痛で右足が痛い。
今までは「ああ、イタイ、ツライ、朝からイヤダナ」の気分で、
のそのそ起きていたのが「痛いのは、人一倍?、私の為に
働いてくれたのだ。それなのにいままで一言の礼もいわなかった。
すまなかった、アリガトウ」すると、「痛いと言っても身体のごく一部じゃないか。
手も動く、目も見える、歩くことはできる。
それなら結構じゃないか」という思い方になっている自分に気付きます。
そして前よりも気分あかるく起きていくことが出来るようになりました。・・・・
という体験談を元にしたご法話です。
アリガトウと同じように、南無阿弥陀仏も感謝の言葉、南無阿弥陀仏を
口にする生活をしてみると、アリガトウと口にする生活と同じく、徐々に
変わっていく自分が見えて来て有り難いものです。
宗教 (教育新潮社)平成十四年 二月号
第1673回 鏡で見ると
令和 7年 2月 20日~
学生の時、「鏡を見ると 左と右が逆転しているけれど 何で上下は
逆転しないのか」と問われて いろいろと考えたものの、
答えが出せずに、先生に尋ねると、
「鏡は間違いなく 左は左に 右は右に 上は上に 映しているが
自己中心の心で見ているので、左右が逆のように
教えられた話を聞きました。
この世の中のことを、私たちは ちゃんと見ているようで、
実のところ自分の都合のよいように見ているのです。
雨が降っても、嫌いな行事が中止になる雨は、良い雨であり、
楽しい行事の前では いやな、悪い雨です。
同じ現象も、自分の都合で見方が、まったく変わってきます。
私たちは 自分に都合のよい尺度を持って生きています。
そして、努力さえすれば自分の思い通り 希望通りになるもの、
思い通りになるのが幸せであると信じ、そう育てられてきました。
しかし、この世の中は、自分の思い通りになることばかりではありません。
生老病死 生まれたからには、必ず歳を取り、病気になり、
いのちが終わっていくことは間違い真実です。
ところが、他人はそうでも、自分だけは特別で、努力さえすれば
大丈夫と、思い込み、病気になるとその原因を探し、慌てています。
全ての生き物、全ての物質は、必ず変化して
やがて消滅すると、諸行無常であることを、仏教では説かれています。
刻々と変化して二度と戻らない1日1日、一刻一刻を、今、生きているのだと
説き、教えていただいていますが、自分のこととしては、納得していません。
もし今ここで、仏さまの願い 仏さまのはたらきを聞くことが
出来ると、そうした真実にはっきりと、目覚めることが出来るのです。
真実を聞くことで、当たり前の毎日が、当たり前ではなくなり 有り難い
1日1日であると知らされ、人生の味わいが深まり、今まで
知らなかった新たな喜びが 生きる力が湧き出てくるのです。
平凡な日常が、有り難い大事な1日に、転じられ感じられてくるのです。
二度と無いこの瞬間、二度と無いこの出あい、この瞬間、今を
しっかりと全力で 何事にも向き合って、生きていくことが出来るように
なるのです。
それが、仏さまの願いにかなった、もっとも人間らしい有り難い
毎日となるのです。
第1672回 今 ここに 生きる
令和7年 2月13日~
今を生きずに いつを生きる
ここを生きずに どこを生きる
昭和期の教育者として浄土真宗の僧侶として、苦難の中、精一杯
生き抜かれた東井義雄さんの言葉です。
これまでのことを思い起こすと、夢中で生活をしていた若い頃、
今現在よりも、これから未来のことばかりを考えながら生きていたように
思います。
あそこへ連絡し あれを準備して、あそこを改良しよう、それよりも
こうしたほうが良いのかも、等など、仕事のこと、その段取りに気を取られて、
今を充分に味わいながら、生きていた実感があまりありません。
お釈迦さまは、「過去は追ってはならない。未来は待ってはならない。
ただ現在の一瞬だけを、強く生きねばならない。
今日すべきことを明日に延ばさず、確かにしていくことこそ、
よい一日を生きる道である」と 説かれたといいます。
過去や未来に、こころを奪われずに、今、現在、この一瞬、
一瞬を強く生きる、こうした生き方こそが どんな時代になろうと、
歳を重ね、病気になろうと、もっとも人間らしく、生きていく生き方で
あるのだろうと思われます。
食事するときは 目の前のお料理の一つ一つに、ちゃんと向き合って、
その調理と味付けに思いをいたし、子どもや家族との時間は 二度と
無いこの瞬間を 帰ってはこないこの時を、味わいながら
仕事の時には その仕事に夢中になって、こころを、どこかに遠くに、
他のことに泳がすことなく、今 ここで 充分に生きていく、そうした人生を
味わいながら、送りたいと思います。
今生きているここで、生かされていることの実感を味わいながら、
また、東井先生には、こんなことばがあります。
自分は 自分の主人公 世界でただひとりの
自分をつくっていく
今この瞬間を 味わい深く、喜び感謝の思いを持ち、出来ることを、
やるべき事を、精一杯 限りあるいのちを、この世で残されたいのちを
生き続けていきたいものです。
それが 今 ここに生きること、ここに生きることなのでしょう。
第1671回 良かったね 母さん
令和7年 2月6日~
夕方の通勤電車に乗りました。満員で奥まで行けず
入り口に立っていると、発車直前に、三歳ぐらいの男の子が、
お母さんに手を引かれて乗り込んできました。
男の子は大人たちに囲まれ「お母さんー 疲れたあ 座りたい」と
ぐずり始めました。
仕事帰り、みんな疲れているのに 子どものその言葉に
車内は微妙な空気に包まれました。
その時、おかさんが、意外なことを言いました。
「よかったね。人気があんだね、この電車、
こんなに沢山の人が乗ってるでしょう。
この電車 とても人気の電車なんだよ。乗れて良かったね」と。
そばに立っていた高校生の男の子が、お母さんを応援するように
「この電車人気があるんだね。俺も乗りたかったんだ」
「乗れて良かったね」と、笑いながらいいました。
ぐずり出しそうだった小さな男の子は、高校生と母親を見上げて
「人気の 電車に乗れて、よかったね母さん、やったーやったー」と。
環境が変わったわけではありません。同じ満員電車でも受け取り方で
まるで違って感じられたのです。
これは、子どもだけの話ではありません。
歳を重ねてくると 体もあちこち痛く、物忘れをする、暗い気持ちで
「歳を取って 良いこと何もないね」と、愚痴る仲間と一緒にいると、
辛い苦しい人生に感じられてしまいます。
ところが、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の仏さまは、
この私に、「待ってるよ 期待しているよ、お浄土へおいでね。
と 呼びかけおられる」 こう聞くことの出来た人は、
同じ環境でも、違ってくるものです。
若いときのように、体が思うように動かなくなり、周りの
みんなに迷惑をかけ、誰にも相手にされず邪魔者扱いされ、
独りぽっちであっても、仏さまの呼びかけ、「期待しているよ、まってるよ
あなたが必要 お浄土で仏になって 多くの人を救うはたらきを
一緒にしてほしい。南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏」と
聞くことができた人は、受け取り方がまるで違います。
若い頃 合格通知を受け取って 入学や 会社に入社する日を
期待して待っていた時のように 大きな仕事が始まる前のように
希望に満ちた生活が送れるのです。
私は 期待されて待たれている。
前だった親も祖父母も、一緒に 頑張ろう 期待しているよ
と呼びかけ、待っていただいている。
そう味わえてくると、希望が 喜びがわいてくるものです。
苦しい状況でも、悲しい状況のまっただ中でも
感じ方、味わい方が 違ってくると、まるで違った世界が見えてくるものです。
私もあなたも、まもなく 仏さまとして活躍出来るお仲間 期待され
待たれていると味わいながら、この世での一日一日を
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を口にして
精一杯 生きていきたいものです。
第1670回 大丈夫 大丈夫 順調 順調
令和7年1月30日~
年忌法要のお斎で、隣の席は自動車学校の先生でした。
その先生の話を聞いていると、ああだろう こうだろうと、
勝手に、都合の良い思い込みで 運転するのが一番危険だといいます。
この道は 誰も通らないだろう、自転車が飛びだすこともないだろう
小さな子どもなど居ないだろうと、勝手に思い込んで運転することが
一番危険であると、教えてくださいました。
では、どうすればいいのか、
多くの危険があるのが公道、常に「〜かもしれない」すべての
可能性があると、前の車は 急ブレーキをかけかもしれない、
自転車が出てくるだろう、子どもが飛び出しくる、あらゆる危険が
起こる可能性があるものと思って運転すべきであると教えてくださいました.
私たちの日常の生活も、自分の都合の良いように、ああだろう
こうだろうと、思い込み、その通りにならなくて大慌てをしていますが、
不都合なことが起こるのも、当たり前 起こりえる可能性が充分にあると思い
生活すべきであるということでしょう。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は 貴方の人生 決して
あなたの思い通りにいくことばかりではありませんよ。
必ず 老病死の苦しみは 間違いなく起ってくる、それでも
間違いなくお浄土へ生まれさせるから心配しなくっていい。
これから、何が起こるか分からないが
どんなに真面目に 立派なことばかりしていても、不都合なこと必ず起こる
誰も逃れる事は出来ないこと、でも心配はいらない充分に気をつけて
生活しなさいと、呼び続けていただいているのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は ぼんやりと生きている私に 老病死が
襲ってくるのは当たり前、そのことを分かった上で 堂々と生きてきなさい
いのちが終われば必ず 仏に成るのだから、そして、今、貴方の大切な先輩は
親は 祖父母や 多くの方々は 仏になって貴方のことを心配して見守って
いただいているのですよ。
先輩達が みんな通ったこの道 決して平坦ではないが、大丈夫
今、やれることを、やるべき事を 精一杯つとめなさい、何が起こっても
大丈夫 必ず救うからねと、呼びかけていただいているのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は 仏さまがこの私に呼びかけていただいている
応援の言葉、励ましの言葉、お褒めのことば、大丈夫大丈夫、順調順調と
呼びかけていただいていると味わっています。
第1669回 マルテンを見ると
令和7年 1月 23日~
年忌法要の後、おときの席で、こんな話を聞きました。
学校給食がまだ始まらない、みんな弁当を持って登校していた思い出です。
冬になると、教室の教壇の前に大きな箱が置かれ、子供たちは
持参した弁当箱を 好きなところに入れていました。
炭火のすぐ上に置けば、お焦げが出来ることもあり、良い置き場を確保
しょうと、朝は競争になっていた。
やがて教室いっぱいに、いろいろなお料理の匂いが
お昼休憩の鐘がなると、やけどしそうに熱くなった
取り出して、弁当の蓋にお茶をもらって、お昼を食べていた。
弁当箱の中心には みんな、赤い梅干しが入っており、その酸のせいか
どの弁当箱も、中央部分は 色が変わっていたことを思い出す。
ご飯にはまだ麦が入っていた時代で、白いお米の部分だけを
すくいとって はずかしくないように 弁当に入れてくれていたのを
思い出すねと。
うちは弁当のおかずは 毎回マルテンを甘く煮たものだった、
魚のすり身を天ぷらにしたマルテンだった。ゴボウも入っていた
ごぼう天だったように思う。
親父が戦死して、母親がひとり働いていたので、ことによると、
子供心に、マルテンが美味しかった、大好きだと、親を安心させるために、
自分が言ったのかもしれないなあ。
何しろ品物のない時代、そのマルテンを買うのも実は大変だったのだろうと
今は 有り難く思っていると。
今でも、マルテンを見ると、子供の頃 そして母親の苦労を
思い出し、胸が熱くなってくるものだとも。
でも、こんなに大きくなった体も、マルテンのお陰だったのだろうなあと、
懐かしく、しみじみとお話されていました。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の声を聞くと 懐かしい母親や
おばあちゃんのイメージ、あかぎれが出来た指の溝に黒い膏薬を
ねじ込んで、頑張っていたその姿を、懐かしく有り難く
思い出すものだなあと、白が頭のお年寄りたちが、親の法事のおときで
昔を懐かしく語りあっておられました。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1668回 世間か 娑婆か
令和7年 1月 16日~
気になることがあります。
どうも、日頃、「世間では」という言葉をよく使っているようで、ある方から
注意を受けてしまいました。
「世間では」とは この世の中ではとか この娑婆世界では、
宗教心のない人々の生きている世界では、などの意味で使っていたようですが、
その場に居た方からは、世間よりも 娑婆世界という言葉の方が、
仏教的ではないですかとの助言もいただきました。
そして、注意して下さった人は、若い人をさして みんな世間のことは
よく分かっていますよと、苛立たしくつぶやかれました。
そのことを、他の人に話ましたら、世間知らずだという趣旨で発言している
ように、誤解して受け取られたのではないかとの感想も頂きました。
世間というよりも 娑婆といった方が、仏教的ではないかと言われても
それもどうも違うように感じます。
娑婆というと、仏教的な知識認識がある人が、この世のことを見て
仏の国、あるいは理想の国に対して、娑婆と表現している言葉のようにも
聞こえます。
世間という言葉は、仏教的な価値観を持つことのない人が、
もくもくと生きている世界、この複雑な人間世界という意味で使っている
言葉であったようにも思います。
中には 刑務所などにいる人が、自由な世界を意味して娑婆に出たら、
ああしたい こうしたいなどという、夢見るイメージがあるなどと、
おしゃる方もありました。
ところで、浄土真宗本願寺派では、教学を専門に研究する組織があり、
ネットを使って、いろいろお聖教の検索が出来ます。
それを使って、浄土三部経というお経で、娑婆と世間という単語が
説かれている箇所を検索すると、世間が 27回 娑婆が1回。
その中で、これこそ真実の教といわれる、仏説無量寿経では、
世間が24回 娑婆が0回 という結果が出てきました。
親鸞聖人の書かれた教行信証では、世間が58回 娑婆が29回
蓮如上人の御文章では 世間が10に対して 娑婆が2、断然
世間という言葉が多いことも分かりました。
これは お師匠の法然聖人の選択集では 10件の世間 4件の娑婆
親鸞聖人が 世間を多く使われたのは、この流れによるの
だろうと、思われます。
そして、真宗の聖教全体では、233の世間と 130回の娑婆。
どうも、日常的に使っていた世間という言葉は、お聖教の勉強会などで
講師の先生が、この私たちの生きて居る世界のことを 娑婆というより、
世間、世間ではと、仰っている言葉のオウム返しをして使っている言葉で
あったように感じています。
それにしても、娑婆という言葉よりも、世間という言葉が 浄土真宗の
お聖教では、とても多く使われていることを、改めて知りました。
第1667回 これもご報謝
令和7年 1月9日~
年末から お正月の三が日 お寺の境内にあるお墓には
多くの方々がお参りに なりました。
お子さんを連れた方が 多かったのは 有り難いことですが、
本堂へ上がって、お参りの方は 少数で ちっと残念な風景でもありました。
中には お正月の晴れ着の方もあり、近くの神社へ
初詣の方もあったのかもしれません。
親戚でもない神様は 誰にでも一律でしょうが、身内のご先祖さまは
自分だけには 特別扱いで、わがままな願いを聞いてくれる
のではないか、かなえてくれるのではないかとの
ほのかの願いが、あっての墓参りかもしれません。
ところで、当妙念寺の電話サービス 初期のころのお話を、まとめて
印刷しようと準備していますが、その中で、こんな言葉がありました。
マザーテレサさんのお母さんは、常日頃、
「大切なのは 貴方がやりたいことを知ることではなく、
神様が望まれることを知ることです」と、言っておられたと。
私たちの場合は、自分のわがままな願いを聞いてもらうのではなく
阿弥陀さまの願いを 聞きとることが大事といえるのでしょう。
また、浄土真宗は、職業であるならば、猟漁をも商い奉公をもせよ、
出家しないで、家にいるままでよい、欲のあるままでよい、
そのまま必ず救うと。
そこで日常の生活は、すべて報謝であると心得えての
生活をするといい、農業の人は、鍬の一打ち 一打ち
大工さんお場合には 槌のひと打ち 一打ちが 皆ご報謝と
思って生活しようではないか。
お仏壇の前で お念仏するときだけが 報謝ではなく、
朝起きてから晩寝るまで、すべてがご報謝のしどおしと成るように
生活するのが 浄土真宗の報恩感謝であると
教えていただいてもいます。
そして、
感謝するから 幸せなのだ という言葉もありました。
令和7年 1月2日~
本堂正面に今年は、絹の紫色の幕を張っています。
いつもの木綿の幕に比べて 軽く色も鮮やかですが、残念ながら
たたみシワが はっきりと見える欠点があります。
木綿幕の時には、霧吹きをして、そのシワを
伸ばしていましたが、絹製でも同じようにしても良いのか、
ネットで調べてみましたが、絹は水が大好きですと書かれており、
お風呂掃除用洗剤のボトルをよく洗い、そこに
水を入れて シュシュと吹き付けて、たたみシワを立派に
伸ばすことが出来ました。
昭和48年 3月 川崎みやと、寄進者の名前と
「宗祖親鸞聖人、御生誕800年記念」とあり、今から50年前に
御寄進いただいたもの、シワが取れ
太陽があたると
ところで、こんな話を聞きました。
一人住まいだった母親を亡くし、故郷に帰って
遺品を整理をしいたときのことです。
母のタンスの上に 一つの箱が置かれていました。
それを開くと、中学、高校の時 夢中だった
野球のユニホームが 綺麗に洗って 入っていました。
太ってしまい、もう着ることはできませんが、母親が
捨てずに大事に保存していたのが意外でした。
そして、ユニホームの下には、小学生、中学生、高校生の
通信簿が順番に全部 そろって入っていました。
自分の子どもや妻に、とても自慢出来るような内容ではなく、
そのまま捨ててしまおうと ゴミ袋に入れようとしましたが,
箱の一番下に、母親の字で 「マー君 よく頑張ったね
貴方は私の宝ものです」と書かれた紙が 張ってあり、
捨てるのを思いとどまりました。
お通夜 そして葬儀、初七日と ご住職の話で
南無阿弥陀仏のことを、
「任せない あなたを必ずそのまま救う 親だから」と
南無阿弥陀仏の意味を教えていただきましたが、
ただひたすらに、この私のことを見守り続けてくれた母
今まで気づかなかっただけ、
何の条件もなく、私の頑張り努力の結果ではなく、
そのままの私を 受け入れてくれていたことを知りました。
そして阿弥陀さまの国で 仏になった 今も 私を見守り続けているのだ、
だろうと気づきました。
もっと頑張りなさい、努力しなさいではなく、よく頑張ったねの
言葉に、安心しホットしました。
任せない あなたを必ずそのまま救う 親だからと
の言葉が 有り難く。
いま仏になった母親が、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と
呼びかけているのだろうと。
この故郷へは 帰るつもりはまったくなかったのが、今
定年後、帰って親たちが生きてきた世界を見直してみようと
思うようになってきました。 と
第1665回 浄土真宗は 有り難いですね
令和6年 12月26日~
こんな話を聞きました。
あるご住職が、普段着に着替えず、布袍を着たままで
銀行に行かれた時の話です。
ATM 現金自動預け払い機の前に行くと、長い行列が出来ていました。
カンターにある受付の方を見ると、そこには、お客さんの姿がありません。
申し込み用紙に、名前などを記入したり、ハンコを押すのが
面倒なので、みなさん機械の方に、並んでいるのでしょう。
このまま 立ってじっと待っているよりも、あっちの方が早いかもしれないと、
申し込み用紙に、必要事項を記入して、奥の窓口の方に向かいました。
受付の女性の方は、「いつも有り難うございます」と、挨拶した後、
「ご住職は 何宗ですか」と、尋ねられ、びっくりしました。
記入する欄に、宗派を書く必要があって それを忘れていたのかと
一瞬思いましたが、自分が僧侶の布袍の姿だったので、
尋ねられたのだろうと、気づき、「浄土真宗ですよ」と、答えたそうです。
すると、その女性は、「そうですか、浄土真宗は有り難いですね」と
にこやかに仰います。
突然の言葉に、驚きながら、見つめ返すと、その女性は
「大好きな 祖母を先日亡くしまして、悲しくて、辛くて 落ち込んでいましが
ご住職が、死んだら すべてが終わりではなく、
お浄土に生まれて 仏さまになられて 私たちに
はたらきかけてくださっているのですと、教えていただいて、
ほっとしました。
悲しさが少し消えて 嬉しくなりました。死んでしまったのではなく
おばあちゃんは 生まれたんだと聞いて、浄土真宗は 有り難いですね」
と、手続きをしながら、仰いました。
いつもお会いするご門徒ではなく、まったく関係のない銀行の窓口の
人に、浄土真宗は有り難いですねと、言われて、気づきました。
子供のころから、お浄土がある、仏様になると、繰り返し聞いて
いましたので、当たり前になっていました。
そして、誰もがみんな そのことが分かっている、知っているものと、
思い込んでいました。
しかし、多くの人が そうではなく、亡くなった人はどうなるのか
自分が死んだらどうなるのか、心配しながら生活しておられるのだと、
改めて気づかせていただきました。
近頃 お仏壇の無い家で 子供たちは育っています。
きっと多くの若者が、お浄土があることも、仏さまになった方が
はたらきかけていただいていることも、まったく知らずにいるの
だろうと、思います。
大切な方を亡くした人に、「浄土真宗は 有り難いですね」と言われ、
この言葉が、新鮮に聞こえ、とても嬉しく、有り難く味わわせていただきました。
私たちは、もっともっと 素直に お浄土があることを、
喜んでいいのだと思います。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1664回 良いことをするときには
令和6年 12月19日~
令和6年の正月は、早々に 大きな地震が発生、そこに
救援物資を、繰り返し運んでいた海上保安庁の飛行機が、羽田空港の
滑走路で事故に遭遇し、大変悲しい辛い年明けとなりました。
その事故原因調査が進められていますが、飛行機に設置されていた
ボイスレコーダの解析などから、残念ながら
滑走路手前で待つべきところを、
事故の原因だったようです。
普通は、機長、副機長が管制官からのことばを、再確認するものの
ようですが、被災地へ何度も救援物資を運んでいるこの飛行機を
最優先に、出発できるよう、周りが誰もが配慮してくれているとの、
誤解が、思い込みがあったようです。
人は 自分の為、自分の利益のために努力しているときなど、
どこか後ろめたさがあるためか、充分に配慮して行動しますが、
良いこと、人に為になることに邁進しているときには、どうしても
注意が散漫になることがあるようです。
周りのみんなが、自分と同じように考えて、心配りをしているのだろう
誰もが自分たちと同じ気持ちでいると思い、感じて、突き進んで
しまうことがあるようです。
良いことをするときには、ついつい間違いを起こしてしまうものです。
悲しいことですが、辛いことですが、人間はそのように出来ているようです。
そして、僧侶である自分もまた、仏さまの教え、仏法を多くの人に
知ってもらおうと、良いことをしていると思い、注意を怠り
周りの人や 相手の気持ちに無頓着になって、突き進んでいるのだろうと、
このニュースを聞きながら感じています。
良くないこと、自分にとって有利なこと、少し後ろめたいこと、
恥ずかしいことを 実行するときのように、良いこと、人の為になることを
するときには、油断せずに
かえってマイナスに
心にかみしめています。
何がご縁になるか分かりませんが、力まずに 淡々と お念仏の
味わいを 表現することで、後は 仏さまのはたらきに お任せ
することだと、意気込まないことが大切だろうと思います。
日頃、車で走るときも、横断歩道でないところを、歩行者が横切ろうとして
いるときなど、安慰に道を譲るのではなく、周りをよく注意をして
行動しないと、親切にしたことが、かえって悲しい結果を
もたらす事があるものと思います。
自分が、良いことをしていると思ったときには、慢心にならずに
充分に気をつけて、周りをよく見ながら、誰もが自分と同じ考えではないと
意識しながら、行動することが大事であると 改めて感じています。
第1663回 絵本の読み聞かせ
令和6年 12月12日~
大阪に行信教校という 浄土真宗の専門学校があります。
そこの校長先生だった方が、こんな話をされたことがあると
いいます。
子どもが夜寝る前に 親が絵本を読み聞かせて
寝かしつけることがあります。
その絵本の内容を 子どもに伝えようということよりも、
子どもに添い寝して
ちゃんと母さんは 父さんはここに居るよと
寄り添うことで、子どもは安心して眠りにつけるのです。
浄土真宗のお説教は この読み聞かせと同じようなもの、
辛いこと悲しいこと悩み苦しんでいるこの私に、心配しなくていい
いつも一緒にいるから
南無阿弥陀仏と 阿弥陀さまが
繰り返し繰り返し 聞かせていただくのだと、
教えていただいたと言います。
先日亡くなった 詩人の谷川俊太郎さんが、若いお母さんの質問に
こんな答えをしたと聞きました。
私は、夜になると、一日が終わることと、いつか死ぬことが怖くて
怖くて泣いていた子どもでしたが、娘も同じように「死ぬのが怖い」と
夜な夜な泣く子です。母親として、どんな言葉をかけてやったら
いいのでしょうか、という質問です。
これに対して谷川さんの答えは「抱きしめて、母さんも死ぬのが
怖いと
「大丈夫 大丈夫ではなく、母さんも怖いよと伝えること。
人は誰でも死ぬ。みんな怖いのです。
抱きしめてそのことを、子どもに伝えてあげたほうが良い」と。
詩人の谷川さんは、そんなときには言葉ではなく
しっかりと抱きしめて 一緒に泣いてあげることですよと。
言葉を大事にしている方が、言葉ではなく、寄り添い
抱きしめてあげることですとの意外な回答だったと言います。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏も 阿弥陀さまがいつも一緒だよ
何があろうと、どんなことがあろうと、私が一緒だよと
呼びかけ、私を抱きしめてくださっている、そう味わうことで
どんなことが起こっても、何があっても、この人生は 安心です。
それには、繰り返しお聴聞することが大事なことです。
そして、阿弥陀さまと一緒になって、今は亡き、父も母も
祖父母も私の大切な人が、みんな揃って、私を見守り 抱きしめ
支え続けてくださっていることを、自分でお念仏し、耳で
南無阿弥陀仏の声を
安心して
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は、その呼びかけの声です。
第1662回 ハッピーバースデーだね
令和6年12月5日~
こんな話を聞きました。
とても熱心で、厳しく、しかし誰にでもやさしかった門徒総代さんの
お葬式の時のことです。
開式のアナウンスがあり、全員で合掌礼拝をして、キンを
打とうとした時のことです。
「ハッピーバースデーだね」と 幼いお嬢さんの元気な声が
会場に響きました。
葬儀のお勤めを始めましたが 子どもさんの言葉が、気になります。
確かに お葬式は、お浄土へ生まれた お祝いの会なんだと味わえます。
亡くなった総代さんは、自分が死んで居なっても
お浄土へ生まれて 仏さまになるのだよと、可愛いひ孫さんに
言い聞かせていたのだろうなあと、総代さんの写真を見ながら、
その思いに 気づき だんだんと有り難くなってきました。
お勤めが終わり、喪主の方が控え室へ挨拶にこられて
「先ほどは大変失礼しました。」と謝られます。
「何でしょう」と聞くと 「孫が 大きな声で
あんなことをいってしまって 大変申し訳ありません」と
恐縮しておられます。
「いやいや、きっとおじいちゃんが ひい孫さんへ お話をされて
いたんでしょうね。とても有り難い事ではないですか」と言うと、
「実は つい先日 あの子の2歳の誕生パーティーを
開いたばかりで、そのときにローソクを付けてお祝いしましたので、
今日 またローソクを見て 誕生会のことを 思い出し、
場所もわきまえず 大変申し訳なく思っています」と仰います。
お孫さんは そうだったのかもしれませんが、あれほど熱心に聴聞された
有り難い総代さんのことですから、死んだんじゃないよ、お浄土へ生まれて
仏さまといっしょに、お前達のことを 応援しているぞと、
お孫さんの口を通して 教えて頂いたんじゃあないでしょうか。
本当に有り難いことですねと。お話ししました。
お通夜は 娑婆のお別れの会 人間の卒業式とおしゃる方があります。
そして、お葬式は、お浄土の入学式 仏さまの就任式であると、
ですから、確かにお浄土へお生まれになって 仏さまになられたということは
喜びのお祝い ハッピーバースデー に違いありません。
仏さまは いろいろの人を通して そのはたらきを教えてくださっています。
ところが、それに、ほとんど気づかないでいるのが私たちです。
南無阿弥陀仏の声は そうした仏さまになられた方々の はたらきかけ
呼びかけの言葉なのでしょう。
耳を澄ませて 先輩方の呼びかけを 願いを、しっかりと聞かせていただき
生きがいある喜び多い毎日を 南無阿弥陀仏とともに過ごさせて
いただきたいものです。
第1661回 周りに迷惑をかけて
令和6年 11月28日~
仏教では「多くのお陰によって生かされている」と教えてくれています。
植物や動物の生命を奪うことでしか、人は生きることができません。
そのことへの「痛み」があってこそ「人間」であり、痛みを失ってしまえば
人間とはいえません。
(「無慚愧は名づけて人とせず」・慚愧は罪に対して痛みを感じ、
罪をおかしたことを羞恥する心。慚愧がなければ、人と呼ぶことは
できないという意味。涅槃経の言葉を 教行信証に引用)
慚愧がないことは、畜生という主体性を失った生き方(飼い主に
生殺与奪の権利を握られ)、欲に振り回されている存在(餓鬼)に
なってしまうと教えています。
それでは長生きをしても喜べず、むなしく過ぎる人生を送ることに
なるというのです。
私たちはすでに人間として生まれていると思っていますが、
仏教では、多くの「お陰さま」を、感じることができて初めて
人間と言えるというのです。
外見は人間でも、中身が餓鬼畜生のような在り方なら、間柄を
受け取れる智慧の目がないと、人は傲慢なる危険性があり、
相手に迷惑をかけ、苦しめる三悪道(地獄・餓鬼・畜生)の
世界を生きることになるのです。
「人間」、それは、間柄を生き、あらゆるものと関係をもって
存在しています。
単独の存在を主張する人は、あたかも真空パックの中に
いるようなものです。三分間も経てば酸欠で必ず死を迎えます。
人間のありさまの過去・現在を、あるがままに見ると、
父母をはじめ、あらゆる存在の犠牲の上に今、現に存在して
いるのです。
いくら「誰にも迷惑をかけてない」と、うそぶいてみても、
人は周りに迷惑をかけずには生きていけません。
私たちの分別は、科学的思考を信条としていますが、
戦後の貧しさを克服して、物質的に豊かな国になった成功体験から、
仏教などなくても生きていけると、傲慢になっているのでは
ないでしょうか。
いくら科学・医学が進歩しても、人間は「老病死」を免れる
ことは出来ません。
迷いの人生の苦しみを超える仏教の教え、私たちの分別の
次元を超えた(異質な)仏の世界に触れることによって、
私のあるがままの姿に気づき、目覚めさせられるのです。
仏の心に触れるとき、「人間として生まれてよかった。生きて
きてよかった」という人生を生きることに導かれるのです。
田畑正久著 「生きることを教える仏教」本願寺出版社
第1660回 親の足を洗う
令和6年11月21日~
こんな話を聞きました。
ある会社では、入社試験に毎年、「これから三日の間に、
お母さんの足を洗って、その感想文を提出してください」という
問題を出すそうです。
学生達は、簡単な問題でほっとして、会社を後にしますが、
なかなか母親に言い出すことが、できない人が多いようです。
ある学生は、二日間、言い出せず、やっと三日目、ようやく
母親を縁側に連れて行き、その足を洗おうとし
その足の裏が、あまりにも荒れ放題で、ひび割れて
掌で感じて、絶句してしまったといいます。
「この荒れた足は、自分達のために働き続けてくれた足だ」と、
胸が一杯になり「ありがとう」と、つぶやくと
それまで、ひやかしていた母親は、声を詰まらせ「ありがとう」と
言ったまま
「私はこんなに素晴らしい経験をしたのは初めてでしたと・・・・」
今まで 自分の頑張り、努力したことばかりを意識していましたが、
自分のために、はたらいてくれた親の苦労に はじめて気づきましたと。
親鸞聖人が 29歳のとき、比叡山を降りて法然聖人のもとを
訪ねられたときも それまで、自分の力で修行をすることばかりを
考えていたのに、自分の努力以上の、仏さまの大きなはたらきかけに、
気づかれたのでしょう。
自力から他力への転換です。
お釈迦さまの時代、仏足頂礼 仏前にひざまずき、
仏足を自分の頂にあてて礼拝することを最高の敬意を表すことと
されていたようですが、これも、ことによると、教えを説き、各地へ
休むことなく厳しい旅を続けられて 痛んだその足を拝むことで、
そのご苦労を改めて気づき、味わい、感謝することを意図したのかも
しれません。
私たちは、自分の行いや努力、自分のことしか気づきませんが、
お念仏にあうことで、南無阿弥陀仏を聞くことで、私のために、
いかに多くのはたらきかけが、ご苦労があるかに気づかされ、
感謝する力が育てられていくのです。
感じる力が育ってくると、なんとありがたい人生であったかと
味わうことが出来るのです。
気づくことができないと、自分ひとり苦労して、何もいいことは無かったと
辛い苦しい人生だったとしか、味わえないで一生を終わるのです。
気づくか 気づかないか、感じるか感じないか、それで、まるで
違った人生となってしまうのです。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏を聞く度に だまって私のために
はたらきかけてくださる 多くの有り難いはたらきかけが 力があることに
改めてはっきりと、気づかせていただきたいものです。
第1659回 願いを知る
令和6年 11月14日~
月忌参りをはじめ、本堂での法座では、いつも「正信偈」を
お勤めしています。
お仏事ですから、阿弥陀経などお経をお勤めするのが普通でしょうが、
親鸞聖人のまとめていただいた「正信偈」を、いつも拝読しているのには
大きな理由があります。
お釈迦様の教えは 八万四千の法門といわれるように数多くあると
言われます。
しかし、その多くは 出家して、厳しい修行をし、さとりを
開こうとする、お弟子さん達のために説かれたものと言われます。
ところが、私たちは 出家していません、修行をするような
気持ちもありませんし、また、その能力もありません。
そうした私たちをも、何としてでも救いたいと、阿弥陀さまは、
はたらき続けておられると、お釈迦さまは、教えていただいているのです。
わがままで、自分が生きるためと、生き物のいのちを奪い、
罪の意識もなく平然と生きています。
しかし、その報いで、私は必ず地獄にいく生き方をしているのです。
それなのに、阿弥陀さまは自分の国、お浄土へ生まれさせて、
救いたい、何としても仏にしたいと、南無阿弥陀仏のお念仏となって
はたらき続けておられるというのです。
親鸞聖人自身は 出家して修行をして さとりを得ようと
努力された方でした。
しかし、すでに末法の世、自分で努力しても、人間の力では
決してさとりを得ることの出来ない時代であることを知り、
お念仏の教えでしか、救われないことを、法然聖人に
出会うことで、はっきりと理解されたのです。
これはインド、中国、日本の優れた先輩たちが
自分自身で味わい喜び、伝え残していただいた、有り難い教えであると、
教行信証にまとめていただいてるのです。
ですから、正信偈のおつとめをするのは、数多くの教えがあるものの
今の時代、この私が救われる教えは、このお念仏の教えしか無い。
他の教えでは、助かることは出来ないと教えていただいているのです。
そして、ご和讚で詠んでいただいたように
安楽浄土にいたるひと 五濁悪世にかえりては
釈迦牟尼仏のごとくにて 利益衆生はきわもなし
お浄土へ生まれて仏と成って、はたらいておられる
両親や 祖父母・多くの先輩の方々は、お釈迦様のように
私のために この教えでしか救わる道はないと勧めて
いただいているのです。
いつも正信偈を拝読しているのは 先だった両親の
遺言を読み直すようなもの、親の願いを聞くことなのです。
なかなか親の願いに気づくことができませんが、
その思いに、願いに出会うことが出来ているのです。
遺言書を 読むように、親の願いを味わわせていただき、
お勧めいただいているとおり、お念仏して、同じお浄土へ
生まれるものとしての生き方をさせていただきたいものです。
第1658回 私は 私でよかった
令和6年 11月7日~
こんな話を読みました。お医者さんでお念仏の人、
田畑正久先生の本で「生きる ことを 教える仏教」
その中の「私は 私でよかった」という内容です。
日常生活で、われわれは 事に当たって 何か判断する時、
私にとって 善か 悪か、損か 得か、勝ちか 負けかを 考えます。
われわれが善いもの、得になるもの、勝ちになるものを
集めようとするのは、そうすることで 自分の人生を
充実したものにしたい
という心が 働いている
からだと思われます。
世間的には 自分を 充実させるもの として、良好な人間関係、
経済的安定、社会的評価や 健康等を 考えます。
しかし、それらは 相対的なものですから、どこまで
手にすれば 満足することに なるか わかりません。
人間を 一番 困らせるのが「 死 」です。
哲学者のフィヒテは「 死というものは、どこかに
ある
のではなくて、真に 生きることの できない人に
対して のみある 」と言われています。
フィヒテの言う「 真に 生きる 」とは、「 足るを知って 生きる 」
「 私は 私で よかった 」「 完全燃焼 できた 」
「
生きてきて よかった 」と いうような 生き方だと 思われます。
江戸時代の思想家で、医師でもあった 三浦梅園の書に、
「 人生 恨むなかれ 人知るなきを 幽谷深山 華 自ずから 紅なり 」
( 他人が 自分のことを 評価してくれなくても 嘆くことはない。
深山幽谷に咲く花は、誰かに 見られなくても 精一杯
見事な花を 咲かせている )
最後の「 華 自ずから 紅なり 」は、私は 私でよかったという
「 真に 生きる 」ことを 表現した言葉と
思われます。
「
真に 生きる 」ことのできない状態を、仏教では 餓鬼、
畜生と
表現することがあります。
餓鬼とは、いつも
何かを 取り込まないと 満足できず、
常に 取り込もう、取り込もう としている 状態を 示します。
畜生は 家で飼っている ペットのようなもので、
飼い主の顔色を うかがいながら 生きて、主体性が 無い状態です。
自らに 由ってない、自由でない 生き方です。
「
真に 生きる 」とは 足を 知って、主体的に 自由自在に
生きることを示しています。
自分に 与えられた 場を、「 これが 私の現実 」と
受け取れる人は、その場で
精いっぱい 生き切ることが
出来るでしょう。
あとは 安心して「 仏へ お任せ 」になるのです。
田畑正久著 「
生きる ことを 教える仏教 」本願寺出版社刊
第1657回 私が 仏になる
令和6年10月31日~
やがて、「仏に成る」ことが、なかなか理解出来
ないという方があります。
阿弥陀如来という仏さまは 一人も漏らさず必ず仏にしたいと、
宇宙的長い間自分で修行をし、南無阿弥陀仏を口にするものを、
お浄土へ必ず生まれさせ、仏にし 続けておられると、
お釈迦さまは説かれています。
それで、親鸞聖人は 念仏をしようと思うこころがおこった時
摂取不捨の利益、間違いなく仏の仲間であると、言われた
と歎異抄にあります。
仏教は 因果の道理 自業自得が説かれており、
自分でつくった原因は 必ず自分に帰ってくると。
そこで、生き物を殺さないこと、(不殺生)、盗みをしない(不偸盗)、
よこしまな姓の交わりをしない(不邪淫)うそをいわない(不妄語)、
酒を飲まない(不飲酒)など、慎むべきことが説かれています。
生き物を殺すと、その報いを受けることになると。
しかし、皆やっていることで、生きていくためには必要なことだと
何の心配もしていませんが、その報いを受けることは間違ないのです。
そこで、地獄にしかいけない自分であると、気づき、
仏さまの助けが必要であり、 阿弥陀さまは この私のために
お念仏を与えていただいたと、理解し、味わえるように
なったものを、真実に気づいた人、目覚めた人を、本当の人間、人間になったと
いうのでしょう。
私たちは人間に生まれ、すでに完全な人間になっていると
思っていますが、実は、そうではなく、いつも満足出来ずに、
欲望を追い求めて飢餓の状態、餓鬼の毎日であり、
動物のように養われ、本能のままに生きている畜生の生活、そして
絶えず対立し闘争する 修羅の人生、まさしく六道の餓鬼、
畜生、修羅、地獄のような苦しみの生活をおくっているようです。
自分の行いの報いで、自分の行き先は 間違いなく地獄であると
理解できたとき、阿弥陀如来のはたらきでしか、救われることは
ないのだと味わえて、南無阿弥陀仏と、お念仏を口にしようとするとき、
はじめて人間になったということなのでしょう。
親鸞聖人は、「いずれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は
一定すみかぞかし。」とおしゃっていたと。
この私は、地獄にしか行くところがない 南無阿弥陀仏の
はたらきでしか、救われることはないのです。
本当の人間になり、お念仏を口にすることができれば、やがて間違いなく
お浄土へ生まれることが出来る、お念仏の人は もう仏の仲間であると。
私たちは、私、私と 自己主張をしていますが、
私の字から 人を引くと 仏になると 漢字ではみえます。
のぎへんから -(マイナス) 人 は、にんべんとなります。
私は 仏になれるのです。
本当の人間に成り、やがてお浄土で仏になる、それは
私の力ではなく、仏さま 阿弥陀さまのはたらきのお陰なのです。
そして今、感謝報恩のお念仏が出来る 仏の仲間の生活を
送っているのです。
今の状態から、もっとよくなる浄土へ生まれるのではなく、
地獄へ行くべき所を 救われてお浄土へ生まれ仏になれるのです。
第1656回 救われる私
令和6年10月24日~
こんな話を聞きました。
祖父の33回忌法要のために、四国に帰り、祖父が
長年書き綴ったものを、見るご縁がありました。
戦前のこと、成績が良かった長男に期待して 地元の学校ではなく、
海を渡った広島の学校に入学させ、その成長を楽しみにしていました。
ところが、昭和20年、原爆が投下され、広島の親戚が、探し回り
被爆して横たわっている長男を発見し、連れ帰ってくれましたが、
30分もしないうちに「おやすみ」と、一言残して息絶えてしまった
ということです。
電話も手紙も通じず、やっと、6日の後、遺骨になった我が子と
対面することになりました。
見取ってくれた親戚に、自分たち父や母のことを、何か口にしなかったかと、
何度も確かめましたが、「おやすみ」の言葉だけで、他には何も
言わなかったと聞かされ、子どものためと思って、遠い広島の学校に
一人で出してしまって淋しかったのではないか、恨んでいたのではないかと、
悔やまれ、それからは悲しく苦しい毎日だったとあります。
この子がどんなところにいようとも、なんとしても
助けなければいけない、救ってやらねばならないと、それからは
お聴聞を繰り返す生活をしていましたが、あるとき、ふと気づかせて
いただいたと。
自分が救おう、自分が仏となって救おう、救ってやろうと思っていたが、
あの子のご縁で、こうしてお聴聞させていただいているのである、
救われなければならないのは、若くして亡くなった子どもではなく、
この子をご縁として、私こそが救われているのではなか。
救う側ではなく、自分は救われる側であったと、
味わえるようになったと書かれていました。
本願寺第十四代ご門主 寂如上人は
引く足も 称える口も 拝む手も
弥陀願力の 不思議なりけり
こうして、お仏壇の前に座り、本堂にお参りし、おつとめをして
お聴聞し、お念仏を口にし、手をあわすという尊いご縁は、
私の力ではなかった、阿弥陀さまのはたらきのお陰であったと。
そして、そのご縁を結んでいただいたのが、若くして亡くなった
あの子であったと味わえるようになったと。
第1655回 後になって 気づく
令和6年10月17日~
あるお寺の掲示板に 「後になって気づく ことばかり」と
ありました。
あの時、ああすれば良かった、こうすればよかったと、後になって
悔やむことがあります。
歳を重ねてくると、若いころ気づかなかったことに、あれは
ああ、そうゆうことだったのかと、有り難く感ずることも
多くなるものです。
前もって 気づくことが出来ればいいのですが、後になって、
反省したり、悔やんだり、感激したりしています。
ネットに 前もって気づくには、どのようにすればいいですかと、
尋ねると、「経験者や先輩に聞くこと」との返事が返ってきました。
そういえば、親鸞聖人は 教行信証の最後に中国の道綽禅師の
『安楽集』の言葉「前に生まれん者は後を導き、後に生まれん者は前を訪え。」
と書かれています。
「前に生まれた者は後に生きる人を導き、後の世に生きる人は
先人の生きた道を問いたずねよ」という呼びかけです。
訪え、尋ねることを、とぶらえ(訪え) 訪問する家庭訪問の訪の字が
使われています。
訪ねていって聞くということでしょう。
仏教は、お釈迦さまが説かれた教え、人生を深く見つめて悟られた内容を
多種多様に説いていただいています。
その神髄を、800年前の親鸞聖人は インド中国そして日本の優れた
先輩が理解し味わわれ、解釈していただいた内容を、教行信証に
まとめて表し、私たちに残していただきました。
そこで、仏法を聞く、お聴聞するということは、訪ねて
先人に、経験者に訪ね、聞くことなのです。
このお念仏の教えに遇うことが出来れば、後になって気づく
のではなく、今、前もって気づかせていただくことが出来るのです。
失敗し後悔するのではなく、気づいていなかった親切や思いやり、
温かい はたらきかけにも 気づかせていただくのです。
良いことも悪いことも、後で気づくのではなく、今 前もって
気づかせていただける、それが、お念仏に生きる人の特徴だと
いえましょう。
そして訪ねれば、訪ねるほど、有り難くなり、喜びがましてくるのです。
後悔や 反省することよりも、感謝の思いが深く味わえてくるのです。
何事も当たり前になって、気づいていなかった
仏さまのはたらきを、はっきりと感じ、味わえ、喜ばせて
いただけるのです。
それが、お念仏の生活、南無阿弥陀仏に遇えた人生です。
第1654回 ハチドリのひとしずく
令和6年 10月10日~
こんな話を聞きました。
「ハチドリのひとしずく」という 物語です。
森が燃えていました
森の生き物たちは、われ先にと逃げていきました
でもクリキンディという名のハチドリだけは
行ったり来たり
くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは
火の上に落としていきます
動物たちがそれを見て
「そんなことをして いったい何になるんだ」
と言って笑います
クリキンディは、こう答えました
「私は、私にできることをしているだけ」
南米のアンデス地方に伝わるお話だといいますが、
この物語を翻訳し出版されると、大きな反響があるようです。
多くの小学校では、この森の火事はこの後、どうなったのでしょうかと
子どもたちに問いかけると ほとんどの学校では
「ハチドリの姿を見て、森の動物たちも、火を消すことをはじめ、
森の火は、やがて消えました。」との回答がほとんどだといいます。
純粋な子どもたちは、先生の問いかけに、授業の時間ですから、
正しい答えは何かと考えて、そのように回答するようですが、
世間の現実を知っている、大人の世界では、はたしてどうゆう
答えが返ってくるのでしょうか。
大きな出来事だけではなく、身近な問題、小さな出来事でも
自分の出来ることを、無理だと思っても、無駄だと思えても
ほんの小さなことでも行動し、活動し続けていきたいものです。
そして、浄土真宗の門徒の私たちは、まず出来ることは、何か、
それは、声にだして、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と口にする
ことなのかもしれません。
その声が、少しでも聞こえてくると、やがて、仏さまの仲間が
増えていき、仏さまの願いが、はたらきが味わえる人の輪が、広がって
世界は少しづつ、変わっていくのだろうと味わいます。
ほんの小さな声の南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏でも、
仏さまのはたらきかけ、
くることでしょう。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1653回 墓 友 ~この世からの仲間~
令和6年 10月3日~
お墓を維持していくことが出来なくなったと、墓所を
整理する人が増えています。
少子化で、後を見る人がいなくなったとか、地方の
出身者が都会へ出て、もう故郷には帰って来ないなど、お墓が
あることが負担となっている人が増えてきたようです。
先祖から受け継いできたもの、粗末には出来ないものの、
なかなかうまく維持できず、どうすればよいのか、関係者に
とっては、お墓の存在は 切実な問題のようです。
また、お墓を持たない人は、お骨を海にまく散骨や、
樹木の元に納める樹木葬などが注目されてはいますが、
なかなか、そこまでは踏み切れず、それといって、新しく墓を
ひとりで建てるのは無理だと、仲間でお墓を
お墓に一緒に入る仲間を募って、お墓を
あるようです。
死んでからだけではなく、同じことなら、生きている間に
親しい仲間になろうではないかという、墓友の会というのがあると
テレビで放送していました。
親子や兄弟などの血縁関係ではなく、友達で一つの墓を建てようと
いうお墓の友だち、お墓の仲間・グループです。
お稽古事や、趣味の仲間、友だちは、元気で、生きている間だけのこと、
墓友は、生きている間だけではなく、いのち終わっても
ずっと一緒の仲間であると、まったくの赤の他人が、あの世までも
一緒しようという話です。
このテレビの内容を聞きながら、浄土真宗のご門徒は、みんな
墓友ではないかと思えてきました。
同じお墓ではないものの、同じお寺の境内の墓地に入り
そこに留まるのではなく、みんなお浄土で仏さまになる。
そして、仏さまとして、人々を救うはたらきをするのです。
テレビでは、墓友という新しい仲間づくりをする、斬新な発想と、
紹介していましたが、
存在していました。
この世だけではなく、お浄土でも共にはたらく仲間、それが、
浄土真宗の門徒ではなかったかと、味わっています。
そして、浄土真宗の仲間は、いのち終わっても
一緒に、よろこびをもって はたらく仲間です。
しかも、時代を超えて 両親や祖父も、ずっと前の多くの祖先とも
再開し、共に同じ 喜びと生きがいをもって、活躍できるのです。
そして今、やがて仏となる仲間と一緒に、生きているのです。
みんな一緒にお聴聞をし、御斎を共にし、共におつとめをし、
共に歌い、共に笑って、共に泣き生きているのです。
限られたこの世の短い間だけではなく、末通って、共に生きる仲間、
それが浄土真宗の門徒なのです。
第1652回 法座 & フォークソング
令和6年 9月26日~
ご法座の多くは 午後の1時半から始めていますが、
お彼岸法要と門信徒総会・降誕会の時だけは
午前中にスタートしています。
親鸞聖人の降誕会では 斎のあと それぞれが日頃鍛錬した
かくし芸や、カラオケを披露しあって楽しんでいますが、
彼岸会ではここ数回、福岡県甘木市から 石井太郎さんの
ギターとボーカル、
三原奈津子さんのピアノの、お二人を招いて
昭和時代の懐かしいフォークソングを聞かせていただいています。
午前中の法座だけで帰られた方もありましたが、
40人ほどの方が残っていただき
ドップリとしたって
その歌詞の多くは、周りの親切や思いやり、純粋な愛に
気づかずに、悩んでいた青春時代、歳を重ねて、少しずつ気づかせて
いただけるようになると、みなさんに支えられた有り難い時代を
生きてきたことを
本堂の椅子に、体を揺らすこともなく座って、静かに聞く姿を
見ていましたが、中には、眼を閉じて、歌詞に合わせて、
唇を動かす方が
なつかしい、なじみの曲を、一緒に口ずさんでおられるようです。
その姿を、じっと見つめながら、お念仏を喜ばれた有り難い
先輩の方々を思い出しました。
ご法話を聞きながら、いつもお念仏を口にされたいた懐かしい方々です。
未来への不安や思い通りにならない悲しく苦しかったのが青春時代、
それに対して、お念仏の人は 明るい未来と安心を
お念仏を口にしながら確認し味わっておられたことでしょう。
あるご婦人が、こころが洗われるような、心地よさを味わわせて
いただきましたと、お礼を言っておられましたが、
南無阿弥陀仏のお念仏もまた、心からの安心と喜びを味あわさせて
いただくものだと感じています。
こころにしみる音楽と、こころに新たな喜びを与えてくれる
ご法話、南無阿弥陀仏のお念仏、私に元気を与え、生きていく力を
与えてくれるところに、共通点があるように感じています。
第1651回 はじめての道 はじめての人生
令和6年9月19日~
山登りが大好きなご住職に、こんな話を聞きました。
学生時代は 高い山に登っていましたが、近頃は、そうもいかず
時間をつくっては、近くの山によく登っているとのことです。
慣れ親しんだ山であっても、別れ道では、右だったか、左だったか、
よく悩むものだそうです。
でも、そんなところには、テープでの目印や、岩にペンキで矢印が
書かれてあったり、迷うことがないようにと山の仲間が、ちゃんと
心配りをしてくれているのだそうです。
一歩一歩、登っていくのは大変ですが、新鮮な空気、眼に鮮やかな
赤や、緑、眼下に広がる豊かな自然に、なんとも言えない喜びがわいてきて、
どうしても、登山はやめられないものだそうです。
そして、山登りは 人生と同じように、荷物が軽いと軽快ですが、
どうしても捨てきらず、ついつい沢山の荷物をしょいこんでしまうと、
その道のりは、とてもきつく苦しいものになるといいます。
登頂まで何日もかかる高い山ですと、専門の案内人を付けないと
とても無理ですが、日帰りできる山でも、道案内や標識がなければ
迷ってしまうとても危険なものです。
ところで、この人生も、私にとっては、はじめての経験です。
どこへ向かっていけばいいのか、どこが目的で、どう行けばいいのか、
まったくわかってはいません。
その道を知った人に、経験した人に尋ねることができれば、少しは
安心ですが、尋ねることもなく、自分勝手に、どんどんと歩んで、
苦しんでいる人が多いものです。
人間について、深く深く考え抜いたお釈迦さまが説いていただいた、
そして、それを私たちにわかり安く、紹介し解説してくださった
親鸞聖人が示してくださった確かな道が、行き先があるのだと
先輩が先祖や親たちが、私たちに伝え残してくださって
いるのです。
ところが、それを知らず、気づかず、振り向かないで、一人悩み
苦しんでいるのではないでしょうか。
南無阿弥陀仏の教えに遇えれば、自分でやれること、仏さまに
任せておけば、大丈夫なこと、この限られた人生だけではなく、
いのち終わっても大丈夫な世界、有り難い価値観があるのだと
聞かせていただけるのです。
初めての人生、初めての道 知らない危険な山に登るのと同じことです。
重い荷物を背負い込んで、自分ひとりで悩み苦しむのではなく、先人たちの
経験を、教えを素直に聞く耳を持ち、豊かな有り難い人生を
喜びながら、一歩一歩、歩みたいものです。
第1650回 自分の姿を鏡で見る
令和6年9月12日~
近くの県にある親のお骨を近くに移したいが、どうしたら
良いのでしょうかと、美容師の方が、相談に来られました。
そこで、美容院と お寺 多くの共通点があるように思います。
定期的によく美容院に通われる方と、まったく無関心な方があるように、
お寺も定期的に、よくお参りいただく方と、まったく
ご縁のない方があるものです。
美容院にいくと、頭が軽くなり、こころも明るくなってくるものですが、
お寺も、お参りして仏さまのお話を聞くと、すっきりとして、
心も明るくなるものです。
お墓に花をあげただけで、帰る方がありますが、それでも、
少しは気持ちが
しかし、これはちょうど、美容室の花瓶に花をさし、
待合室で雑誌を見ただけで帰るようなもので、カットや髪を洗って
セットして
それと同じように、お寺も、ただ墓にお参りするだけではなく、
お話を聞いて、新たな価値観を、新しい視点を受け取ることがなければ、
余り有り難いものでは、ありません。
美容院の鏡で、素敵になった自分の姿を見たときのように、
仏さまの話を聞くことで、心の中が、新鮮な喜びを、感じられてきて、
すっきりとして、うれしくなってくるものです。
浄土真宗では、特に恩ということをいいます。
親鸞聖人の御命日を報恩講といい、よく歌ううたも、恩徳讃、恩という
言葉がよく聞かれます。
これまでいかに多くの方々の力、支えがあったかを気づかされて、
心の中が喜びでいっぱいになり、生きていく力がわいてくるものです。
美容院を出るときのように、世界が変わって見え、未来が明るくなるものです。
とはいえ、しばらく時間がたつと、その喜びは薄れてくるものです。
髪も伸びて、気持ちが悪くなるように、心もだんだんと重たくなって
どんよりとしてくるものです。
そこで、美容院に行って、綺麗にしていただくように、浄土真宗の方は
仏さまのお話を聞くことで、心の喜びがよみがえっていくものです。
ですから、ただお骨を預けるだけではなく、それをご縁に
お話を聞くことができる所に、ご相談されることをおすすめします。
第1649回 あんたが悪い
令和6年 9月5日~
こんな話を聞きました。
「あんたが悪いと指さした
下の三本は自分を向いている」
仏教のことばが書かれた掲示板がお寺にはあります。
これは、山の断崖の大きな岩のくぼみに建てられた奥院
国宝の「投入堂」で有名な鳥取県三朝町(みささちょう)にある
天台宗の三佛寺(さんぶつじ)境内にある自動販売機に
掲げられていたことばだそうです。
自販機に掲示板というのは、なかなか斬新な有り難い発想です。
お前が悪いと 一方的に批判しているのが私たちです。
相手を指さし非難していますが、その手をよくみると、
人差し指は相手をさしていても、折り曲げられた中指、薬指、
小指の3本は、自分の方を向いているものです。
人を指している指は自分の目からよく見えますが、自分を指している
3本の指は意識しないので視界にはあまり入って来ません。
相手の悪いところが 見えたとき、気づいたことは、私の方には、
その三倍の問題があるのだと、教えてくれているようです。
相手の悪い部分と同じようなことを 自分もしていることに
気づいていないのが、私たちです。
もし、相手に怒りや憤りを思えたときには 一息入れて
自分の方には、気づいていない三倍の 悪い点を 回りに見せていると
理解した方がよいようです。
中国の善導大師は
経教(きょうきょう)はこれを喩(たと)ふるに鏡のごとし。
しばしば読みしばしば尋ぬれば、智慧を開発す。
『観経疏』序分義
仏法は 鏡に映すようなものだと言われていますが、
誰かの悪が見えたとき 自分自身の姿を 鏡に映すように
点検してみることが、重要なようです。
「あんたが悪いと指さした
下の三本は自分を向いている」
第1648回 まだ仕事は残っています
令和6年 8月29日~
「老いて聞く 安らぎへの法話」という 本の中に
最後の仕事という項目が ありますが、
その一つで、「まだ仕事が残っています」というお話です。
本願寺派に雑賀正晃というとても立派な布教使さんが
おられました。
そのご法話で こういうお話を聞いたことがあります。
雑賀先生のお寺の檀家総代 Yさんが老齢で入院され、
もう末期になられた。
雑賀先生がお見舞いに行かれると、目に涙をためて、
「先生、もう私は何もできません。この家内と看護師さんの
お世話になるばかりで・・・・」と細い声で言います。
「いや、Yさん、あなたには まだ大事な仕事が残っています。」
「仕事って、どんなことですか」
「『ありがとう』って言うことですよ。奥さんにも、先生にも、
看護師さんにも、お見舞いの人にも『ありがとう』とお礼を言うのが
あなたの仕事です。もし声が出なかったら、手で、眼で
言ってください」
「あぁ、そうでした、そうでした。本当ですね。『ありがとう』
ございました」
「それにね、Yさん。どのようになっても、お救いくださる
阿弥陀さまにお礼申しあげることが第一ですよ」
「あぁ、そうでした、そうでした。なもあみだぶつ、
なもあみだぶつ、・・・・」
藤枝宏壽著 老いて聞くやすらぎへの法話より 自照社出版
まだ、まだ先は長いと思っていますが、明日がしれないこのいのち
大切な人に、そして阿弥陀さまに ありがとうございますと
お礼をする一日でありたいものです。
第1647回 さいごの仕事
令和6年8月22日~
あるご門徒さんが言われました。
「わたし、歳がいったらもう何もできません。
あかんもん(だめなもの)になってしまいました」と
そこで私は「いや、いや。まだ大事な仕事が残っていますよ」
と、言って次のようなお話をしました」
大阪府吹田市の光徳寺さんの掲示板にこういう詩がはってありました。
病気になって 気付く 空の青さ 空の高さ 空の広さ
直海玄洋師
ある日、中年の女性が、この人は薬剤師さんでしたが、
この詩を見て感動します。
実はガンの宣告を受けて、悩んでいたのです。
さっそく住職の直海先生にお会いしてお尋ねします。
「私は、余命いくばくもないと宣告されてから、身の回りの
整理をしましたが、どうしても心の整理がつきません。
人間、何のために生まれてきたのでしょうか」
すると直海先生が、
「仏法を聞いて、仏の世界に生まれ、仏のさとりを
得るために生まれてきのです」
と答えられます。
女性は目の前が明るくなるのを感じました。
それから、彼女は何回も仏法を聞かれましたが、
ついにこの世のご縁が尽きて亡くなられました。
すると、ベッドの下から遺書が見つかりました。
私は間に合ってよかった。
みんな、手遅れにならない中に、仏法に遇うておくれ。
彼女は、自分自身のいのちの行き先をハッキリするという
大仕事をやり遂げ、さらに遺された若い人たちをも、
その人生の行き先に導くという さいごの仕事をされたのでした。
藤枝宏壽著 老いて聞くやすらぎへの法話より 自照社出版
第1646回 お母さんの 一言
令和6年8月15日~
阿弥陀さまのお話をユーチューブで繰り返し聞きながら、
何故か、子どもの頃に見たモノクロの映画のことを断片的に思い出しました。
当時、「母もの映画」といっていたようですが、三益愛子という
俳優さんがいつも母親役で、食料事情も良くない戦後まもなく、
その日 その日、食べることにさえ苦労していた、大変な時代のこと、
苦労して苦労して一人息子を育てていた母親。
しかし、子どもの方は、その親の心が分からず、反抗し悪い仲間と
つるんで問題ばかり起こして、心配をかけつづけていますが、ついに
警察につかまってしまいます。
それでも見捨てることのできない母親、連行されていく子どもが、
そこに母の姿を見て、はじめて「おかあさん」と、呼んだ時、観客は、
みんな一斉に涙を流していたのを思い出しています。
「お母さん」との息子の言葉、涙する母親、一緒に泣いている
満員の観客。
どの母もの映画を見ても みんな同じような物語だったように思います。
今思えば、脚本家か監督か制作者なのか、浄土真宗のご法話を聞き
阿弥陀さまのはたらきに、反抗する人が、その有り難さに気づいて
南無阿弥陀仏と口にお念仏するそのことを、母と子の関係で
表現したのではないかと、味わっています。
反抗し 反抗し 困らせ続けた息子が 最後に一言 お母さんと
声に出す、それは、母親の苦労、心配に気づいて 有り難く
感じてた瞬間だったのでしょう。
出来損ないの息子が、親のきもちに触れて、お母さん と
呼んだときと同じように 南無阿弥陀仏と 声を出したとき、
こころから喜んでくださる方あることを、改めて味わっています。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は 私を思い よびかけ続ける
大きなはたらきがあることを、そして、その有り難さを
感じたときに、口から漏れ出る 大きな願いのことばなのでしょう。
仏さまが、親たちが 最も喜んでいただくことば、安心することばです。
第1645回 未来は 前か 後ろか
令和6年8月8日~
こんな話を聞きました。
私たちは、未来へ、あしたへ向かって精一杯生きていますが、
未来は 明日は、どちらの方向にあるのでしょうかとの質問です。
多くの人が、前に進む 前向きに生きると 未来は自分の前にあると
イメージしています。
「眼の前に広がる」のが未来であり、「後ろは振り返らない」などと、
うしろにあるのは、過去のことです。
未来は 自分の前にあり、過去は、自分の後ろにあるものと思っています。
しかし、「この後のご予定は」等と言うとき、私たちは
未来を前ではなく「あと(後ろ)」に置いています。
三日後にまたお会いしましょうとか、五年後にはこうなるとか、
未来は 前ではなく、 後ろにあるように話しています。
そして、三日前に、一年前は などと、過去のことは 前と表現しています。
日頃使う言葉では、過去のことは 前方にあり、未来のことは 後ろ、
後方で表しているのです。
ですから、「以前」は、前は過去で 「以後」、後ろは、未来のことです。
私たちの気持ちの上では
前が未来で 後が過去なのですが なぜか 言葉では
逆の 未来を後ろ 過去を前の 表現をしています。
ヨーロッパの国では、過去は前にあり、全部見えるが、
未来は 自分の後ろにあり、何も見えないという表現をするところが
あるようです。
蓮如上人のお手紙である 御文章にある 後生の一大事 も
後生とは、これから先、未来のことを意味します。
見えているようで、見えないのが未来です。
浄土真宗では、お釈迦さまが説いていただいたように
精一杯生きている人は、必ずお浄土へ生まれさせ
自分と同じはたらきをさせる仏にすると、阿弥陀さまは、はたらきかけて
いただいている、後は任せればいいのだと、受け取っています。
これから、老病死 沢山の苦難が訪れるものの、心配はいらない
かならず、お浄土へ、そこには両親をはじめご縁のあった
多くの方々が、待っていていただく世界へ 生まれていくのですと、
呼びかけてくださっているのです。
その呼び声が 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏なのです。
見ることの出来ない未来 阿弥陀さまにおまかせして
今できることを 精一杯 生きていきたいものです。
お盆が近づきましたが、地獄へ落ちた人は、地獄の釜の蓋が開く
13日に、お帰り頂くのでしょうが、お浄土の人は いつでも
私のために、遠くではなく、今、ここではたらいていただいているんです。
第1644回 気づかない 私が
令和6年8月1日~
大阪のおばちゃんが、左足のしびれが出始めて、病院にいきました。
診察したお医者さんは、「うーん、これは残念ながら、高齢のためですね」と
告げました。
「でも、先生、この右足も同級生ですぜ」と、返事しました。
先生も負けず、「心配せんでええ、まもなく右足もしびれてきます」と。
同級生という表現でいえば、右足だけではなく、私の手も頭も口も
心臓もみんな同級生なのです。
ところが、頼みもしないのに、みんなだまって働き続けてくれています。
夜になれば、私自身は、眠って休んでいますが、
一日も、一刻もやすむことなく、働いてくれた同級生も沢山います。
心臓はその一つです。
頼みもしないのに、やすむことなく働づめで私を生かしてくれています。
私が気づかないところで多くの臓器が、精一杯、黙々と働いて
くれていたのです。
そればかりではないといいます。
頼みもしないのに、阿弥陀さまは、この私のためにずっと
はたらきかけ続けていただいているというのです。
気づかないだけ、知らなかっただけで、私のために多くの同級生と
一緒になって、私を生かし続けていただいているのです。
そう気づくとき、感謝しても感謝しきれないことが、いかに多いかが
知らされてきます。
当たり前になって気づかないことが、なんと多いことか、南無阿弥陀仏は
その多くのはたらきかけに、気づき、心から、感謝することばであり、
仏さまが、そして私の体のすべてがもっとも喜んでくれる言葉なのです。
何事も当たり前では、何の感動もなく不平不満のつらく苦しい毎日になりますが、
多くのはたらきかけに気づき、味わうことができれば、なんと
ありがたく喜びいっぱいの、豊かな人生を味わうことができるものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は、その喜びを、感謝を表す言葉、
「ありがとうございます」という言葉にもよく似た、親たちが受け継いで
残してくれた 有り難いことばです。
私に、多くの はたらきかけがあることに気づかせてくださる
仏さまの言葉です。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1643回 感じ取る力
令和6年 7月25日 ~
「学仏大悲心」という大きな額が、講堂の正面に掲げられている
学校があります。
善導大師が説かれた、仏の大悲心を学ぶという言葉です。
学ぶということは
勉強する。学問をする。
教えを受けたり見習ったりして、知識や技芸を身につける。
習得する。経験することによって知るという意味がありますが、
そればかりではなく、 まねをするという意味もあります。
何をまねるのか、それは苦悩するものを必ず摂取して捨てないと
はたらき続ける仏さま、阿弥陀さまの大悲心を学び、それを、ほんの
少しでもまねることだと言われます。
お念仏の教えは、仏さまの話を聞くこと、お聴聞することが大事と
いわれますが、これは、仏の大悲心、仏さまのはたらきを聞く
ということです。
それは、頭で理解したり、何かを覚えたりすることではなく、
全身で、仏さまのはたらき、仏さまのお慈悲のぬくもりを
感じとることを意味します。
必ず救う、ひとり残さず救うという、摂取不捨の光明に
照らされていることを、この身に感じることが出来るように
育てられていくことなのです。
そうした、大きなはたらきかけがあることを、感じることが出来る
ようになると、自分ひとりで生きているのではなく、
実は、生かされているのだという、大きな喜びと安らぎを感じることが
出来るようになっていくものです。
いくら仏教を深く学んでも、お慈悲のぬくもりを感じることが出来
なかったら、なかなか喜びは味わうことが出来ません。
仏さまのはたらきを、感じることが出来ると、そのはたらきの
まねをさせていただくこと、ところが、自分中心の私には、とても
とても、仏さまのようには、できないということに、気づかされて
いくと、人生は大きく変わってくるものです
仏さまのはたらきは、目にはなかなか見ることはできませんが、
仏さまのお話を繰り返し、繰り返し聞くことによって、仏さまのはたらきを
ほんの少しずつでも感じることができるようになっていくものです。
仏さまのはたらき、真実が、ただ一つのことば、南無阿弥陀仏となって
私に絶えず、喚びかけてくださっていることを、感じ取れていくのです。
第1642回 誰の安心のためか
令和6年 7月18日~
ある布教使さんから、こんな話を聞きました。
近くのお寺に招かれて、ご法話にいったとき、
控え室でお茶をいただいていると、帽子をかぶった紳士の方が、
お参りになる姿が見えました。
その姿をじっと見ていると、坊守さんが、あ、あの方の奥様はとても
有り難い方で、今日もお参りになりましたねと、おっしゃいました。
本堂でご法話中、その紳士がうなずきながら熱心にお聴聞されており、
隣の奥様も、にこやかな笑顔でお聴聞いただいていました。
うらやましいご夫婦と拝見していましたが、一席を終わり休憩のあと、
本堂にいくと、その紳士の隣には、別の女性が座っておられます。
どうゆうことだろうと、気になっていましたが、その女性は、
どちらかと言えば、暗い顔をして、あまり反応がないを方でした。
控え室に帰って、ご住職に聞きました。
あの紳士の奥様は、最初に横に座っておられたかたですよね、
後半、横に座った方はどなたですかと聞きますと、住職さんは
どなたのことですかね。聞き返されます。
帽子をかぶった立派な紳士の奥様のことですよと、言いますと、
いえあの方の奥さんは、もう何年になりますかね、ご往生されましたよ。
大変有り難い方で、婦人会の役員もしておられましたが、
ガンにかかられて亡くなられました。
奥様が元気なころは、ご主人は、まったくお参りになりませんでしたが、
病気になった奥様が、私がいなくなったら
必ずお寺でお話を聞いてとご主人に頼まれたそうです。
あまりにも熱心なので、わかったわかった、私がお寺に行けば、
あなたは安心出来るのでしょうから、必ず参りますよと、返事を
されたそうです。
そうすると、奥様は、私が安心するのではなく、残された貴方が
安心できるから、どうか、お参りしてくださいと、真剣に頼まれたそうです。
その奥様のことば通りに、あの方はお寺でお話を聞かれるように
なったのです。
亡くなっていく人を安心させるのではなく、生き残った自分のことを
心配してくれた奥さんのご縁で、お聴聞されるようになりました。と
お念仏の教えは、先立つ親や、連れ合いを安心させる教えではなく、
自分自身が安心を得られるもの、この人生を堂々と生き抜く力を
与えられていくのです。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏は、心配しなくていい、間違いなく
お浄土へ生まれさせ仏にするぞ、一緒に仏として はたらいてくれと
真剣に呼びかけ、はたらきかけていただく仏さまの言葉です。
誰の安心のためなのか、この私の安心のための教えです。
第1641回 いつも一緒の阿弥陀さま
令和6年 7月11日~
近頃 ご門徒のお宅へお参りするのがとても
楽しくなりましたと、いうご住職に会いました。
どうしてなのか、「南無阿弥陀仏」の声が聞こえてくると ああここにも、
阿弥陀さまが はたらいておられると味わえるようになったからですと。
朝目覚めたとき 南無阿弥陀仏とお念仏して、ああここに阿弥陀さまが
顔を洗いながら 南無阿弥陀仏 ここにも阿弥陀さまが、
食事のときも、着替えのときも、おつとめをするときばかりではなく、
南無阿弥陀仏といつも私と一緒の 阿弥陀さま。
ご門徒のお宅にお参りすると、お経さんの本をちゃんと
準備して、待っていただいており、一緒に合掌し、いっしょに声を出して
おつとめをしていただくと、ああ、このお宅でも阿弥陀さまは
間違いなく はたらいておられるのだと、確認出来て有り難く
嬉しくなり、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏。
自分の口から出た 南無阿弥陀仏は勿論ですが、近くの
どなたかの口に南無阿弥陀仏が出て、聞こえてくると、
阿弥陀さまのはたらきが、なお一層はっきりと、感じられます。
日差しが 暑い中、境内のお墓参りにおいでの方を見ても、阿弥陀さまが
あの方を、お墓まで導いていただいていると、
法座の時に、沢山の方が本堂に座っていただくと、目でも見えて
とても心強く、頼もしく、お堂いっぱいに南無阿弥陀仏が聞こえてくると、
有り難く嬉しくなってくるものです。
ところで、若いころ、親しい友と また明日ねと 別れる時など
バイバイ、グッドバイといっていましたが、その意味を訪ねてみると
実は、「神様があなたと一緒にいますように!」とか、
「神さまの御加護を!」という意味なのだといいます。
いつも、神様があなたを守ってくださいますように、
というキリスト教の祝福の言葉だったというのです。
そういうことなら、浄土真宗では、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は
いつも阿弥陀さまが一緒という意味なので
別れの時、「では、またあした 南無阿弥陀仏」でいいはずです。
私たちが 気づいていなくても、忘れていても、阿弥陀さまは
いつも私のことを見守り、励まし、導いてくださっているのです。
寝ても覚めても、居ても立っても、嬉しいときも悲しいと時も
悔しいときも、悲しいときも、いつも阿弥陀さまがいっしょ
阿弥陀さまは、私といっしょに、はたらき詰めであります。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏となって。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏。
第1640回 浄土真宗にないもの
令和6年 7月4日~
築地本願寺の晨朝のご法話で、こんな話を聞きました。
京都でタクシーに乗ったら、運転手さんが話しかけてきました。
京都は、どこへいってこられましたかと、聞かれ
本願寺ですと答えると、そうですか、それでは突然ですが
クイズですと。
京都には 数多くのお寺さんがありますが、他のお寺にあって
東西本願寺さんだけにないものがあります。
それは何でしょうかとの問題、質問です。
お寺には必ずあるのに、本願寺だけにないもの、それはなにか。
浄土真宗には、戒律はない、座禅はしない、たたく木魚はない、などと
つぶやいてみましたが、
運転手さんは いえいえ、外からすぐ見えるものです。
思いつかずに、黙り込んでいると、
正解は 入り口の門に、敷居が無いことです。
確かに、山門を入るときに敷居をまたぐことなく、スムーズに
門をくぐって入っています。
多くの人は 門の前で立ち止まり、軽く頭をさげてから、
入っていかれますが、足下を気にするはありません。
お参りの方は、年配者が多く、安全のために 敷居をなくしたのだろう、
今はやりの「バリアフリー」の先取りなのではないかと思っていましたが、
どうも、それだけではないというのです。
普通の寺院は、山門から中は 別の世界、一段高い敷居は、
外の世界と境内を分ける結界であると言うことです。
また木造建築では、敷居は、強度をたかめるためには重要なはたらきを
しているものだそうです。
そこで、またいで通るもの、踏みつけて劣化させないためにも敷居は、
踏まずに、またぐものだといわれるそうです。
山門をくぐって神聖な別の世界に入っていくのが一般の寺院ですが
浄土真宗の寺院だけは ひとり残らず、一人漏らさず
必ず救うという阿弥陀さまの教えを伝えるお寺であるために
結界である、敷居はないのだそうです。
当たり前になって、気づきもしませんが、敷居のないのが、
浄土真宗である 他力のお念仏の教え、そして、浄土真宗の
お寺であると、教えていただきました。
よくお寺は敷居が高いといいますが、浄土真宗のお寺には
敷居がないのです。
いつでも自由に入ってこれるのが、開かれた貴方のお寺なのです。
第1639回 かっこいい大人に
令和6年6月27日~
東京都知事選挙に、異色の候補者が登場し、善戦しています。
ユーチューブという動画配信を使い、情報発信をして有名になった
広島の安芸高田市の市長だった石丸伸二という青年です。
街頭演説では、「かっこいい大人になってください」と、
歩道いっぱいに集まった人々に呼びかけています。
一人ひとりに投票権があり、政治に直接参加できるのに
投票したところで、どうせ変わりはしないと諦めています。
しかし、みんなで投票することで、東京を動かし、日本を動かして
いきましょう。
東京のみなさんは いま日本全国から期待され注目されているのです。
かっこいい大人の姿を、子どもたちに見せてやってくださいとの演説です。
その言葉を何度も何度も、ユーチューブで聞きながら、浄土真宗の
お念仏の教えも かっこいい大人の姿を、次の世代に見せ、
残していくものではないかと、感じました。
多くの人が、死んだら終わり、死んだらすべてなくなると
思い込んで生きています。
しかし、阿弥陀さまは 私たちを、自分の国お浄土へ生まれさせ、
一緒に はたらいてほしいと、呼びかけておられるというのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を口にする人に 仏に成って
すべての人のために、はたらいてくださいと願われているのです。
生きていくためには、どうしても自分の家族や仲間のために、
努力せずにはおれず、利己主義にならざるを得ません。
しかし、やがていのちが終り、仏になったら、
みんなのために はたらいてほしいとの仏さまの願いとは、
いったい何を意味しているのでしょうか。
一人ひとりが、損得ぬきに、自分の出来ること、勤めをはたし
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を口に、にこやかに喜びながら、
いきいきと、堂々と生き抜いていく。
お金や財産などすぐに消えてしまうものだけではなく、
おかげさまでと感謝して、楽しく自信にあふれた、
かっこいい大人の姿を見せていくことが、次の世代に対しての
最高の贈り物となることでしょう。
かっこいい大人になる これがお念仏に生きるということなのでしょう。
第1638回 因を知り 感じる力
令和6年6月20日~
仏教では、因果の道理が説かれています。
因果とは、原因の「因」と結果の「果」で、行いや考え方に
よって、それに応じた結果が出るというのです。
子どものころから、勉強しなければ良い結果は出ない、
努力することこそが大事だと、教えられて頑張ってきました。
病気になるのも、歳を取るのも、自分自身で
その原因をつくっているのだと思い込み、精一杯生きています。
ところで、今、私は、将来のために行動し、様々な原因、
因をつくっていますが、因果関係でいえば 今、結果、果も
受け取っています。
ご恩という言葉がありますが、恩という字は、原因の因と、心と書きます。
現在は 結果であるとすれば その原因を、因をはっきりと知り、
感じとることを、恩を知るということなのでしょう。
今この状態を、なにもかも当たり前と思っていますが、
数多くの人々のご苦労やご縁により、今ここにいるのです。
因果関係を 過去に遡って正しく見つめ、感じる力が
育てられてくると、私の人生は平凡ではなく、とても素晴らしく
有り難いことと味わうことが出来るものです。
これまで育て導いてくださった、両親をはじめ、
気づいていない沢山の人々、いのちを投げ出して、食物となった
動物や植物、そして自然、感謝しても感謝仕切れるものではありません。
どうかご恩を味わう力を持ってほしいと、先輩達は、南無阿弥陀仏の
お念仏を伝え残してくださったのでしょう。
私たちは、明日のこと、将来のことを心配しているにもかかわらず、
知らず知らずに地獄へいくような悪い原因ばかりをつくり続けて
いるといわれますが、心配はない。大丈夫だよ。
南無阿弥陀仏の人は 間違いなくお浄土へ生まれさせ仏にする、
すでに、阿弥陀仏がその原因を完成されているので、心配はないと。
阿弥陀さまは、あなたの未来は大丈夫、任せておきなさい
それよりも、いままで気づいていない、数々の因や縁を、感じ取る力を、
ご恩に気づき 今を喜び、感じ取り、味わえるように
なってほしいと、呼びかけ、はたらきかけていただいているのです。
南無阿弥陀仏は、将来ではなく、今を喜ばせていただく、
報恩のことばです。
第1637回 かんしゃくのくを 捨てて
令和6年 6月13日~
かんしゃくの く(苦)を捨てて 日を暮らす
かんしゃく から、くをとると かんしゃ(感謝)になります。
ご本山の常例布教に出講中のご講師が、ご本山にいる間は
腹を立てることもなく、有り難い日々を送らせていただいています。
何故かというと、それは 腹を立てる相手が近くにいないからですと、
にこやかにお話くださいました。
自分の不甲斐なさに立腹することもありますが、多くの場合
そこに相手がいて、自分と違った主張をしたり、行動したり
思い通りにならないことに、イライラしてしまうものです。
その相手がいなので、腹の立てなくていいとの意味でしょう。
一方 かんしゃくの苦を取った感謝の方は、そこに相手が
居ても居なくても、しかも現在だけでなく、過去も未来も、
有り難く感じ味わうことができるものです。
食事の前の、食前のことば 「多くのいのちと みなさまのおかげにより
この御馳走を 恵まれました。深く御恩を喜び ありがたくいただきます。」
この言葉を通しても、食事の度に 感謝することもできるものです。
ネットで 「感謝する」と検索してみましたら、
日本予防医学協会という
「人生は 感謝するだけで 好転する」とありました。
外国の心理学者の実験で、「小さなことでよいので、感謝できることを
5つ書き出す、それを続けてもらうと、感謝することを毎日考えた
グループは、何もしなかったグループと比べてみると、
感謝することで、幸福度が高まる 体調がよくなる
人間関係がよくなる 生産性が高まる、よく眠れるなど、
様々な良い効果が期待できるということです。
また感謝すると体内で何が起っているのか
科学的研究の結果から、感謝することで、セロトニンや
ノルアドレナリン(情動や感情に作用)、サイトカイン(抗炎症および免疫力)、
コルチゾール(ストレスホルモン)、血圧、心拍数 、血糖値など、
様々な体内のシステムのバランスが取れる、そして、心身の多くの
機能に好影響を与えてくれることが分かってきたと書かれています。
昔から、感謝することは大切!と言われていましたが、心身の健康に
大きな影響を及ぼすことが科学的に実証されてきているのです。
そして、お聴聞をしている人にとっては、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の
お念仏は、感謝を表すことば です。
先輩達は 感謝することで こころと体に、いい影響があることを知って、
私たちに、南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏のお念仏を残して
くださっているのでしょう。
第1636回 まずは 仏さまに
令和6年6月6日~
こんな話をききました。
子どもさんが持ち帰った算数のテスト用紙をみていると、
×が、ついたところがありました。
理解出来ていないのはどんなところかと、問題をみてみると。
りんごを4つもらいました。
お友だち三人で分けたら、一人、何個づつになるでしょうか
という問題に、答えを 1個と書き ×がついていました。
一個と3分の一、分数や小数以下のことが 理解出来ていないと
思い、子どもに聞いてみました。
子どもは こう答えました。
「お友だち三人で 一個づつ分けて、一個は仏さまにあげたので、
みんな一個づつだよ」と、いいます。
「だって、もらったリンゴだから、仏さまにあげなきゃ
いけないでしょう」との答えです。
算数の問題だから、仏さまのことは、考えなくて
いいのと言おうと思いましたが、
なんだか こころが温かくなり、そうだね、いただいたものは
まずは、仏さまにもあげなきゃねと、
そのままにしました。
理科の時間に 氷が解けると何になりますかの問いに、
「氷がとけたら 春になる」と答えた子どもがいたという
話を聞きます。
同じように、頂いたリンゴは 仏さまに、まずはあげるのだという
子どもに 嬉しく有り難く感じました。
近頃 仏壇のある家では、子供たちは育っていません。
自分たち家族だけ、生きている人間中心の生き方を
していては、気持ちのやさしさや 思いやりのある子どもは
なかなか育ってこないのではないでしょうか。
氷がとけたら 春になるとの答えと 同じように、
いただいたものは、まずは ほとけさまに上げるとの
答えも、正解にしたい、こころ暖まる、有り難い答えだと味わいました。
子どもの純粋なこころを、大人たちがだんだんと、損だ得だ、
勝った負けた、比較し競争していくことを教え込んでいます、
例え損をしても、負けても、間違いと言われても
思う存分、心豊かに生きる力を、持ち続けてほしいものだと
思っています。
それを、先輩たちは 仏さま お仏壇 お墓
などを通して、伝えようとして
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏も そうした
先輩たちの願いのこもった ことばなのでしょう。
第1635回 孫たちのために
令和6年 5月30日~
目には見えない 仏さまの はたらきについて こんな話を聞きました。
家には 大きな梅の木があり、毎年その実で、梅干しをつけています。
食卓にいつも置いてある梅干のその実は 父親がまだ小学校高学年の頃に、
おばあちゃんといっしょに植えたものだといいます。
おばあちゃんとお寺参りした帰りに、苗木屋さんの出店に立ち寄った時、
おばあちゃんが選んだものだといいます。
杖をつき背中が曲がった ばあちゃんが、梅の苗木を選んでいると
店のおじさんは 「桃栗三年柿八年、梅はすいすい十三年、・・・
梅は実が付くまで時間がかかるから、ばあちゃんが
生きているうちには
実はならんよ、こっちにしておいたら」と、桃の苗木を進めたそうです。
おばあちゃんは わしのためではなく孫たちのために植えるで
これでええよと、梅の苗木を買ってかえり 一緒に植えたのだと、
父親に何度も聞かされました。
写真でしか見たことのない ひいおばあちゃんが、
植えてくれたものが 梅干しになって、いつも食卓におかれているのです。
ずっと昔の 遠い遠い ひいおばあちゃんが 今でも 私たちのために
はたらきかけていていただいているのだなあと、食べる度に思います。
そう考えてみると、庭にある柿の木も 桃の木も 数多くの花も、
私の知らない 多くの先輩方が、孫やひ孫のために、植えて育てて
くれたものばかりなのでしょう。
そして、この建物も、掛け軸も 置物も、陶器も、敷物も
昔からあって、みんな当たり前で、有り難いなどと感じてはいませんが、
私の周りには、仏さまになった多くの先輩方の思いが、
今でも 生きて はたらきかけ続けているのです。
こうして今、お寺にお参りし、お念仏をしているのも
私自身の力だけではなく、多くの先輩のご縁によって、はたらきかけ、
その力によって、手を合わせ 南無阿弥陀仏と口にしているのです。
仏さまのはたらきかけは 目で見ることはできませんが、
私が気づかないだけで、いつでもどこでも、私のために
体の外からだけではなく、内側からも、はたらきかけ よびかけ
続けていただいているのでしょう。
ぼんやりと生きている私に、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
と呼びかけ、そのはたらきかけに気づかせて
いただいているのです。
気づかなければ 当たり前で、何の感動もない平凡な毎日ですが、
多くの方々の、大きな思いに包まれていると気づかせていただくと
本当に有り難いことばかりです。
ありがとうございます。みんなみんな御蔭さま
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏です。
第1634回 お任せします 有り難うございます
令和6年 5月23日~
朝のおつとめの後、なにげなく外を見ると、
紙袋に、ちり取り、そしてゴミはさみを手にした近所のおばあさんが
道路のゴミを 拾っておられる姿が見えました。
まだ、朝の出勤前で、人通りの少ない時間、捨てられたたばこや
紙くず、ペットボトルなどのゴミを、つまみ取り紙袋に入れながら、
歩いていかれます。
近頃、通りが綺麗になったと思っていましたが、こうして、
一人もくもくと掃除をしていただく方があったからだと、気づきました。
この方は、お念仏とご縁のある方ではないようですが、
それを精一杯やらせていただこう、これもご報謝、これもご報謝と、
報恩感謝の行動を進んで取られておられる方が多いものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 の 南無は 帰命する、帰順すると
私の方が真剣に、仏さまに帰順する、私が努力することが必要と
理解するのが普通ですが、浄土真宗の場合は、そうではなく、
仏さまの方が先に、自分に任せなさい、貴方のことを必ず救う、
心配しないでいい、任せなさいと呼びかけていただいているのだと
味わいます。
その呼びかけを聞いて、私の側は、仏さまの呼びかけに、
お任せします。有り難うございます。
南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏と返事をするだけでいいのです。
私が、頑張ってしっかりと、つかまる必要はなく、どうかよろしく
お願いしますと、こころからお願いする必要もなく 仏さまの方が
先に私のことを心配して、必ず救う私に任せなさいと呼びかけ
続けていただいているというのです。
私が称える南無阿弥陀仏は、ですから、お願いしますの意味ではなく
ハイお任せします、有り難うございますと、報恩のお念仏をする
だけなのです。
一般的には、私が努力して、良いことを積み重ねて、
それを、仏さまに認めていただくことが出来たなら、そのご褒美に
良い結果、素晴らしい効果が得られると思いがちですが、
そうではなく、仏さまが先に私のことを心配して
私にまかせなさい、貴方のことを救いとりたいと
呼びかけ、はたらきかけていただいているというのです。
赤ちゃんのとき、頼みもしないのに、母親がお乳をのませ
おむつを替えて、育てていただいたように、阿弥陀さまは
この私のことを、なんとか本物の人間に、そしてやがて
仏にして活躍してほしいと、はたらきかけ、呼びかけていただいて
いるというのです。
ですから、その呼びかけを聞き取り、お任せします。
南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏とお念仏をして、自分が
今できることを精一杯つとめさせていただく、それが
お念仏の報恩の生活ということでしょう。
仏さまが先か 私が先か、親が先か こどもが先か
お浄土に生まれることも、仏になることも、人間の力の及ぶことのない
ことなのです。
ですから、仏さまにお任せするしか、方法はないのです。
私が出来ることを、報恩の行いを、お念仏と一緒に
つとめさせていただくだけなのです。
第1633回 よく頑張ったね
令和6年 5月16日~
2歳年上の兄が 亡くなったとの知らせを受けて、
慌てて上京して、お別れをしてきましたという方が、
お参りになりました。
学校を出てから、東京で就職し、東京の人と結婚し、子どもにも
恵まれ85歳で亡くなりましたと。
ちょうど、その日、新聞の投稿に、友人の死を悼んで綴られた
文章を見た直後のことでした。
「肩車を してもらっているだろうか 今頃は 戦死した父親に
亡くなった親友は」
と言う内容でした。
兄も5歳の時に父を亡くしています。一番遊んでもらいたいときに
父と別れ、もう肩車してもらうことの出来ない、寂しさを 悲しさを
持ち続けての80年だったのだろうと思います。
新聞の投稿を見た日に兄の死を知り、多くの方々が戦争で
肉親を亡くされたのであろうとつくづく思いました。
そして今も ウクライナやガザ地区では、
親を亡くした子ども、夫や妻、子どもをなくして悲しむ人が
沢山いらっしゃることでしょう。
その悲しみ寂しさは、一生涯深く続いていくことでしょう。
新聞の投稿では、お浄土で父親と再会して、きっと今頃は
甘えていることだろう、との文章でした。
甘えたい、肩車をしてほしいのに我慢していたことを、友人に
話していたのか、それとも友だちが日頃感じておられたのか。
大切な人が去った悲しみが投稿されていました。と
お話いただきました。
そこで、こんなお話をしました。
浄土真宗では、亡き方は、お浄土でじっと
待っていていただくのではないと説かれています。
仏と成って、この世で、はたらき続けておられるのだと。
ですから、この世の出来ごとを、いちいち説明しなくても、
仏となったお父さんは、全部知っておられて、
「大変だったね、ご苦労やったね。よくがんばったね。」と、
今頃は、きっとほめていただいておられることでしょう。
親というものは、生きて居る時は勿論、
亡くなって仏になっても、尚一層、子どものことを案じ、
いつも応援していただいてたことでしょう。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の仏さまとなって、
お父さんと再開したお兄さんは、お父さんといっしょになって、
弟さんのことを、見守って応援しておられるのでしょうね。と
少し疲れて、淋しそうな弟さんに、お話しました。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1632回 母の日のプレゼント
令和6年 5月9日~
サザエさんという子どもに人気のテレビマンガがあります。
日曜日の夕方の放送ですが、ずっと以前に
「母の日の贈り物」という タイトルの回があったということです。
母親のフネさんに 母の日のプレゼント、何をしようかと
兄妹で相談して、いろいろのアイデアを出し合いますが、
なかなか良い案がありません。
それならばと、いっそのこと、受け取る本人である
お母さんに直接聞いてみて、それから決めようということになり
「ねえ、お母さん お母さんのしあわせって 何?」と聞きました。
答えは「あなた達が、元気でいることですよ」と。
これでは、プレゼントのヒントにならないので
重ねて質問してみました。
「お母さんの喜びって何?」と、期待を込めて聞いてみましたが、
返事は「あなた達が いつも笑顔を見せていることですよ」
自分のことではなく、みんな子どものことばかりであり、
どうも、お母さんの中には、自分のことよりも、子どもたちのことで
いっぱいなのだと、分かったものの、お母さんが喜んでくれる
物は、聞き出せませんでした。
ところで、一昔前までは 仏さまのことを親様・親様と
言っていたといいます。
自分のことよりも、子どもの、この私のことを第一に
考えてくださっているのと親と同じように
仏さまは 私のことを第一に、いつも考えてくださっていることを
意味した言葉なのでしょう。
子どもの方は 親の気持ちは ほとんど気づかず、なかなか
味わうことが出来ないものですが、
親は、子どもが生まれるまえから思いを寄せ、生まれて
おっぱいを飲ませ、熱を出したと心配し、幼稚園、小学校、
中学校・・・ずっとずっと、手塩にかけて育てていただいたことに
ほとんど有り難さを感じることもなく、みんな、当たり前になって、
感謝の気持ちは、少しも持ち合わせていません。
同じように、仏さまも このわたしのことを、
見守り励まし 導いてくださっているのに
私たちは、まったく気づいていません。
それが、仏さまのお話を聞かせていただくことで、
お聴聞することで、その思いや、はたらきが、少しづつ
味わえてくるものです。
それとともに、自分の親や兄弟 祖父母、周りの人々の思いを
気づかせていただくことが出来るように育てられていくのです。
そうすると、なんと有り難いことばかりなのか、勿体ないことか、
大きな喜びを感じることが出来るものです。
母の日に、贈りものを渡すだけで終わらずに、親たちが
もっとも喜んでくださるのは、子どものわたしが
活き活きとして喜び多く、笑顔で生きていることでしょう。
それが最高の親孝行、最高のプレゼントではないかと、味わえます。
そう味わうと、生きている親にだけでは無く、仏さまになって
私を応援してくださっている方々をも、今からでも喜ばせることが
出来るのです。
先だった親たちを、喜ばせるのは、お聴聞して、その思いに
気づかせていただくこと、そう考えると、親孝行は
今からでも出来るのです。
まだ、遅くはないのです。
第1631回 いつも一緒に
令和6年 5月2日~
こんな話を聞きました。
幼稚園や保育園の子供たちを見ていると、気持ちは急ぐものの
体がついていかず、足がもつれて、よく転ぶものです。
4歳ぐらいの男の子が、転んで泣き出してしまいました。
すると、同じ年頃の女の子が、男の子のすぐそばに
近づいて、一緒に寝転んで、男の子の顔をじっと見つめているのです。
泣いていた男の子は、その女の子が、自分を見つめているのに気づき、
泣き止みました。
そして、二人ともゆっくりと起き上がり、また元気に遊びはじめました。
大人は、泣いている子どもに声を掛け、手を差し伸べて、
起こそうとしますが、同じ年頃のその女の子は、地面に寝て
泣いている子どもと同じ高さで、その子を見守っていたのです。
ころんで泣いている子どもが、自分のことを心配してくれる友だちの
存在に気づいたとき、安心したのか、はずかしくなったのか
急に泣き止み自分で起き上がったのです。
誰かに助け起こされるのではなく、自分で起き上がり、何でもなかった
ように、また遊び始めたのです。
自分のことを心配していてくれる人の姿に気づいたとき、泣き止み自分で
立ち上がったのです。
大人はついつい上から見下ろして、声を掛けたり、手を差し伸べて
助け起こそうとしますが、幼い女の子は、泣いている子どもと同じ目の
高さで、じっと見守っていたのです。
南無阿弥陀仏の阿弥陀さまは、声の仏さま いつも私を心配して
見守っていただいているのです。
ところが、それに気づくことなく、泣き叫んでいるのが私たちのようです。
そこに、南無阿弥陀仏の声が聞こえてきた時、この私のために
いつでも寄りそっていただいている、仏さまがあることに気づかされると
自分自身で、立ち上がる力がわいてくるのです。
気づくか 気づかないか、南無阿弥陀仏のお念仏は、
私を見守り応援していただいている、阿弥陀さまという 仏さまが
どんなときでも、どんなところでも、私のすぐ横で、いつも一緒
であることを、教えていただいているのです。
お念仏に遇うことで、私の人生は まことに有り難く
感じられてくるのです。
阿弥陀さまが 寄りそい、はたらきかけていただいていると、
気づき、感じさせていただく人生をおくりたいものです。
第1630回 よろこぶ こころ みにうれば
令和6年 4月25日~
お料理の店を開いていた板前さんは、
自分がつくった料理を 美味しい、美味しいと
食べてもらうのが、一番うれしかったと。話してくださいました。
現役を退いた今でも、材料が手に入るとドレッシングなどを
大量につくって、近所の人に配っていますと、私も一ついただきました。
まるで、仏さまのようですね。
仏さまは、お浄土へ生まれるのだと知った人が、南無阿弥陀仏、
南無阿弥陀仏と喜んでお念仏をしている姿を見るのが、最もうれしいと、
喜んでおられるといいますからね。
私たちが子どものころから受けてきた教育は、新たな知識を得ることで
表には現れていない、いろいろの事実を発見し理解出来るようになり、
より多くの喜びを感じることが出来るようになるものです。
それに対して、宗教は ごく普通の当たり前のもの、平凡な出来事を、
ちゃんと見て、気づき、感じる力を 育てていこうとするもの
でしょう。
仏さまのお話を聞くことで、この私のためにどれだけ
多くの人々が ご苦労いただいているのかを、感じとる力が、
育て
普通の出来事が
有り難いことであると
そうした力が、身につき始めると、私の人生は 平凡で、
つまらないものではなくなり、とても有り難く意義あるものであると
感じられてくるものです。
鈍感な私に その真実を知らせ、感じ味わうことの出来る力を
育ててくださるのが、南無阿弥陀仏の教えでしょう。
南無阿弥陀仏のお念仏は、自分で経験する前に、失敗する前に
その真実を、有り難さ豊かさを気づかせるはたらきがあるものです。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、お念仏の教えに遇うことで、
大きな力が、はたらきがあることを、知らせることによって、
普通で、当たり前にしか見えないものを、出来事を、本当は
とても有り難く、素晴らしいものであることに気づかせ、
それを感じ取り、感動する能力を育てていただくのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を聞き、口にする生活は、
その感受性が
お聴聞することで、親たちが最も喜んでくれる生き方が、
知らされるのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 は 仏さまの願い 親たちの願いです。
第1629回 視点が変わると 世界が変わる
令和6年 4月18日~
本願寺派の宗門学校 中央仏教学院には、通信教育があります。
そのホームページに、「通信教育で学びませんか」と、
福間学院長の
ネットにこんな話が載っておりました。
あるサラリーマンが真夏に出張に出かけ、電車を降りてバスに乗りました。
するとバスは満員ですごい熱気でした。
「しまった、タクシーにすれば良かった。」でもバスは動き出し、
もうどうしようもありません。
すると赤ちゃんの泣き声が聞こえてきます。もう最悪の状況です。
彼は思いました、「ああ最悪のバスに乗ってしまった。」すると、
その泣き声が近づいてきました。
赤ちゃんを抱いたお母さんがバスを降りようと、入口近くにいる
彼に近づいているのです。
「
バスの運転手が下りようとしているお母さんに聞いたそうです。
「その赤ちゃんはどうされたのですか?」
「熱があって泣いているのです。」
「でも大学病院はバス停が3つ先ですよ。」
「この子が大泣きして迷惑をかけているので、ここから病院まで
歩いて行こうと思うのです。」
こんな会話がすぐそばの彼に聞こえてきたそうです。
するとバスの運転手は、やおらマイクで乗客に語りかけました。
「この赤ちゃんは熱があるそうです。あと3つのバス停で病院です。
それまで我慢していただけませんか?」と。
その後バス内は大拍手が起こったそうです。
お母さんは泣きながら乗客達に有難うとお礼をしたそうです。
その時サラリーマンは思ったそうです、
「自分は最高のバスに乗った。」と。
この運転手の言葉の働きが仏法です。
視点が変わると世界が変わるのです。
仏法の視点を持つ時、今までとはまったく異なる世界が広がります。
閉塞した世界が広い世界に転じられるのです。
みなさんも通信教育で仏教を学びませんか。
家事やお仕事をされながらでも学ぶことができます。
まず、いつでもどこでも短時間で仏教・真宗が学べるようにと、
スマホやタブレットで学習できる入門課程を用意しています。・・・・と
損得勝ち負けだけの価値観で生きていますが、
仏教の教え、お念仏の教えに出会うと、違った世界が見えてくるものです。
お聴聞 お聴聞といいますが、新たな価値観を知らされていくのです。
それがお念仏の教えです。
第1628回 仏さまは 忘れずに
令和6年 4月11日~
こんな話を聞きました。
浄土真宗には 有り難い学者さんが沢山いらっしゃいますが、
昭和の初期に 広島に是山恵覚 (これやま えかく) という
和上 (わじょう) さまがおられました。
たくさんの書物を残されており、また、たくさんのお弟子さんを
お育てになった有り難い方です。
しかし、晩年には残念ながら認知症になられ、毎朝お勤めして
おられた正信偈でさえも、最初の「帰命無量寿如来……」は
出てくるものの、次の二句目が、どうしても出てこないことも
ありました。
一緒にお勤めをしておられた坊守さんは、
「昔は、難しいことばでも、みんな暗記し、すらすらと書かれて
いたのに、いまでは、お正信偈も出てこなくなって……」と、
悲しそうにつぶやかれました。
それを聞いた和上さまは、
「私が忘れても、仏さまが忘れてくださらんけえ、大丈夫じゃのう」
坊守さまに向かって、「私はあんたの顔も忘れていくじゃろうし、
この口から、なまんだぶつのお念仏も、出てこなくなってしまうかもしれん。
それでも、大丈夫。大丈夫。
私は何もかも忘れても、私を忘れてくださらん仏さまが、いまここに
いらっしゃるじゃないか。なまんだぶつの仏さまが、いまここに
おられるから、
いのちの長い短い、死に方の良し悪しも一切問題ない、
あなたの生き方に、何の要求もされない。あなたの身の振る舞いに、
何の注文もつけない。今後あなたがどのような生き方になっても、
どのようないのちの終わり方になっても、決して見捨てたりはしない。
いまこの私のいのちと、ご一緒に、歩みを運んでくださるお方が
阿弥陀さまという仏さま。何があっても、お浄土に一歩一歩、
一緒に足をお運びくださる、仏さまです。
苦難の多い人生ですが、南無阿弥陀仏の仏さまとご一緒に、
生き抜いていける道が、ちゃんと整えてあると味あわさせていただきます。
第1627回 体の中では 変化が
令和6年 4月4日~
こんな話を聞きました。
「誰かに親切にしたことを、思い出せますか ? 」と
質問すると、多くの人が なかなか思い出せないものです。
ところが、親切をしているという自覚がないまま、
人とすれ違う時に道を譲ったり、道に迷っている人を案内したり、
氣づけば普通にしているものです。
『親切は 脳に効く』(デイビット・ハミルトン著、サンマーク出版刊、
2018年5月30日初版発行)という本があり、そこには
親切な行為を、科学的に検証してみると、本人にも他人にも社会にも
プラスの副作用を もたらすと書かれています。
気遣いや親切は、日本人には当たり前の話で、先祖代々受け継がれ、
遺伝子に組み込まれたもののひとつでしょうが、親切な行いが
気持ちがいいのは 脳内ホルモンのオキシトシンが、増量され
炎症を抑える作用や、心臓を強くし、血圧を下げ、老化を遅らせ、
うつ症状を治すなど、大きなはたらきがあるからだといいます。
あの人は、とても若く見えるとか、どうも老けて見えるなど、
その人の見た目の印象も、親切や・やさしさに包まれた生活を
しているのか、そうでないかで、違ってくるのでしょう。
日頃、親切にすることが出来る人は、自分に対しての親切や、
思いやりにも、敏感に気づくことが出来、感謝の気持ちを
持てるものです。
ありがとうと思う時、脳内では、幸せホルモンのセロトニン、
集中力・意欲アップや幸福物質とも呼ばれるドーパミン、
絆ホルモンと呼ばれるオキシトシン、免疫アップなど脳内麻薬とも
言われるエンドロフィン等が分泌されると言われています
南無阿弥陀仏のお念仏は、私のことをいつでも、どこでも、
思っていてくださる方があることに、気づかされ、感謝することばです。
「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と聞えてくると、数々の思いやりや、
親切に気づかされ、いつも見守ら、励まされていることを実感し、
感謝の気持ちが起こるとき、私の体の中では、大きな変化が起こって
いるのです。
お聴聞をして、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏を口にする生活は、
ここちよく、ありがとうございますと、よろこびを感じられるのは、
こうした体の中の変化が起こっているからなのでしょう。
第1626回 これさえ残せば
令和6年 3月28日~
墓地の草を取っていると、高齢の男性がお参りになりました。
今日は 父親の命日で お参りにきましたと、50回忌もとうに終わり
80年前になくなった父親です。
その方がおっしゃるには、日にちと時間を知らせる目覚まし時計で
起こされたのですが、今日が父親の命日であり、また外孫の
一人の誕生日であることに気づきました。
ご院主さんに教えていただいて、今ユーチューブで、ご本山の
ご晨朝に、毎日あわせていただいていますが、お勤めの後、御文章を
聞きながら思いました。とお話しくださいました。
一年365日ですから、確率は365分の一でしょうが、たまたま
孫が私の父親の命日に生まれています。父から見ればひ孫にあたるのですが、
その孫が、これからの長い人生、どうか喜び多い豊かな人生を送って
くれるようにと願うものの、遠くに住む孫に対して、経済的に
援助してやれるだけの財力もなく、何かしてやりたいものの、
どうしてやることもできません。
そう思っていると、私が子どもや孫を思うように、私の父親や
祖父母も同じように私のことを思っていてくれているのだろうなあと、
思い当たりました。
ご本山の、御文章の拝読を聞きながら、これこそが、親たちが
私に当てた手紙であり、そして、私が子どもや孫に伝えたい内容であることに
気づきました。
お念仏の教えにさえ出会ってくれれば、老病死、いかなる苦しみの時も、
きっと力強く生き抜いてくれるに違いない、これさえ残しておけば
間違いないと思いあたりました。
そこで、孫や子どもが、間違いなくお念仏に出会うことができるように、
はたらきかけてほしい、ご縁をつくってほしいと、お墓参りにきたのです。と。
第1625回 みんな違ってみんないい
令和6年 3月21日~
こんな話を聞きました。
日曜学校の子どもたちに、
赤い丸いものをイメージしてくださいというと、
それぞれに違ったものを教えてくれます。
真っ赤なリンゴ、トマト、イチゴ、太陽、信号機、日の丸の旗、など
いろいろなものをイメージして発表してくれます。
同じ、ことばでもそれぞれに違って受け取るものであることを
教えてくれます。
私たちは自分と同じことをみんな思っていると、ついつい思いがちですが
そうではなく、みんなそれぞれに違った受け止めをしていることが
分かります。
いくら説明しても、あの人はどうして分かってくれないのかと、
悩みをもつものですが、それぞれに個性があり
自分とは同じではないことを、理解しておきたいものです。
そういう自分自身でも、時とところと、時代が変われば同じ言葉でも
まるで違ったものを想い浮かべています。
子どもの頃から、正しい答えは一つと、思い込んで成長してきましたが、
大人になってみると、答えは沢山あるものです。
お経には、青い花は青く輝き、黄色の花は黄色く、赤い花は赤く、
白い花は白く、それぞれに、すばらしく美しく、その香りは気高く
清らかであるとお浄土のことが説かれています。
それぞれの花がいのちをもっていて、自らの色そのままで輝いて
咲くことが尊いことであると語られています。
花の色は、人間の個性をあらわしており、この世の中に
たった一つしかないかけがえのない尊いものです。
他と比べて優劣がつけられるものではありません。
私が私に生まれたということ、そのことが尊く思え、
そして一人ひとりが今、輝いている。
みんな違ってみんないい、そう味わえる人生を
送らせていただきたいものです。
第1624回 いつも 私を
令和6年 3月14日~
知り合いのお嬢さんの結婚披露宴に出席しました。
新郎新婦の紹介が、写真を大きく映しながらありましたが、
新婦さんが、こんな風に話してくれました。
アルバムを開き、多くの写真を見ながら、
どの写真を使おうかと、選び出していたとき、気づいたことがあります。
赤ちゃんの時から、幼稚園、小学校といろいろの行事、
そして、遊園地や海水浴、旅行と家族揃って写った沢山の写真に
兄弟や母親は、写っているのに、父親の姿が、一つもないのです。
知らない人が見れば、父親の居ない家族と思われるでしょうが、
車を運転して、いつも連れていってくれたのは、お父さんでした。
そのお父さんが、どこにも写っていない。
それは、いつも父さんが写真を撮ってくれていたからです。
そう思って、写真を選んでいると、どの写真も、
ただの記念写真ではなく、お父さんのまなざしの記録であるということに
思いあたりました。
当たり前になっていましたが、
いつもあたたかいまなざしの中に、生かされていたことに
写真を選びながら、はじめて気づきましたと
父親への思いとお礼のことばがありました。。
これを聞きながら、
私の周りの多くの人々も、阿弥陀さまも、
どの写真にも写っていませんが、いつも私を見守り、励まして
くださっているのに、気づいていない私がいることに。
私が気づかなくても、いつも見守って応援し、サポートして
くださっているのに、気づかなければ、何でもないことですが、
気づくと、本当に有り難いことだと、感じさせていただきました。
当たり前で終わらずに、多くの思い、はたらきかけに、
気づくか気づかないかで、私の人生は 大きく違ってくることを。
第1623回 はたらき続ける
令和6年 3月7日~
先日 お寺の年忌法要をお勤めしました。そこで、こんな
挨拶をしました。
西蓮寺さま 光明寺さま そして、ご参列くださいました
みなさまのお陰で 前住職の25回忌 前坊守の7回忌法要を
おつとめすることができました。誠にありがとうございました。
次の 33回忌は 8年後、 13回忌までは 6年もありますので、
これは、若い方に、よろしくお願いしたいと思います。
若いといえば、今 若い人の将来の人気の仕事は、ユーチューバー
だそうですが、このひと月 私も ユーチューバーをやっておりまして、
ユーチューブに画像をアップしておりました。
内容は、電話で法話をしておりますものを、動画にしたもので、
親鸞聖人のまとめていただきました、
お釈迦様が説きたかった、仏さまのはたらきは
お浄土へ往生させる 往相と、 仏となったら、この私たちを導く
還相のはたらきがあるということだとあります。
どんなはたらきか、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と耳に聞こえる
仏さまとなってはたらきかけておられるとあります。
ですから、今日、ずうーうと、はたらきかけ続けていただいていた、
そうした内容を 四、五分でアップしたものを、30本ほど、
現代語訳のお聖教と合わせて
一日、300回ほど
いただけるそうで、それを期待していますが、現在 521人の段階です。
どうぞ、ご協力くださればありたたいことです。
孫、ひ孫、ヒイヒイ孫も、参列しておりますので、
仏さまに成られた お二方も喜んでいただいていると思います。
別室で、おときを準備いたしておりますので、そちらへどうぞ、
第1622回 諦めず呼び続ける
令和6年 2月29日~
大阪に行信教校という 浄土真宗の専門学校がありますが、
その卒業生の方が 在学中の校長先生のご法話を思い出して
こんな話をされました。
まだ携帯電話が珍しい頃のこと、新しいもの好きのこの先生は
早速購入されたそうです。しかし、携帯電話の電源はいつも
切ったままだったと言います。
それは、どこからか電話があるのが、イヤで、自分の方から電話を
するとき以外は、電源を入れることはなかったといいます。
ある日、先生が 外出中に、お寺に急ぎの電話があり、
坊守さんは住職さんに、連絡をとりたいものの、いくら電話をかけても
つながらない。
それでも、諦めないで、繰り返し繰り返し、電話をされ、いつか電源が
入るときに、気づいてもらえるように、かけ続けられたそうです。
そして、ついに、重要な急ぎの連絡がとれたことがあったといいます。
そのことを、校長先生は、ご法話で、有り難いことだと気づいたと。
阿弥陀さまも、こっちが電源を入れていなくても、気づかなくても、
絶えず、呼び続けていただいている、いつか気づいてくれるだろうと、
諦めず呼び続けていただいているということに、
携帯電話を通して、阿弥陀さまの有り難さを 改めて
味わわせていただいたとのお話だったといいます。
「心配いらない必ず救う お浄土に生まれさせ 仏にするぞ」との
はたらきかけに気づかずにいるのが 私たちなのでしょう。
それでも、あきらめることなく南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と
呼び続けていただいている。
いつかは気づいてくれることを願いながら、そして、先だった父、母、
祖父母は、阿弥陀さまと一緒になって、一日でも早く気づいてくれ、
気づいてくれと呼び続けていただいている。、
そして、南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏の呼びかけに気づくことが出来れば、
平凡なつまらない、当たり前の人生ではなくなりますよ。
仏さまになるこの身であることに気づかされ、人生の受け取り方が、
生き方が違ってくるものですよと、
はたらきかけ続けておられるのです。
私のことを、諦めず呼びつつけていただいているのです。
自分だけのいのちではなく、仏さまになる尊いいのちを今
生かされているのですと。
第1621回 ける かるのご法話
令和6年 2月22日~
こんな 話を聞きました。
「ける・かる」という お話です。
ある法座で、連続してご法話があり、最後のご講師の
時間が無くなってしまいました。
そこで、ご住職さんは、大変申し訳無さそうに、
終わりの時間も迫っていますので、ご法義を短く、一言で
お願い出来ませんでしょうか、お頼みしますと。
その先生は分かりましたと、うなずき登壇されました、そして、
ご門徒を一通りご覧になり、
「ける、かる」とおっしゃって、「肝要は ご文章で」と、
ご文章を拝読され、降壇されてしまいました。
一瞬の出来事に、ご門徒は唖然とするばかり、
驚いたご住職さんが、あわてて講師控室に伺って
誠に申し訳ありませんでした。ご無理を申して、でも
どうゆう意味なのでしょうか。「ける・かる」とは、恐縮しながら
お尋ねしました。
「一言でとのことでしたから、一言で話したまでのことですよ」と、
ご住職は、どういうことでしょうか。と
ご講師は、「ける」とは、阿弥陀様のお喚び声、はたらきです。
それは、私の行為や努力に関係無く、必ず救ってくださる。
阿弥陀様は、助けるの仏さま、つまり、【助(ける)】の、けるです。
そして、「かる」とは、私の側の話です。
その阿弥陀様のお救いに私たちの疑いや、はからいを、持つ余地もなく
南無阿弥陀仏で、私は、ただ助かるのです。
つまり、私の方は【助(かる)】、ただ助かる(救われる)だけ。
ですから、かるです。
阿弥陀様は、私を助けるのける、
私の方は、 助かる、かるです。
そこで、「ける、かる」と一言お話いたしましたと。
これ以上短い法話はないでしょう、これこそが
「ける、かる」に込められた阿弥陀様のお心、すべての人を救うという
阿弥陀さまのはたらきのお話です。
第1620回 赤ちゃんに聞く
令和6年 2月15日~
西本願寺のお晨朝のご法話で、こんな話に出会いました。
ある布教使さんが、布教のため海外に出かけられた時のこと、
ご法話の後に、質問の時間があったそうです。
そこで、ある若いご婦人が、「お任せする、阿弥陀さまに任せる」
ということは、どうゆう事ですかとの質問があったと言うことです。
外国の人に、どのように説明すれば理解していただけるか、
一瞬迷ったものの、質問した方が赤ちゃんを抱いているのに気づき、
「その答えは、抱っこしているあなたの赤ちゃんに聞いてみてください」と
答えられたということです。
赤ちゃんは、母親を信じ切って、すべてを任せて安心して抱かれています。
お腹がすいたら泣けば、間違いなくおっぱいがもらえます。
何の疑いもなく母親に任せきりで生活しています。
同じように 私たちも、阿弥陀さまにおまかせして生活するのが、
浄土真宗の教えとの味わいでしょう。
ところで、思い出すと、赤ちゃんも成長し、少し知恵がついてくると、
なかなかそうもいきません。
小さな子どもを、遊園地に連れて行ったとき、ジャングルジムにつかまり、
年上の子をまねて、どんどんと登っていき、一番高いところにまで登りきり。
振り向いて、親がいることを確認し、自慢げに一瞬笑顔をみせますが、
その高さに気づき、怖くなって、ついには泣き出してしまう子がいます。
「大丈夫、自分で登れたんだから、ゆっくり降りて来なさい」といっても、
怖がって、棒にしがみつき固まってしまいます。
親が、いくら呼んでも、泣くばかりで身動出来ずにいます。
親が上まで登っていき、体を支え、手を持って棒を持ち変えさせてあげると、
一つずつ、ゆっくりゆっくり、降りることが出来るものです。
阿弥陀さまは 南無阿弥陀仏と私を呼び続けておられます。
心配要らない大丈夫、今やれることを精一杯やればそれでいい、
南無阿弥陀仏を口にして生活をしなさい。間違いなく救うから安心しなさいと。
怖くて立ち止まり、どうすることもできない時も、大丈夫 大丈夫と
呼びかけていただいています。
高いところに登って怖がっている子どものように、立ちすくみ心配して、
動くことが出来ない時でも、その声に励まされ、次へ進むことが出来るのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の声は、大丈夫、大丈夫と
阿弥陀さまと一緒になって、父も母も、南無阿弥陀仏と
呼びかけてくれているのです。
貴方と同じように、悩み苦しみ 悲しみながら、母さん達も
生きた来たんだよ、大丈夫、南無阿弥陀仏で大丈夫だから、
心配せずに大丈夫だよと、呼び続けていただいているのです。
第1619回 遺伝に加えて
令和 6年 2月8日~
間違えて、うかつにも別のお宅にお参りする
慌てて、本来のお宅に電話をして
たまたま土曜日で 80歳代のご主人と 隣の住宅に住む
50代の息子さんが
「会社の方はどうですか、若い方は なかなか大変でしょう」と
話しかけると、「今の若い人は よく分かりませんよ、
男までも 髪をそめるし、爪にまで色のついたマニキュアはしてくるし」
と、笑いながら答えられました。
「手は汚れる仕事ですか、手袋はするんでしょう。」
「油が付くので 手袋はしていますが、どうも理解出来ない」と。
でも、考えると ライオンも鳥たちも メスより 雄の方が
立派で 目立つようですね。
動物は 本来 雄の方が 目立つように 選ばれるように頑張るものかも
しれませんね。と話しながら おもいました。
動物たちは 本能 遺伝子で、生き抜く智慧を、次の世代に伝えて
いくでしょうが、人間はそれに加えて、言葉を使って 文字を使って、
より多くのことを伝達してきたのではないかと思いました。
それが、現代は 表面的で利己的な動物的な本能は伝わっているかも
しれませんが、精神的なこころの有り様の伝承は はたして出来て
いるのだろうかと思えてきました。
宗教というものは、特に 南無阿弥陀仏の教えは、人間が動物ではなく
人間として 生きがいを持ち よろこびを感じ、協調して生きていく
その力を 次の世代に伝えようとするものであり、それが、はたして
現代は うまくいっているのか。
だんだんと、動物的な本能をむき出しにした、価値観が中心になって
いっているのではないかと、思われます。
すべての人が、人間として充実して喜び多く、生きていることが、
有り難く感じられる、そうした価値観が忘れられ 消えつつあるように
思えてなりません。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は 先輩達が伝え残したかった、
人間の本当のよろこびを 感じ味わう力を受け継ぎたかったのだろうと
思います。
もっとも大事なものを 残し相続してほしいと。
第1618回 遠くて 近いのは
令和6年 2月 1日~
日頃 車でばかり移動していますが、忘年会や新年会
お酒を伴う会合では 自分の車で出かけるわけにはいきません。
研修会など、1時間以上かけて遠くから参加される方、
特にお酒の出る会合では 悩まれることだろうと思います。
先日、久しぶりに、ひとり、てくてくと歩きながら、
一休さんと 蓮如上人の逸話を思い出しました。
浄土三部経の一つ 「仏説阿弥陀経」には、
「ここから西の方へ十万億もの仏がたの国々を過ぎたところに、
極楽と名づけられる世界がある。そこには阿弥陀仏と申しあげる
仏
説かれています。
そこで、一休さんは
極楽は十万億土と説くならば 足腰立たぬ婆は行けまじ と
読まれたと伝えられています。
お念仏の教えは、阿弥陀さまのはたらきである他力というが、
お浄土までが、十万億の仏の国々を超えた世界であるのならば、
とても、老人ではたどりつくことができないではないか、との
皮肉がこめられた歌とも取れます。
それに対して 蓮如上人は
極楽は十万億土と説くなれど 近道すれば南無のひと声
一休さんは 修行してさとろうとする 聖道門の方ではありますが、
阿弥陀さまの他力のお念仏の教えに 好意的で 理解されていたのだと
思います。
そこで、庶民の疑問をうたでよみ、蓮如上人がどのように
答えてくれるのかを 楽しみに 問われたのでしょう。
お釈迦様の教えも お弟子さんの問いに答えて説かれたものが
ほとんどと言われます。
仏教の教えは 問題意識 問いがなければ とても伝えることのできない
大きく深い教え、漠然と聞くのではなく、人生、毎日の生活の
老病死をはじめ、苦悩の中で 問いを持ってお聴聞すると
私のための教えであったと 納得いくものです。
どんなに遠くにあろうとも、南無阿弥陀仏のお念仏一つで 仏の国に
生まれ、今度は 人々を救うはたらきに従事するのだよ、待ってるよと、
私の大切な人々が 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と 見守りながら
よび続けていただいているのです。
第1617回 梅は こぼれる 菊は 舞う
令和6年 1月25日~
早いもので 境内の紅梅、白梅ともに 開きはじめました。
日本語には 豊かな表現があり、梅の花は 丸く咲き ちょうど
涙のように見えるので 花が散ることを 涙がこぼれるようだと
梅の花は こぼれると言うのだそうです。
昔から〝桜散る こぼるる梅に 椿落つ 牡丹崩れて 舞うは菊なり“と
この他 朝顔は しぼむともいいます。
「しぼむ」、「落ちる」「くずれる」等、花びらの変化を表した
味わい深い表現です。
では どうでしょうか、私たち人間の最後は……? と聞かれると
私たちはついつい「死ぬ」と答えてしまいます。
また「人間死んだら終わり」ということも耳にします。
しかし、いのちの終え方は「死」や「終わり」だけではなく、
違った言葉があるものです。それは 「往く」という表現です。
花の終わりも、言葉で雰囲気が違って聞こえるものですが、
私たちの終わりも、表現することばで、大きく違ってくるものです。
「往く」の元になっている言葉は、「往生」です。
私たちのお仏壇のご本尊、阿弥陀如来が、私たちの為に開かれた
救いの世界、お浄土に往き生まれることを「往生」と言います。
人間がいのち終えることを、「終わりだ」「死だ」と表現するのは
私たちの見方。
一方で、阿弥陀さまは「仏としてのいのちの始まりだ」
「生まれるんだ」と、
阿弥陀さまは、死で終わりではないよ、
お浄土に往生させ、仏さまのいのちへと実を結ばせたいと
願いを発して、はたらき続けてくださっています。
私たちは、美しく咲く花だけしか見ていませんが、
やがて枯れて、散ることで、実を結ぶことが出来るのです。
その果実が、次のいのちを生かしてゆく、重要なはたらきをするのです。
仏さまへと実を結ぶと、今度は 慈しみをもって多くのいのちを包み、
育み、導いていくはたらきが出来るのです。
先立って仏さまと成られた方々の ご苦労で はたらきによって、
お念仏に 南無阿弥陀仏に 出会えたのが、この私なのです。
そう考えると、人間に生まれて、今 花をさかせていますが
南無阿弥陀仏のお念仏で、
そして人間の時よりも、もっと大きな 重要な はたらきができる世界に
生まれるのです。
今、まだ助走中で これからが 本番、大事なはたらきが、
本来のはたらきが
第1616回 渋柿の渋
令和6年 1月18日~
渋柿の 渋がそのまま 甘味かな
という句があります。
私どもの寺院の境内に 甘柿と渋柿の木があります。
青い間は甘柿も 渋くてとても、食べられませんが 赤く色づいてくると
渋味が取れて、食べることができるようになります。
一方、渋柿の方は 赤く色づいても渋がのこり、完全に熟してぶよぶよに
柔らかくなってしまうまで、渋みが残っています。
色づいた渋柿をもぎ取り、皮をむいて 軒先に干していると だんだんと
甘みが出てきて、甘柿以上に甘みが強い 干し柿が出来上がります。
干し柿の渋がぬけるのには、太陽の光や冷たい風、夜露などの力
自分の力ではなく 大きな自然の力、はたらきによって
変えられていくのです。
ご和讚に
罪障功徳の体となる
こほりおほきにみづおほし
(『高僧和讃』曇鸞讃 『註釈版聖典』585頁)
氷が多ければ多いほど とければ水が多いように、渋が多い渋柿の方が、
甘柿にくらべて甘みが強くなるものです。
私たちも 悩み苦しみ悲しみ、怒り腹立ち煩悩が多い人ほど よろこび多い
人生へと転じられて、味わい深い人生に変えられていくことでしょう。
仏さまのはたらきを 光であらわしますが、干し柿も 光や風のはたらきで
大きく変化させてもらうのです。
氷も 光や風 暖かさでとけてくるものです。
仏さまの大きなはたらきを 繰り返し聞かせていただき お念仏の生活を
はじめてみると、煩悩一杯の私が、渋一杯の柿が、少しづつ甘みが強くなる
よ
渋が甘みに変えられていくように、煩悩が喜びに変えられていくこの教えを
素直に受け取って 悩み苦しみ悲しみから 転じられ、有り難い充実した
人生を 南無阿弥陀仏とともに 送らせていただきたいものです。
第1615回 ただ念仏して
令和6年 1月11日~
これまで 私どものお寺での ご正忌報恩講では
御絵伝を写真にとって プロジェクターで投影しながら
親鸞聖人のご苦労を、四幅の絵像を、二日間にわけて
解説していました。
今年は、本願寺派の総合研究所で作成された 「はじめての歎異抄講座」
を、アレンジしてのご正忌報恩講にしたいと 今 準備しています。
歎異抄の魅力についての項目や 歎異抄の概要と構成などの説明につづき
歎異抄誕生の背景 親鸞聖人のご生涯から という項目があり、その中に、
比叡山で厳しい修行をし、煩悩を無くして、さとりを開こうと
親鸞聖人は、20年間、努力されてきたものの、どうしても煩悩を
無くすことが出来ず、悩まれていました。
そして、得度した青蓮院の近く、吉水の法然聖人の元を訪ねられると、
そこでは、比叡山とはまったく違って
「阿弥陀仏の救いの前では、煩悩は邪魔にはなりません。
阿弥陀仏は どんな人もわけへだてなく、お救いくださるのです。」と
そして、命懸けの厳しい修行するのが仏教の常識であるのに、
「ただ念仏して阿弥陀仏に救われ往生させていただくのですぞ」との
ことばに 非常に驚かれたことでしょう。
そこには、比叡山とはちがって、僧侶ばかりではなく、
商売をする普通の街の人たち、女性も その話を聞いて、
よろこびお念仏をしている人たちがいたのです。
仏さまは すべての人を救おうとされる、すべての人を
救うには、誰でもできる方法、それはこれしかないと、お念仏に
生きる道を選ばれたのです。
自分の力で さとりを開くのが仏教ということを信じて、
励んでこられたのに、人間の力を頼っては、すべての人が
すくわれることはなく、
仏さまのはたらきによらねば、お念仏でなければと
確信されたのです。
阿弥陀さまは 信じさせ お念仏させて お浄土に往生させたいと
はたらき続けておられることを、親鸞聖人は、かずかずの書き物を残し、
私たちに 教えていただいているのです。
第1614回 生かされている不思議
令和6年 1月4日~
こんな話を聞きました。
築地本願寺の朝の法話で ある布教使さんが
お話しいただきました。
あるお寺にうかがった時 有り難い尊い方とお会いしました。
それは、ご年配の方ではなく、20歳の青年でした。
ご法座が始まるまでの 短い時間でしたが、
その青年は 自分が生まれたときのことを話してくださいました。
わずか八百グラムの未熟児として誕生したのだそうです。
そして、すぐに集中治療室に入れられ、無事成長出来るかどうかわからない
退院出来ても、何歳まで 生きておれるか分からないと、
両親には告げられたということです。
その私が 20歳を迎えることができたのです。
これは みなさんのご苦労、多くのご縁のお陰です。ですから、
私は、みなさんへご恩をお返していくことが、勤めだと感じています。
こう青年は 話してくれたそうです。
生きていることが当たり前で 感動もない人生をおくって
いますが、その青年の言葉に、今日まで両親をはじめ
自分の知らない多くの人々のお陰で 今 生かされているということに、
改めて気づかせていただきました。
そして、その青年は そのご恩返しをするのに
自分が出来ることは何かというと、
お聴聞することだと思っていますと言わて
また驚ろかさせられたといいます。
ご恩返しに何が出来るのか それはお聴聞することだと思と
その20歳の青年は いうのです。
仏さまのお話を聞かせていただくことが、ご恩返しであると。
言われてみると、お聴聞することで、気づかないでいる
多くのご恩に気づかせていただく、そうすることで
自分がやるべきことが見えてくるのは確かだなあと感じました。
南無阿弥陀仏のお念仏を聞く度に 私に はたらきかけていただく
数々の力に 気づかせいただくことで、この人生は もっともっと
有り難く 素晴らしいものであることに気づくことが出来、
平凡な人生ではなく、当たり前の人生ではなく なんと多くの願いに
包まれて これまで生かされてきたのかを
改めて 味わわせていたくことが出来るのです。
第1613回 卒業式 入学式
令和5年 12月28日~
こんな話をききました。
お通夜は 人生の卒業式、お葬式はお浄土の入学式。
という お話です。
年末の忘年会の帰り ある人は 今年も もう終わりかーあ
この一年早かったなーと 言う人
まもなく新年か 準備をはじめるかあ
春が来て 卒業式。
友だちと別れるのが悲しいと 感傷的になる人があります。
これから、中学校や 高校 大学 あるいは就職と
新たな世界へ旅立っていくのだと、新たな未来を思う人もあります。
これと、同じように、この世で いのちが つきてお別れするのも、
これですべてが終わってしまったのではなく、阿弥陀さまの国
お浄土への旅立ちをするのだと、思える人もあります。
お浄土へ生まれたら、自己中心の私でも、他の人のために頑張るのが
よろこびの利他的な仏さまのはたらきが出来ると喜ぶ人もあります。
死ぬんじゃないよ、生まれていくのだと。
仏さまの国(浄土)に生まれる、いのちの故郷に、
父母がまっていてくれる世界に往くのです。
往き生まれるのです。
生まれるのですから、めでたいことです。
現在でも滋賀や福井のある地域では、お通夜に赤飯を炊くところが
あるそうです。
お通夜は亡き人の死を悼み、ご苦労さまでしたと、
そのご苦労をたたえていく人生の卒業式。
そして、お葬式はお浄土の入学式だというのです。
死んで終わる人生は 寂しいものです。
人生の行き先がはっきりしなければ、いのちの行き先が
見えなければ不安でしかたがありません、真っ暗闇です。
それでは、寂しく虚しく死んでいくしかありません。
念仏者は光の国であるお浄土に生まれるのですから
安心して命終えていけるのです。
懐かしい人と再会出来る、倶会一処のお浄土に
生まれていくのですから、先に往き生まれた方々と
また会うことができるのです。
「待ってたよ」「ご苦労さん」「お帰り」と迎えてもらえる、
いのちの故郷に生まれていくのです。
そう味わうと、歳をとることも喜びとなってくるものです。
明るい未来が 開けてくる、
期待され待たれている私であることを 感じ取れるのです。
第1612回 育ち盛り ~いつも私を~
令和5年 12月21日~
2歳になる外孫が 時々訪ねてきます。
先月 妹が誕生して 誰もが 自分の方を見ていたのが
今は、赤ちゃんの方へも みんなの目が向かっていきます。
母親が赤ちゃんのお世話をするのを、横目でみながら、
ちょっと淋しそうです。
母親を独占して遊んでいるとき、赤ちゃんが泣きだすと
慌てて 赤ちゃんのお世話に向かう母親に あまえて
「抱っこ抱っこ」と だだをこねています。
自分の方を向いてほしい 赤ちゃんよりも自分を大事にしてほしいと
ぐずり出します。
夕方 父親が仕事から帰ってくると、その父親を独占して とても
嬉しそうです。自分だけを抱いて、食事の世話をして、遊んでくれる父親が
一緒なのがとても嬉しく、満足そうに見えます。
これを見ながら 大人になっても 自分のことを一番大事にし、
自分をいつも見守ってくれる人がそばにいると、とても安心なの
だろうと思います。
高齢の方で、歳をとると いろんなものを失っていきますが
歳を取ることによって、はじめて気づく、目覚めることも
あるのですね。とおっしゃる方がありました。
仏教を聞くことで、お聴聞することで、仏さまにお育ていただいて、
70歳で気づくこと、80歳でわかることもあるもので、
自分は 今、子どもの時のように、精神的には
ずうーと 育ち盛りだと感じています。
年を重ねることが、今は喜びとなってきましたと。
南無阿弥陀仏を聞くと ひとりぼっちではなく、 南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏の阿弥陀さまは、 先だった親たちと一緒になって
いつも一緒だよ、ここにいるよ、
南无阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と呼びかけてくださっている。
姿は見えませんが、触ることはできませんが、ここにいるよ
かあさんはここだよと、子どものころに聞いた声を思い出しています。
運動会のときの 応援の声のように、暗闇で怖いとき
大丈夫だよと、声をかけてもらった時のように、
いつも 私を見守っていて 一緒に居てくださるように思えています。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は 私を呼び、応援してくださる
言葉です。
一人で淋しいとき 困ったことがあったとき 嬉しいことがあったとき
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏が聞こえると もう一人ではなく
いつも私を見守ってくださっている方が 一緒であるように
思っていますと。
お話下さった方がありました。
第1611回 何がしあわせ
令和 5年 12月14日~
あるお寺の掲示板に
何のために生まれて 何をして 生きるのか
答えられないなんて そんなのは 嫌だ!
と 書かれていました。
これは 仏教のことばのようにも聞こえますが
もう何十年も前から 子どもたちに 人気のマンガ
アンパンマンの挿入歌の一つ
「アンパンマンのマーチ」一節です。
その歌の出だしは
そうだ うれしいんだ 生きるよろこび
たとえ 胸の傷がいたんでも とあります。
人生は それぞれの受け取り方で大きく違ってくるものです。
何が しあわせで 何が よろこびか
探し求める 一生を みんな送っているのでしょうが、
それが分からずにいる人が 現代は 多いのではないでしょうか。
先輩たちは それを 宗教で確認していたのでしょうが
本物の宗教を知らない人が多い 現代の人々は
一生わからないまま 終わっているのではないでしょうか。
「終活」という言葉が、よく聞かれます。
「子どもに迷惑を かけないように」と、自分の世代で
すべてを解決して終わらせておこうということでしょうが、
一番大事なことは 子どもたちに しあわせとは何かを
確認する方法を しっかりと残え残しておくことでは
ないでしょうか。
いろいろの宗教がありますが、自分の親たちが口にした
南無阿弥陀仏の教えを 子どもたちに、伝え残すことが
父や母、そして祖父母や 多くの先輩が最も喜んでくださる
ことではないでしょうか。
お念仏の人は 死んで終わりではなく お浄土へ生まれ
仏となって この私をずうつと導いてくださっているのです。
それに気づかずにいる私ですが、お聴聞をすると、
仏さまのお話を聞くと、そのことを
繰り返し 繰り返し 教えてくださいます。
それは 先輩たちの呼びかけ、阿弥陀さまと一緒になって
私が進むべき方向を、目標を 生きる目的を知らせていただいて
いるのです。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏を口にし、耳に聞くことで
何のために生まれ 何が幸せかを はっきりと確認し
生きるよろこびを ほんとうのしあわせを 知ることが出来るのです。
第1610回 自分が居なくても
令和 5年 12月7日~
60年前 希望を持って会社に入り、3ヶ月ほど新人研修を受けました。
現場から来て講義してくれる先輩、研修所の教授として、系統だって
専門教育をしてくれる先生、それぞれの経験を精一杯伝えてくれました。
そんな中で、こんな話をした方があります。
「君たちは 自分が居なくてもちゃんと動く組織を作りなさい。
何でも自分でやっていると、そこに塩づけになって
出世できないぞ」
チームにとって、無くてはならない有能な
社員になろうと思っているのに
どうゆう意味だろうかと、疑問に思ったものです。
創造的な能力を発揮するチームは
知識も技能も経験も優れた者が責任者となりますが、
やがて、その技能を超える力を持つ者が現れてきます。
その時に、自分の立場を護ろうとする責任者は
折角育ったその後輩を評価せずに、はじき出してしまうものです。
一方、自分と同じ能力を持つものが育ってきたら
自分がそのチームを譲り、次のチームを作るために
離れていけば、実行力のある素晴らしいチームが
もう一つ新たに出来てくるものです。
人間は自分の立場に固執したいものですが、
そこに安住せずに次を目指せ、それが組織全体を強くする
そう言いたかったのではないかと、今思います。
いつも自分が中心で、周りをリードするのは
心地良いものですが、そこに安住せず、次を目指して
新たな挑戦をしてほしいとの願いだったのでしょう。
お寺には、住職や女房役の坊守さんがいますが、
次の世代が育ってきたとき、どう引き継いでいくのか
前任者は完全に手を引くのではなく、今まで出来なかった
個々のご門徒との接触を密にするなど、新たな仕事を開発して
いくように努力することが大事ではないか。
考えると 阿弥陀さまは、すべての人を救うには、
自分と同じ能力を持つ仏をつぎつぎと新たに作り、
一緒になって人々を、救うはたらきを続けようとされている。
そう考えると、私の出来ることは、まだまだあるはず、
救われていない人が沢山いるのです。阿弥陀さまの仕事は
そして、それを助ける諸仏の仕事は、完結することなく
永遠に続くのです。
第1609回 里帰り 「あら お帰り」
令和 5年 11月30日~
西本願寺の朝のおつとめ、ご晨朝をユーチューブで拝見し、
こんなご法話を聞きました。
あるお寺の掲示板に こんな言葉がありました。
「里に帰れば 親がいるのではない 親が居るところが 里である。」
里とは ふるさとのことで、親というのは、両親はじめ
お世話になった なつかしい方々のことでしょう。
父親が亡くなって、実家には 母親が一人で 住んでいました。
その母が、ひと月ほど入院したことがありました。
その時、実家に帰り、ゴミ出しや掃除をしていて、母のいない実家は
いつもと違って、とても淋しく感じたものです。
コロナ感染症の流行する以前のことで 病院は自由に見舞える時でした。
病室を訪ねると
「ごめんね、忙しいのに、こめんね ごめんね」と、何度も口にしながら
迎えてくれました。
何度か病院を見舞ったある日のこと、母親は穏やかな顔をしていましたが
私の顔を見るなり「あら、お帰り」と声をかけて、笑いながら、
「ここは 病院やったね、おかしかね」と。
「こめんね」の言葉より、「お帰り」の言葉に、こころ和みました。
私は、顔を会わした時だけしか、母のことを思っていませんが、
母の方は いつも私のことを思っていてくれていて、
帰ると、「お帰り」と おやつを出してくれたことを思い出しました。
この母親とおなじように、阿弥陀さまは
私が忘れていても、いつも私のことを心配し、思って
くださっているのだといいます。
母を亡くした今、「お帰り」と迎えてくれるのは、
故郷ではなく、お浄土にいる親たちでしょう。
こちらが忘れていても、私のことを思い、そして、お帰りと
迎えてくれる 母が、父が 祖父母が 待ってくれている
お浄土があることを 有り難く感じています。
「里に帰れば親がいるのではない、親がいるところが里である」
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏とお念仏するとき、
阿弥陀さまは そして、お浄土の親たちは いっしょに
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と呼びかけ
私が元気に活き活きと生活していることを、よろこんで
お浄土で、待っていてくれることでしょう。
第1608回 プレゼンの原語は
令和5年 11月23日~
こんな話をききました。
現在は プレゼンテーション、プレゼンの時代。
相手に正確に情報を伝え、商品を買ってもらったり、
仕事の発注を受けたり、受取り手が、何らかの行動を
起こしてもらえるように、働かけすることが
重要とされています。
プレゼンテーションの語源は英語の「present(プレゼント)」で、
動詞としては、「提示する」「示す」「進呈する」という意味を持ち、
相手に渡して 喜んでもらうもの、相手が幸せになるものを
送ること、伝える言葉であるといいます。
プレゼントは 相手が 欲しかったもの、期待していたもの、
予想もしなかったもので 頂いて喜んでくれるものでないと、
意味がありません。
ですから、プレゼンは、受取り手、聞き手の立場に立って、
分かりやすく伝えることが重要となるのです。
「聞き手の要望をしっかりと認識し、伝えたい内容を
分かりやすく説明する」
「聞き手に自分が望む意思決定を行ってもらうためにも、
それに見合った明確な提案」をするなど配慮が必要です。
浄土真宗のご法話も 一つのプレゼンテーションでしょうが、
はたして聞く相手が喜ぶもの、期待しているものに
なっているでしょうか。
阿弥陀如来さまは、私たち全員に、もれなく プレゼントを
贈っていただいているのです。
それは、ものではなく、南無阿弥陀仏という言葉で、是非
聞いてほしいと、はたらき続けてくださっているのです。
私たちすべてのものを必ず救う、お念仏を口にして、
お浄土へ生まれさせ、仏にしたいと、呼びかけ、はたらきかけて
いただいているのです。
そのことを、みんなにわかるように、お取り次ぎ
しているのが、ご法話です。
お話を聞いている人が、自分の為の贈り物であり、
自分が目当てであり 南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏で、
間違いなく 親も祖父母も行っている、お浄土へ生まれることが
出来ると、喜べるようにとお話しているのです。
聞いていてくださる方に、それが届くように、言葉のプレゼント
お浄土への招待状を配達し、南無阿弥陀仏のお念仏を
お渡しているのが、浄土真宗の
ご法話です。
第1607回 逃げ回る 落ち葉
令和5年 11月16日~
門前の駐車場をアスファルトで舗装し、大型の量販店のように
車と車の間に、U字の二重の白線を引いていただきました。
身近なコンビニのように、たびたび、いつでも、お寺にお参して
いただけるように、高齢者でも、駐車しやすいようにと、
車の間隔も、少し広めにとってもらいました。
これまでの砂地の駐車場ですと、松葉箒で落ち葉も簡単に
集められましたが、真っ黒のアスファルトは、落ち葉やゴミが目立ち、
追われるように
雨の後、紅葉した葉っぱが一面に広がり、小さなホウキで
掃除をしている時、風に吹かれて逃げ回る落ち葉や、
地面に張り付いて、なかなか動こうとしない、
しぶとい濡れ落ち葉などを、掃き集めながら思いました。
わずか10数台の駐車場でもこんなに苦労しているのに、
阿弥陀さまは、ありとあらゆる人々を、一人残さず救いとると
はたらき続けておられるのに、私たちは、逃げ回り、
そっぽを向いて、従わないものばかり、とても大変だろうなあと、
味わいました。
阿弥陀さまだけではなく、私の父母、祖父母、曾祖父母、みんな
そろって南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏と、呼びかけて
いただいているだろうに、忙しい忙しいと聞く耳を持たず、
素知らぬふりをして、逃げ回っていることで、大変、
ご苦労が多いことだろうとつくづく感じます。
今度は、私が仏になって、子どもや孫、多くの人々へ
はたらきかける立場になるということですが、
濡れ落ち葉のように、地面に張り付いてなかなか動かぬものや、
ひらひらと風にあおられて逃げ回る、木の葉のように、
それでも、一つ残さず、一人残さず、救わねばおかぬと
はたらきかけることを、遊ぶように、生きがいをもって
はたらきかける、そんな仏さまにしていただくと思と、
今、ご苦労をかけていることに、申し訳なく
感じています。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 風に吹かれて逃げ回る
落ち葉のように、どうしようもないこの私を、間違いなくお浄土へ
生まれさせて、仏さまにするというはたらきを味わい
有り難く喜ばせていただきたいものです。
第1606回 まだ 間に合う
令和5年 11月 9日~
こんな話を聞きました。
腰が曲がった高齢の住職が、導師を勤められた葬儀でのこと。
朗々としたお勤めの後、振り返り 持っている中啓で、
喪主のご長男さんを指して
「お前さん お前さんは 親孝行したかい」と
おっしゃったといいます。
東京に住む長男は、なかなか郷里へは帰れず、今回も
お父さんが亡くなったとの知らせを受け、慌てて
帰ってこられたのです。
突然の住職の言葉に、喪主の長男さんは、肩を震わせて、
泣きはじめられたそうです。
「お前さん、まだ間に合うぞ、親孝行はな、これからでも
間に合うぞ・・ 大丈夫じゃ。
お前さん、お念仏したことあるかい。
お浄土で 仏になられたお父さんはな、
お前さんが、南無阿弥陀仏を口にしながら、阿弥陀さんと
一緒に生きていく姿をみるのが、一番嬉しいんじゃ。
大丈夫、まだ、親孝行は出来る まにあうぞ 」という
有り難いご法話だったといいます。
親が一番喜んでくれるのは、遠く離れていても
子どもが生きがいをもって、活き活きと生活していることです。
それには、阿弥陀さまの願いを聞いて、願いにかなう
生き方をすること。
お浄土へ生まれた、両親やご先祖は
子どもや孫たちが、活き活きと、喜び多い人生を送ってほしいと
はたらきかけておられるのです。
今からでも、まだ間に合うのです。
南無阿弥陀仏を口に、阿弥陀如来の願いを聞き、
親が喜んでくれる生き方をすること
それが、私に今、出来る親孝行なのです。
第1605回 組織は 人で
令和 5年 11月2日~
2年に一度、組の総代会の会員の追悼法要の会所になりました。
今回は、4人の方々を ご縁とする法要でしたが、こんなお話をしました。
みなさまは、これまで いろいろな組織に所属してこられたことと存じます。
自営業の方もいらっしゃりましょうが、会社であったり、地域、ボランティアや
趣味のグループなど、さまざまな組織の中で活躍され、あるときは責任者だったり、
二番手であったり、実務的な立場であったり、いろいろの経験をお持ちのことと思います。
私も 僧侶 30年以上勤めておりますが、その前に 厚生年金が頂戴できるほど
サラリーマンをしておりました。
たびたび転勤をいたしましたし、さまざまな職場、多様なプロジェクトに所属しましたが、
組織は、まさに人でありまして、その所属メンバーの構成によっては、
いろいろの対応に迫られたことを思い出しております。
普通の組織ですと、管理能力が高い者を もっとも経験豊かな者を
責任者にいたしますが、
お寺の場合は そうはいかないことも多く、世間のことに、どちらかといえば、
精通していない、世間に うといご住職であったり、
あるいは若い住職だったり、こうした責任者を、なんとか支えて、財政面でも、
人を集めることでも、総代の皆さま方、並並ならぬ ご苦労をかけているであろう
と存じます。
これが、営利目的の会社などでしたら、目標の設定や、成果を測ることができますので、
みんなで同じ方向へ向かって進んでいけますので、ある面、運営がやりやすいものでしょうが、
目的が、ご門徒のみなさんをまとめ、念仏繁盛をめざすという、
宗教団体は なかなか難しく、また、昔のようにご門徒のみなさんも、純粋、純朴では
なくなってきましたので、総代のみなさま方に大変ご苦労をかけていると思います。
今回、四人の総代さんの追悼法要ですが、この後、それぞれの方の思い出も
ご披露いただくようですが、どの方も、陰になり日向になり、本当によく
ご尽力いただいた方々ばかりでありました。
ご遺族の皆さまのお宅でも、大黒柱が亡くなられて、とても大変でしょうが、
お寺でも、とても貴重な存在でありまして、おられなくなって
その後を、残された方々がカバーしていただいておりますが、
尚一層ご苦労をおかけしていることでしょう。現役の総代の皆さまも、
本当にありがとうございます。
これからも、皆さまのお力で、寺院を 護持していただけいますよう、
お願いいたします。
とともに、ご遺族の方も、ご主人さま、お父様が がんばっていただいたように、
その意志を受け継いで、お寺のお世話役、ひいては、
総代を
先だった方が、喜んでいただくことではないかと、味わっております。
第1604回 今 困っても
令和 5年 10月26日~
浄土真宗の特徴の一つは、全員で声を出して読経することです。
今から 500年前の蓮如上人が、日常の勤行を誰でも
お勤めしやすいようにと、親鸞聖人のまとめられた
教行信証の中の偈文 正信偈と、ご和讃の繰り読みに
定めていただきました。
それまでは、一日に六回お勤めする六時礼讃という、有り難いものの
すくし難しいお勤めでしたが、みんなが容易におつとめ出来るよう
変更されたのでした。
ご本山では 毎朝六時からご晨朝がつとまり、その様子は
ユーチューブで配信されています。
また、東京の築地本願寺では、朝7時からのお勤めも
ユーチューブで見ることができます。
ご本山では、まず阿弥陀堂、続いて御影堂での
お勤めがあり、6時45分ごろから
全国各地の布教使さんによる、短いご法話もあります。
築地本願寺の場合は、7時半ごろからご法話があります。
北海道からこられた若い布教使さんが、
こんなお話をされました。
今日は 今から50年前の、日本で4人目のノーペル賞を
江口玲於奈さんが受賞された日です。
コンピュータなどで使われる半導体、ダイオードの
研究者だそうです。
子どもの頃から大変優秀な方でしたが、なぜか中学受験に
失敗し、高等小学校へ進学、それから再度、中学校を
受験されたそうです。
その一年間に、外国から来た先生にであい、幅広いものの
見方と、英語を学ぶことが出来たことで、アメリカでの研究など、
将来大きく役だったと、後に語っておられます。
研究でも、仲間が失敗した沢山のデータを、再確認して
いる中で、たまたま大発見をし、それでノーベル賞の
受賞につながったと。
親鸞聖人の人生も、波瀾万丈でした。
伝統的な比叡山を降り、法然聖人の元で学ばれていた時、
念仏禁止令によって、遠く越後に流罪になられました。
この大きな災難も、お念仏教えが広がる尊いご縁だったと
味わっておられます。
自分の思い通りになることだけを期待して、私たちは生きていますが、
今日一日、困ったことや悔しいこと悲しいことが起こったとしても
一つも無駄なことはなく、みんな有り難い尊いご縁だったと
喜べる そんな一日でありたいものですね。と
第1603回 つれていくぞの 親の呼び声
令和 5年 10月19日~
【仏教のことば】
「生苦」は「生まれる苦」と言いましたが、
…「誕生」がどうして苦なのでしょうか。
仏典は主に二つの理由を挙げます。まず、
①
「誕生は後の苦(老・病・死など)の原因となるから」です。
もう一つは、②「誕生はそれ自体、苦痛を伴うから」です
(岡本健資『季刊せいてん』124号P58)
【仏教のことば】
「〈わかる〉ではなく〈聞く〉である」と聞いても、
それを聞かずにわかろうとしてしまうのが「わからない!」
の理由です。
(石田智秀『季刊せいてん』126号特集「信心がわからない」P48)
9月13日
【仏教のことば】
われ称(とな)え われ聞くなれど 南無阿弥陀
つれてゆくぞの 親のよびごえ
【仏教のことば】
辛いとき、悲しいとき、嫌なとき、嬉しいとき、
あらゆるときに「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と
念仏するならば、それによって私たちは真実に
呼び覚まされていく。
絶えず呼び覚ましを私たちにもたらす声が念仏である
(梯實圓『浄土教学の諸問題』上P71)
【仏教のことば】
あらゆる悪と人々を救ふ世界を見出したのが浄土真宗である
…仏を信じたとて、病気が回復したり、貧乏が金が
儲かつたりするやうな利益はない。
されど如何なる境遇にありても「安らかさ」と
「ゆたかさ」とが恵まれてある。 (梅原真隆『人生と宗教』P18)
9月16日
【仏教のことば】
経典にも「仏心とは、大慈悲心これなり」と出ているように、
「慈悲の心」とは、一切衆生を平等無差別に救わずには
おかないという、末通った深い愛情ひとすじの「仏の心」である。
(花岡大学『親鸞へのひとすじの道』P208)
第1602回 難しい道と 易しい道
令和5年 10月12日~
西本願寺の総合研究所からの【仏教のことば】の紹介です。
【仏教のことば】
仏教の重要な目的の一つは自己を知ることだとよく言われます。
まさにそのとおりであって、仏陀とは自己を知り尽くされた人だと
言ってもよいでしょう。
(徳永道雄(一道)『観無量寿経を読む』P42) 2023年9月1日配信
【仏教のことば】
布教使の方によく言うのですが、自分の考えを言った時に、
相手が共鳴してくれたら、それは…真実であることを証明して
くれているのです。
承認してもらえることが有り難いのですから、
「教えてやるなんて思ったら大間違いだ」と言うのです。
(梯 實圓『季刊せいてん』106号P39)9月2日配信
【仏教のことば】
「自分が信心を得てもいないのに、人に信心を得なさいと勧めるのは、
自分は何もものを持たないでいて、人にものを与えようとするような
ものである。これでは人が承知するはずがない」と、蓮如上人は
お示しになった
(『蓮如上人御一代記聞書(現代語版)』P66)9月3日
【仏教のことば】
仏法には、はかり知れないほど多くの教えがある。
たとえば、世の中に難しい道と易しい道とがあり、陸路を
歩んでいくのは苦しいが、水路を船に乗って渡るのは
楽しいようなものである。
菩薩の道も同じであり、修行に努め励む道もあれば、
仏の教えを信じるという易行(いぎょう)によって
速やかに不退転の位に至る道もある。
(『十住毘婆沙論 浄土論(現代語版)』P6)9月4日
【仏教のことば】
私たちは「南無阿弥陀仏」という名号を通して、間違いなく
お救いくださる阿弥陀さまと、いまここで出遇(あ)って
いくのです。ですからお念仏を称えながら阿弥陀さまを
探す必要はありません。
(赤井智顕『なぜ?どうして?浄土真宗の教学相談』P9)9月5日
【仏教のことば】
私が疑わないことに決め、私が信心する。
その私が残っている事が問題なのです。
…深く信ずるとは…如来回向の信心のことです。
自分が信心によって救いを掴もうとする立場から、この身
このままを如来に摂取されて行く立場に転換されることです。
(井上啓一『真宗の法話』P23)9月8日
第1601回 溺れる人がいれば
令和5年 10月5日~
今回も 本山総合研究所から届けられた言葉です。
【仏教のことば】
人びとは、ややもすると他力の救いということを、他人をあてにし、
自分は何もしないでなまけていることのように誤解するのですが、
決してそうではありません。
他力とは仏の願力をいうのであって、仏力を主体として、真実に
生きることをいうのであります。
(『山本仏骨法話集』2P30)· 2023年8月25日配信
【仏教のことば】
他力の教えは、自分で悟りを開けないもののための仏道であり、
そのための仏が阿弥陀仏なのです。
川で溺れている人と、土手にいる人とがいれば、溺れている人を
救いますよね。(釈 徹宗『歎異抄 救いのことば』P72)
【仏教のことば】
懺悔は単なる道徳的反省の心ではない。
それは光によって映し出された相であることにおいて、
そこにはすでに光の中にあったという法悦(ホウエツ)と、しかも
常にその光に背きつつあるものという慚愧(ザンギ)の心とが
交錯するものである。(村上速水『親鸞読本』P182) 8月29日
【仏教のことば】
唯円房があやまっている人たちを、…打ち破ってしまえば
それでいいのだというような裁きの態度でかいたものでなく、
…そのあやまれるものを抱きしめて歎かずにおれないところに
「歎異抄」全体に流れている持ち味が知られると思うのであります。
(山本仏骨『歎異抄のこころ』P22)8月30日
【仏教のことば】
今、諸君たちは現実的に宗教を必要としないかもしれない。
しかし今、君たちは宗教に対して決して無関心であってはならない。
何が正しい宗教であるか、また何が誤った宗教であるかを
見極める目を今の時期に養っておかねばならない。
(淺田正博『私の歩んだ仏の道』P32) 8月31日
第1600回 私の生活の中に
令和 5年9月28日~
ご本山 総合研究所からの【仏教のことば】の紹介です。
【仏教のことば】
お浄土に往かれたわが父や母は、往きっぱなしではありません。
お浄土より娑婆に還り来て、私たちをみまもり、私たちが
お念仏申すところ、共にお念仏を唱和して、私たちによびかけ、
阿弥陀仏の大悲をあおがれているのであります。
(普賢晃壽『阿弥陀仏の救い―人生の帰趨―』P233)
2023年8月15日
浄土真宗の特徴は 往相廻向 還相回向の教えです。
正信偈の意訳には、
蓮華の国にうまれては 真如のさとりひらきてぞ
生死の園にかえりきて まよえる人を救うなり とあります。
どうか、お念仏の教えに出会ってくれ、この教えに遇えば、
これから迎える老病死の苦しみも、素直に受け入れることができ、
生きがいある人生を味わえますよと、はたらきかけて
くださっているのです。
【仏教のことば】
私達は平素から、見えるものだけに夢中になって、
見えないものの恐ろしさや、有難さを忘れているのでは
ありますまいか。 (井上啓一『御文章の味わい』P53)
· 8月16日
親や周りの人の思い、多くの人々のはたらき、仏さまのはたらき
見えないものを、感じられるように育てられると、この人生は
有り難く、すばらしいものへと変化するのですよと。
【仏教のことば】
如来の心に触れ、これまで如来さまを泣かせて来たことに気付いたのなら、
「もっと泣かせてやろう」と思うでしょうか。そうではなく、
「もうこれ以上、泣かせることはすまい」と思うはずです。
(「悪人正機」について)(満井秀城『季刊せいてん』110号P55)·
8月19日
··
【仏教のことば】
阿弥陀仏は私の心に信心の喜びを与えてくださるばかりでなく、
更に、私の寿命のある限りは称名念仏の声として、
私の生活の中にいつでもどこでも現われましょうという
お慈悲から「乃至十念」の称名をお誓いくださった
ものであると味わわれます
(灘本愛慈『やさしい安心論題の話』P177)
第1599回 子どもや孫の将来を思うと
令和5年 9月21日~
ご門徒のお宅へお参りし、自動車を止めた途端
吠え出す犬がいます。そしてお勤めの間中 泣き止まず
吠え続ける犬がいます。
一方で、必ず玄関まで出迎え、歓迎の挨拶を一通りすまし
お勤めを始めると、静かになり、お勤めが終わると、
また近づいてきて、触ってほしいと催促する利口な犬もいます。
近頃、うるさい犬が増えたのは、犬の種類や性質が
変わったのかと思っていましたが、飼い主が
ただ甘やかすだけなのではないかと聞かされました。
そう考えると、人間の子どもも、少し前までは、
多くの人の前では余り騒がず、おとなしくしていたように思います。
近頃は、小さな子どもが法要に参加すると、走りまわり、騒ぎ出し、
保護者が耐えかねて、外に連れ出すケースをよく見ます。
子どもや ワンちゃんが変わったのではなく、親が、飼い主が
甘やかしてばかりいることが原因ではないかと思われます。
核家族化が進み、2世代3世代で生活する家庭はごく希で、
年寄りたちが口をだすチャンスもなくなりました。
怖いおじちゃん、うるさいおばちゃんの存在もなくなり、
友だちのような優しい祖父母、両親、おじさんおばちゃん
だけになったようです。
子どもや孫の将来を考えると、心を鬼にして、言うべきことを
ちゃんと言い、嫌われても、うるさがられても、大人の役割を
果たすべきだとは思ものの、なかなかそうはいかないものです。
ご法事を勤めながら、仏事は、自分が生きている間に、子どもや
孫に言えることが出来なかったことを、自分が亡くなった後に、
仏教のお話を通して、人間として最も大切なことを、代々伝えて
きたのではないかと、思います。
子どもの将来を考えると、仏さまの事だけは、ちゃんとしてほしいと、
伝えておくことが大事だと思います。
子どもに迷惑をかけないようにと、葬儀も法事も、墓地も仏壇も
無くしてしまう人いますが、自分に変わって、人間に必要なこと、
やるべきこと、そして、老病死を恐れず、受け入れていく力を、
伝えてきた伝統が、仏事、法事だったのではないか。
それを護り、繰り返し伝えていくことが、残された
子や孫にとっては有り難く、大事なことだろうと、痛感しています。
伝承してきたことを、取りやめることで、自己本位で
わがままな生活、それは、心豊かな生き方には、決して
つながらないと感じます。
第1598回 さとりの身となって
令和5年 9月14日~
今回も 本願寺派総合研究所からの【仏教のことば】の紹介です。
【仏教のことば】
念仏の行者とは、わたしを念仏の行者たらしめている
本願力の不思議を信知し、感動しているもののことである。
(梯
實圓『教行信証の宗教構造』P72)·
2023年8月7日
【仏教のことば】
「この源空(法然聖人)の信心も、阿弥陀さまからいただいた
信心じゃ。そして、善信さん(親鸞聖人)の信心も、
阿弥陀さまからいただいた信心。だったらまったく同じ、
一つと言うべきでしょうな…」
(『いつでも歎異抄』P71「後序」意訳) 2023年8月8日
毎年のご正忌報恩講で 親鸞聖人ご伝絵をご紹介していますが、
法然聖人のところで、先輩同僚と 信心についての論争のところです。
自分の努力で起こす信心ではなく、阿弥陀さまからいただいた信心
そこで、師匠の法然聖人の信心も、お弟子の信心もみな一緒のくだりです。
【仏教のことば】
ほんとうの宗教はこの自分の中に最も危ないものを
蔵していることが知らされることであります。
浄土真宗の御念仏とは正しくこの私の中に鬼を
見出すことといえます。
危ないことを危ないと知らされると、危ないことに
気をつけることとなります。
(稲城選惠『人生の道標』P158)·
2023年8月9日
【仏教のことば】
浄土真宗の仏事は、阿弥陀仏のお徳を讃えるとともに、
亡き人を、阿弥陀仏と同じさとりを開かれた仏さまとして敬い、
そのお徳を讃えるということでもあるのです。
追善供養ではないからといって、亡き人への思いを
軽んじるということではありません。
『季刊せいてん』115号P52) ·
2023年8月11日
【仏教のことば】
仏の国に往き生まれていった懐かしい人たち。
仏のはたらきとなって、いつも私とともにあり、
私をみまもっていてくださる。このお盆を縁として、
すでに仏となられた方々のご恩をよろこび念仏申すばかりである。
(『拝読 浄土真宗のみ教え』P53) ·
2023年8月12日
【仏教のことば】
「…私が死んだらお浄土へまいらせていただきます。
…けっして遠いところへ離れていくのでもなければ、
子供と別れていくのでもありません。
ほんとうのさとりの身となって永遠に子供のうえに
生きることができるのです…」(山本和上のお母様の言葉)
(山本仏骨『親鸞人生論』P222) ·
2023年8月14日
第1597回 さるべき業縁のもよほさば
令和5年 9月7日~
今回もご本山総合研究所からの【仏教のことば】のご紹介です。
どの言葉を見ても、お念仏の教えに遇えた人の有り難い言葉です。
【仏教のことば】
人間というのは自分が思っているほど一つに決っていない。
固定的な善人、悪人というようなあり方にはなっていない。
…状況や環境次第で、この私自身がどちらにでもころぶのである。
(相馬一意『本物に出あう』P138)
新聞やテレビで見る容疑者を見て、悪人と批判していますが、
一歩間違えば 誰もが同じ過ちを犯すのかもしれません。
【仏教のことば】
経典を読む(読誦)ということは、本来、清らかな悟りの世界から
ひびいてくる仏陀のよび声を聞くことであり、それによって
真実の何たるかにめざめしめられることである。
(梯實圓『浄土教学の諸問題』下P278)
【仏教のことば】
よく、成仏というと死ぬことだと思われていますが、それは違います。
「仏に成る」ことを成仏と言うのです。
(松﨑智海 『鬼滅の刃』で学ぶはじめての仏教 P22)
【仏教のことば】
必ず浄土に往生する人生を生きるということは、尊い命を
生きるということです。
そこには感謝と喜びをもって生きることができる、これこそが
浄土のこの世におけるはたらきといってよい、私はそう思います。
(勧学寮編『今、浄土を考える』P70)
【仏教のことば】
諸行無常という言葉を、知らない方はいないと思います。…
しかし、それは知識として知っているだけではないでしょうか。
本当にこの世は諸行無常なのだということの納得がなかなかできないのです。
(淺田恵真『お念仏の真実に気づく』P91)
第1596回 疑り深い私のために
令和5年 8月31日~
私たちは 疑い深い性質を持っています。
常識の範疇だと素直に受け入れるものの、常識を超えていると
そんな馬鹿な だまされるものかと、疑い拒否します。
そんな私を 何とか信じさせようと、
お釈迦様は いろいろと苦心して 教えを説いて
いただいています。
仏説無量寿経の中には、
これまで沢山の仏さまが、この世に出て多くの人々を
救っていただいたこと、そして世自在王仏という
仏さまの時代に 一人の国王が、すべての人々を一人残らず
救いたいとの大きな願いを建て、
その理想の国をつくるために 多くの仏さまの世界を
手本にしたいと、さまざまな仏さまの世界を見せてもらったこと。
その数が 10や20ではなく、210億もの仏さまの国を
見せてもらい、その中から特に優れたものを選び取るのではなく、
疑い深い 私たちのために、五劫という長い長い宇宙的時間
考えに、考えて、48項目の設計図を建て、その完成のために
また宇宙的長い間修行して これまでにない最も優れた
お浄土が完成したと説かれています。
その設計図の17番目には すべての仏さまが、
自分(阿弥陀仏)のことを、誉め讃えるような 最もすぐれた
はたらきができる仏に成りたいというのです。
過去の仏さま 現在の仏さま すべての仏さまが
実現できなかった、努力出来る人も出来ない人も、すべての人を、
「南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏」の名号を口に
するものを 自分の国・お浄土へ生まれさせ 仏にしたいと。
ですから、私がご縁を頂いて 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と
お念仏するとき、もう仏さまと同じ はたらきをしている
ことになります。
阿弥陀さまの偉大さ、そのはたらきが、分かっていなくても
お念仏する私は もう仏さまと同じ阿弥陀仏を讃嘆する
はたらきをしていることになるのです。
疑り深い私がどう思と お念仏する時は、もう
仏さまと同じように 阿弥陀さまを讃嘆するはたらきを
しているのです。
ですから、今は 悩み多い人間ですが、やがて いのち終われば
お浄土に生まれ 引き続き 阿弥陀さまを讃嘆する仏さまの
はたらきをさせていただくのです。
もう 今は 仏さまの仲間なのです。
第1595回 物差しを変える
令和5年 8月24日~
今回も本願寺派の総合研究所のツイッター【仏教のことば】のご紹介です。
【仏教のことば】
信心を得る以前は いわゆる常識という物差しで社会を生きてきました。
しかし信心を得るというのは、いままでの常識の物差しを捨てて、
法という新しい物差しの世界へ生まれ変わるのであります。
(霊山勝海『聖典セミナー親鸞聖人御消息』P86)
配信 · 2023年7月26日
私たちは 学校で長年教育を受け、社会での経験を元にした常識で
今まで生きてきました。
しかし、学校教育では ○か×か、採点できることが中心であり
社会では 損得勘定を基本にして、いかに上手に生き抜くか、
老病死を嫌い否定する、価値観で生きてきました。
しかし、現代の科学ではなかなか評価、証明出来にくい、
先輩たちが受け継いできた、大人の智慧、仏法があることを
知らないままでこれまで生きて来たようです。
キリスト教を基本とした西洋的な考え方、ものの見方を
現代人は常識として生きているようです。
そうした、世間の常識を超えた価値観が日本には存在していたこと、
そうした物差しを知り、その世界を体験し、生きていくこと、
それが仏法という新しい物差しの世界に生まれ変わることなのでしょう。
すべてのものを救いたいという仏さまの願い、はたらきを
繰り返し聞き、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を口にし、耳に聞き
どこへ向かうのか、それはお浄土へ向かって力強く生きていく
世界があることを、教えていただいているのです。
【仏教のことば】
仏道を歩むとは…人間の逃れられない根源的な苦悩を乗り越えていく道を
目指すのであり、仏陀の説かれる「苦悩を除く法」とは、「生老病死」の
苦悩を除く法なのである。
親鸞聖人が目指された仏道も、生老病死の苦悩を乗り越えていく道であった。
(勧学寮篇『親鸞聖人の教え』P14)
医学や科学が進み、あたかもこれが万能であるとの誤解があります。
「生老病死」の苦悩を除くには、薬を飲む、手術を受けるなど、
外側からの何らかの治療を受けることでしか、解決法は
ないと信じこんでいます。
しかし、先輩たちは、科学だけに頼るのではなく、仏法を通して
内側からの、精神的な解決法を受け継いできたのです。
そうした世界があることを 教えていただいているのです。
【仏教のことば】
死の問題の解決こそ、同時に生の問題の解決でもあるわけで、
ほんとうの幸福とは、お念仏によって生死の問題を超えさせて
いただく以外にはないと思うのです。
(村上速水『道をたずねて』P27)
ともありました。
第1594回 受け継がれていくもの
令和5年 8月17日~
お盆の間 境内にあるお墓に 子ども連れの見知らぬ若い家族の姿を
多く見受けました。
本堂にお参りする家族、直接お墓にお参りする家族さまざまですが、
年配者が一緒ではなく、自分たちでお参りしているのを見ると、
子どものころに大人に連れられて 参拝していた世代が、
夏休みに帰省して子ども連れでお参りしているのだろうと思います。
大人と一緒に 本堂にお参りしていた家族は、本堂へ上がり
お墓だけの家族はお墓だけ帰る、こうして次の世代に受け継がれて
いくのだろうと、感じています。
さて、浄土真宗本願寺派(西本願寺)総合研究所【公式】から
送られてくる【仏教のことば】に
こんな内容がありました。
【仏教のことば】
わが身の善悪にとらわれて、これで助かるだろうとか、
こんなことでは救われまいと思いわずらうことを、
自力のはからいというのです。
そのはからいをやめて「必ず救う」のおおせ一つをあおいで、
おおせに安んずることを安心とも信心ともいうのです。
(梯實圓『妙好人のことば』P226) ·
2023年7月21日配信
【仏教のことば】
仏教というのは世界の見方を変えてくれる教え…
その教えに一度出会うと、出会う前のものの見方に戻ることはありません。
毎日、大量に消費され廃棄されていく情報とは違う、
出会うとその人の人生をも変えてしまう…それが「仏教」です
(松﨑智海 『鬼滅の刃』で学ぶはじめての仏教 P4)
·
2023年7月23日配信
【仏教のことば】
仏教は道徳ではありません。
私の窺い知る(うかがいしる)ことのできない「仏の世界」を
学ぶのです。道徳と同じレベルで学べば大きな誤りを犯します。
(淺田正博『生かされて生きる―どうして人を殺してはいけないのですか?―』P28)
2023年7月24日配信
【仏教のことば】
本堂においては、すべて本尊を中心にして語られる。
前後、左右というのも、本尊の前後、左右…であって、
私から向って左右ということではない。…あらゆることがらを
自己を中心として考え、行動している日常的な意識が
本
7月25日配信
第1593回 この世に無駄なし
令和5年 8月10日~
毎日送られてくる 【仏教のことば】 そこに こんなことばが
ありました。
【仏教のことば】
「摂取不捨(せっしゅふしゃ)」
この世に無駄なしということなのですね
(鈴木章子『癌告知のあとで―なんでもないことが、こんなにうれしい』P134)
2023年7月17日配信
北海道のお寺の坊守さんで 癌で亡くなられた鈴木章子さんの残されたことばです。
(※摂取不捨=摂(おさ)め取って捨てずという、阿弥陀如来の救い)のことですが、
私たちは 役にたつもの、有益なものだけが 有り難く感じていますが、
この世には 何一つ無駄なことはなく、私たちが忌み嫌っている、老病死も
みんな平等に訪れてくるもの、それをどう捉えることができるかで
人生は 大きく変わってくるものでしょう。
限られたいのち、毎日毎日をどう味わって生きるかで 私の人生は素晴らしいものに
転じられていくのです。
長い命だけが素晴らしいのではなく、健康だけが素晴らしいのではなく、
何一つ 無駄なことはない、ひとつひとつ 味わい深い毎日を
送らせていただきたいものです。
またこんなことばも 送られてきました。
【仏教のことば】
「自由」とは何でしょうか。多くの人は、「自分の思い通りになること」と
考えるでしょう。しかし、仏教では、「自分の思い通り」とは、欲望という
煩悩に支配された「不自由」に過ぎないと見ます。
(『いつでも歎異抄』P51)
【仏教のことば】
慈悲深い両親だからといって、その両親の前で悪事を行って、はたして喜ぶだろうか。
嘆くに違いなく、それでも見捨てないだろう。
また、大切に思ってくれても、悪行については許せない思いのはずだ。
如来の思いも、まったく同じである。(法然聖人の言葉)
(『季刊せいてん』110号P54)
第1592回 仏法は 聴くべきもの
令和5年 8月3日~
毎日 ご本山の総合研究所からツイッターで送られてくる
「仏教のことば」その中に こんなことばが ありました。
【仏教のことば】
世界はこんなに苦しいけれど、解決していく道はきっとある。
月並みな言葉ではありますが、仏の教えというのは、
この苦しい世界での希望なのです。
(松﨑智海
『鬼滅の刃』で学ぶはじめての仏教 P52)
仏教は 生老病死の苦しみを解決するために説かれたとも言われます。
生きるということは 苦しみの連続 その苦しみを解決するために
お釈迦さまが説かれ 多くの先輩たちが その味わいを
具体的に説き 伝えていただいたものが 仏の教えなのでしょう。
先輩が残していただいた、折角の教えに 気づかないでいることは
もったいないことです。
浄土真宗は お聴聞 その教えを 聞くことが大事だといわれます。
【仏教のことば】
「仏法は毛孔(けあな)から入るものである」ならば、
わたしの心身をあげて聴くべきものであろう。
わたしの生活行動を通して、教えのまことを確認する
という意味を含むであろう。
(村上速水『親鸞教義の誤解と理解』P112)
【仏教のことば】
「本尊」とは帰依尊重する本仏をいう。
この本尊が教法の根源であり、また礼拝の対象である。
(『浄土真宗本願寺派「宗制」解説』P43)
【仏教のことば】
「必ずあなたを救いとる」という如来の本願は、
煩悩の闇に惑う人生の大いなる灯火(ともしび)となる。
この灯火をたよりとする時、「何のために生きているのか」
「死んだらどうなるのか」、この問いに確かな答えが与えられる。
(『拝読
浄土真宗のみ教え』P3)
【仏教のことば】毎回 短いことばですが、お念仏の教えを
味わうには 誠に貴重なことばです。
ユーチューブで全体を
 妙念寺
妙念寺
電話法話一覧表へ (平成9年)~
掲載者 妙念寺住職 藤本 誠
電話法話一覧表
| 第1550回 しあわせな人生 | 10月13日~ |
| 第1551回 かけがえのない君へ | 10月20日~ |
| 第1552回 朝のどまんなかに | 10月27日~ |
| 第1553回 片道か 往復か | 11月 3日~ |
| 第1554回 誓いと 願い | 11月10日~ |
| 第1555回 言葉で 救う | 11月17日~ |
| 第1556回 人間にわかる言葉で | 11月24日~ |
| 第1557回 お念仏は 公の言葉 | 12月 1日~ |
| 第1558回 伝え 伝えて | 12月 8日~ |
| 第1559回 お仏壇の前で | 12月15日~ |
| 第1560回 何事も お念仏の助縁 | 12月22日~ |
| 第1561回 遇い難くして 今遇う | 12月29日~ |
| 第1648回 まだ仕事が残っています | 8月29日~ |
| 第1649回 あんたが悪い | 9月 5日~ |
| 第1650回 自分の姿を鏡で見る | 9月12日~ |
| 第1651回 はじめての道 はじめての人生 | 9月19日~ |
| 第1652回 法座 & フォークソング | 9月26日~ |
| 第1653回 墓友 ~この世からの仲間~ | 10月 3日~ |
| 第1654回 ハチドリのひとしずく | 10月10日~ |
| 第1655回 後になって 気づく | 10月17日~ |
| 第1656回 救われる私 | 10月24日~ |
| 第1657回 私が仏になる | 10月31日~ |
| 第1658回 私は 私でよかった | 11月 7日~ |
| 第1659回 願いを知る | 11月14日~ |
| 第1660回 親の足を洗う | 11月21日~ |
| 第1661回 周りに迷惑をかけて | 11月28日~ |
| 第1662回 ハッピーバースデーだね | 12月 5日~ |
| 第1663回 絵本の読み聞かせ | 12月12日~ |
| 第1664回 良いことをするときには | 12月19日~ |
| 第1665回 浄土真宗は 有り難いですね | 12月26日~ |
| 令和 7年 |
| 第1666回 私の宝ものです | 1月 2日~ |
| 第1667回 これもご報謝 | 1月 9日~ |
| 第1668回 世間か 娑婆か | 1月16日~ |
| 第1669回 マルテンを見ると | 1月23日~ |
| 第1670回 大丈夫 大丈夫 順調 順調 | 1月30日~ |
| 第1671回 良かったね 母さん | 2月 6日~ |
| 第1672回 今 ここに 生きる | 2月13日~ |
| 第1673回 鏡で見ると | 2月20日~ |
| 第1674回 アリガトウ | 2月27日~ |
| 第1675回 対治 と 同治 | 3月 6日~ |
| 第1676回 籠を水に | 3月13日~ |
| 第1677回 いつもいっしょ | 3月20日~ |
| 第1678回 私と 仏さま | 3月27日~ |
| 第1679回 自分自身を 採点すると | 4月 3日~ |
| 第1680回 相続していますか | 4月10日~ |
| 第1681回 知恩報徳 | 4月17日~ |
| 第1682回 実を結ぶために | 4月26日~ |
| 第1683回 よいいっしょ 良い一生 | 5月 1日~ |
| 第1684回 何が起ころうと 大丈夫 | 5月8日~ |
| 第1685回 グッドタイミング | 5月15日~ |
| 第1686回 期待され 待たれている私 | 5月22日~ |
| 第1687回 因果応報 自業自得 | 5月29日~ |
| 第1688回 言えば 良かった | 6月 5日~ |
| 第1689回 呼びかけ続ける | 6月12日~ |
| 第1690回 安心して堂々と生きる | 6月19日~ |
| 第1691回 尊いご縁で | 6月26日~ |
| 第1692回 ヨシ 間違いなし | 7月3日~ |
| 第1693回 水道の蛇口 電灯のたま | 7月10日~ |
| 第1694回 未来を開く ことば | 7月17日~ |
| 第1695回 感じる力 知る力 | 7月24日~ |
| 第1696回 無駄な いのちは 一つもない | 7月31日~ |
| 第1697回 見ていない 見えていない世界 | 8月7日~ |
| 第1698回 有り難い方の お通夜で | 8月14日~ |
| 第1699回 スパイスをきかす人生 | 8月21日~ |
| 第1700回 感謝・喜びの効果 | 8月28日~ |
| 第1701回 見る 感じる力 | 9月4日~ |
| 第1702回 誰で皆 86,400 | 9月11日~ |
| 第1703回 あなたは どち ら | 9月18日~ |
| 第1704回 世界中が雨の日も | 9月25日~ |
| 第1705回 みんな一人残らず | 10月 2日~ |
| 第1706回 無税の相続 | 10月 9日~ |
| 第1707回 裏のはたらき | 10月16日~ |
| 第1708回 愚者になりて 往生す | 10月23日~ |
| 第1709回 おまかせ おまかせ | 10月30日~ |
| 第1710回 | |
| 第1711回 |
 妙念寺
妙念寺
記載者 住職 藤本 誠
| 私も一言(伝言板) | このホームページトップへ |