��54��ɖ{���͈�w��w�p���F
����21�N6��5������6��7���܂ʼn��l�s�p�V�t�B�R���l�ŊJ�Â���A��A��Ȃ��܂�N���j�b�N���畛�@���Ɠ��͎��E��2�l���Q�����A�����܂����B�ȉ��ɕ��ڂ��܂��B
���@���@�؉����Y
�V���|�W�E���@�@�w�@���͊��҂́@good�@longevity ���߂����āx
�@�@�@ longevity�@�@�Ƃ́A���ǂ������̉����̂��Ƃł���B
�@�@1.�����Ǘ���Longevity
���͊��҂̎����͐S�s�S�A�����ǁA�]���Ǐ�Q�A������ᇂ̏��ł���B�����͍����Ă��Ⴍ�Ă������\��͗ǂ��Ȃ��B�������͂܂��h���C�E�F�C�g�������A�������Ug�Ƃ���B�~���ڕW�A�ǂ̍~���܂𓊗^���邩�ɂ��ẮA�m���ȃG�r�f���X�͂Ȃ��B
2.���͊��҂ɂ������ӊǗ���longevity
���A�a���҂ŐS���ǃC�x���g�̔��ǃ��X�N�͍����A���S���͂Q�{�ł���B���R���X�e���[����LDH�R���X�e���[���������ƐS�؍[�ǂ̔��ǃ��X�N�������B�A���u�~�����Ⴂ�ƐS�؍[�ǁA�S�s�S�ɂ�鎀�S���������BBMI�Ⴂ�Ǝ��S���������B�r�^�~��D���^�Ŏ��S����������B
3.�h�{��Ԃ̈ێ���Good�@longevity
���͊��҂ł́A�h�{�ێ�̈ێ��A���ǂ̗}���A�\���ȓ��͂Ȃǂɂ���ĉh�{��Ԃ�ǍD�ɕۂ��Ƃ�Good longevity�Ɍq����B
4.Longevity��ړI�Ƃ����S�����ǂ̎���
���͊��҂̎��S�����̖�R�U���͐S�����ł���B���É\�Ȋ����������̑����f�f�Ǝ��Â����v�ł���B
5.�����t�s�S����ѓ��͐f�Â��AQOL���l�i��p�j�A���ԁA�p�x�̎��ŕ]������
�l���̍���⎡�Â̐i���A���z���ɔ�����Ô�̍����Ǝ����̗L�����������鎞��ɂ����āA���͈�Â̕]���͒P�Ȃ�L�����̃G�r�f���X�����ł͕s�\���ł���AQOL���l�i��p�j���ԁA�p�x�̎����l�����đ��p�I�ɍs���K�v������B
6.��J��Longevity
��J�͒������͊��҂ɕp�ɂɂ݂���Ǐ�̂ЂƂł���B�u�ɁA���M�Ɣ�J�͎O�吶�̃A���[���ł���B�t�s�S�͎����֘A��J�̑�\�I���f���ł���A�����͑��ʂł���B
�R���Z���T�X�J���t�@�����X�w���͊��҂ɂ�����S���Ǎ����ǂ̕]���Ǝ��ÂɊւ���K�C�h���C���x 1.�����d����
�ۑ�������i�W������ԂŌp�����邽�߁A���͊��҂�.�����d���ǂ͏d�x�ł���B���A�a���҂͔A�a���҂�蓮���d���ǂ��d�x�ł���BLDL-C���l�AHDL-C��l�ATG���l�ŐS�؏�Q�������Ȃ�B���ǐΊD���̗\�h�ɂ̓K���V�E���ƃ����̃R���g���[�����d�v�ł���B
2.�����ُ�
���͎������A�ƒ댌�����܂߂��]�����K�v�ł���B���͎��̋}�Ȍ����ቺ�ⓧ�͏I�����̋N�����ጌ���͗\��s�ǂł���B�܂��́A�h���C�E�F�C�g�̓K�����Ɖ����̐������K�v�ł���B�@�@�@�@
3.�S�s�S
���͊��҂̎����̂S���̂P�͐S�s�S�ł���B��㏞���S�s�S�̃C�x���g�́A�J��Ԃ������ቺ�A�h���C�E�F�C�g�����ɔ������Ȃ��A�K���h���C�E�F�C�g�̒B������Ȃǂł���B
4.�������S����
���njS�؋����̃X�N���[�j���O���K�v�ł���B�}���S�؍[�ǂ̐f�f�͏Ǐ�A�S�d�}�����Ɛ����w�����ł���B���͊��҂ł͋}���S�؍[�ǂ̐f�f�͓���B
5.�S���ˑR���ƕs����
���͊��҂ł͐S���ˑR����s�����̔��Ǖp�x�������B���Â��ׂ��v�����s�����A�S�[�ד��^�e���ƍ��x�������s����������B�v�����s�����ɂ͐S���ד��^�e����S���p��������B
6.�]���Ǐ�Q
���͊��҂ł͔]�o���������B�]�o���͏d�ǗႪ�����A�]�����j��͗\��s�ǂł���B�}��������ϋɓI�����Ǘ�������B�]�[�ǂ͕a�^���ނɉ��������Â�����B
7.������������
���͂��̂��̂��������������̃��X�N�t�@�N�^�[�ł���B���Ǐ������A�Ԍ���s�⋕�����ɒ��ӂ���B���ߏ�r���k���������N�P�肷��B���Â͂܂��։����A���̋����⊴�����ώ@���Ė��Â�ؒf�̎�������������B
Key Note Lectures for Innovation
�w��Ð��x�̃C�m�x�[�V�����̂��߂Ɂ`��Õ���j�~�̏����@��ʌ��ϐ���I���a�@�O�ȁ@�{�c�G
��Õ���̌����́u�������ځv�ɂ����Ô��i��Ô�S���_�j�ƈ�t�{���}���ɂ��i�Ζ���j�̐�ΐ��s�����B
1.����
���{�̈�Ô��GDP��7.9���Ɛ�i���ł͍Œ�ł���BGDP��11-12���ɂ��ׂ��ł���B���{�̈�Ô�͈����A���ҕ��S�͈�ԍ����B�@
2.��t�s��
�W����t���͍������a�Q�R�N�Ɍ��߂����̂ł���A���݂̎���ɍ���Ȃ��B��t�݂͑̕�R�ł���A��ΐ��Ƃ��ĂQ�O���l�s�����Ă���B�P�X�W�R�N�Ɂu��Ô�S���_�v���o�Ĉ�w��������팸���ꂽ�B�Q�O�O�O�N��WHO�������ł͂U�R�ʂł���B���̌��ʁA�Ζ���͑��Z�ƂȂ�A��Î��̂̊댯�������債�Ă���B��t���Y��������Ȃǖ��ł���B�@�@�@�@
3.���
���ɂ͊������ڂ̑̎�������A�������Ă���B���f�B�A�ɂ���Î��̕����������L�͐����Ƃ͈�Õ���̐^����m��Ȃ��B�����͔N������ƐȎ����ł���A�Â����͂ƒx����{���j�����Ȃ��B�@�@
���́@�y�Ō�t�@�@���R�@���q�@�@�@
����@�@���͂P��p�X�̍쐬�Ɠ����@���@�ۑ��������t���a�iCKD�j���җp������@�N���j�J���p�X�̌����@���@�ɂ����閝���t�s�S������@�p�X�̐��ʂƉۑ�
���e�@���z�@�O���ێ����͊��҂�ΏۂƂ����p�X���쐬���邱�Ƃɂ��A�X�^�b�t�̃P�A��W�����@�K�ȓ��͈�Â��ł��A�p�X�ɂ��A�E�g�J���̉��P�ɂ̓A���P�[�g�����ŃX�^�b�t�̈ӎ��y�эs���̕ω�������ꂽ�B���@���͎��ł��A�������̃p�X�E���Ҏw���p�p���t���b�g�E�����`�F�b�N�E�\�t�b�g�P�A�\���쐬�B�X�^�b�t�Ə������L�����ꂵ���Ō��}���Ă���B���ꂩ��͕ۑ���CKD���ҋ���p�X�i������@�j�[�����A�O���E�a���E���͂ƘA�g�A���ꂵ���w�����ł���Η��z�I���Ɗ������B
����@�@���A�a���҂̌����R���g���[�����悭����ɂ́@���k�J�Еa�@���A�a��ӓ��ȁA�Ԉ�T�P�搶�@���e�@���z
�����R���g���[���́A�����Ǘ\�h�̂��߂����łȂ��A�ł��������������ǂ̎��Ö@�ɂ��d�v�ł���BHbA1C�@�U�������͗ǍD�Ȍ����R���g���[���ɁA���a�Ȓ�`���H���炪�p�������A�l�t���[�[���x���̓��A�a���t�ǂł��A�A�`���̏����܂ʼn��P�ł��A���̌�̐i�W��}���ł��邪����͌����̂݊Ǘ��ł͎����ł��Ȃ��B�@�H���Ö@���d�v���A�a�҂́A�������̌p��������Ȃ̂ŁA���������ł��邲�т��ɐ������Ă����ʓI�ɂ������̉ߏ�ێ�ƂȂ�B�̏d�̉��P��҂��Ă���ԃR���g���[���s�ǂ������ƁA���Ő��ɂ��C���X��������ቺ�������C���X��������\�̕ۑ�����Ă��邤���ɁA�����C���X�����Ö@�ŃR���g���[���̉��P��}��A�X���@�\�C���X������R�������ɂ߂ē������I�����邱�ƂƁA�ጌ���\�h�@�w�����s�Ȃ��B�@
���@�ł����͊��҂œ��A�a���t�ǂ������A�����E�����E�̏d�R���g���[���ŔY�ނ��Ƃ�����B�H���w���́A�H�����e���h�{�m�ƘA�g���w�����s���Ă��邪�A�����g�A���҂̗����ł���悤�ȐH���w�����ł������̃X�^�b�t�ɏ������邱�Ƃ�����B�@����̍u�`�ʼn��߂ĐH���Ö@�̏d�v���������A���҂�育�т̗ʂ�H�����e���A��̓I�Ȏw�����ł���悤�ɓw�͂��Ă��������B
���ʍu���@�@�V�������z�Ƃ��Ă̑ς���S�@���H�����ەa�@���ȁA���쌴�d���搶
���e�@���z�@���͗Ö@���ɂ���t�������҂̐��_�q���ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����邩�P�`�S�^�C�v�ŕ��́@�P�@�����@���͂��d�˂邤���Ɂ@���낢��̍����ǂ��N���邱�Ƃ����O���ā@�s���̓��X���߂����^�C�v�̐l�@�Q�@���邪�܂܂ɂ��ׂĂ��@���߂Ă���l�@�R�@�����ƋZ�p�̃T�[�r�X�̂悢�{�݂�͍�����l�@�S�@�厡��₻�̎{�݂̃��x���������]�����@�S�ʓI�ɐg��C���@����ň�������Ή^���Ƃ��Ē��߂�l�@�@�@�@�@�@�@
�ȏ�̃^�C�v���͂��Ȃ���u�l�Ԃ̑ς���v�Ƃ������_�s���̕\�ʂɂ���S����Ԃ͂��A�ς��钆�ɕa�ސS�̐[���ƕa�ނ��Ƃ��A���������߂�ꑼ��z������S��A���ӂ���S���N���Ƃ����悢�Ӗ��ł́u�ς��铿�v�����܂��B���҂��@�ς���S�������ƂŁ@���ғ��m�x���������Ƃ��ł���@�X�^�b�t�͕⏕�I�����ł悢�B���݂̊Ō�́A��������ς�炸�Ō�ň��Â𑣂����A�p��Ȃǂ̒���������Â�A���������ł̒����Ȉ��Â͑̂̊e�V�X�e����ቺ������B��Έ��Â͋�B��ɓK���Ȏh����̂ɗ^���ĉ𑁂߂�悤�ɂ��ׂ����Ƃ����߂���B�@���҂͏p��▝���a�̗×{���ɂ͈��Â��悢�Ǝv������ł��邱�Ƃ������̂ŁA�i�[�X�͓����悤�Ɏw������B�����ŁA���Î��ċz�@����҂̉����̉^���Ƃ��Ă̕��s���@�A�����ԓ��͂���銳�҂̓��͎��Ԃ̗��p�@�ȂNj�̓I�ɐ���������A���͎��Ԃ͂ځ[���Ƃ����|�W���`�u�ɍl������悤�Ƀi�[�X���菕�����Ăق����Ƃ��b���ꂽ�B�搶�͂X�T�ƍ�����A������t�ł���ő����̍u��������Ă���B�u�����������b�����p���[�Ɉ��|����Ȃ�����p���[�����ꂩ��̊Ō�ɐ������Ă��������B
�Q���ҁ@���͎��@�y�Ō�t�@�y�i�ЂƂ�
���e�F�V�i�J���Z�g���_���i���O�p���j�ɂ���
�P�D��p�@�@�E�����b��B�@�\���i�ǂ́A�����t�s�S�Œ������͂��Ă���l�ɑ�������a�Ԃł���B�o�s�g���ߏ�ɕ��傳��邽�߁A������̃J���V�E���n�o���������Ȃ�A�����铧�͍��ǁi�@�ې������j���N�����B����ɁA�����J���V�E���̑����ɂ�茌�Ǖǂ̐ΊD���i�ُ����ΊD���j���i�݁A�����d���ɂ��d���S���njn�����ǂ̌����ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B���̃V�i�J���Z�g���_���́A���b��B�ɒ��ړ��������A�ߏ�Ȃo�s�g�̕����}����B���̌��ʁA������̃J���V�E�����o���~�܂�A���t���̃J���V�E������̒l���ቺ�����퉻����B���ɂ�ߒɂ��a�炬�A���܂̗\�h���ʂ����҂ł���Ǝv����B����ɂ́A�����I�Ɍ��t���̃J���V�E���ƃ����̔Z�x�𐳏�ɕۂ��ƂŁA�S���njn�����ǂ̗\�h�ɂ��Ȃ���킯�ł���B
�Q�D�����@�@�E���b��B�̂b����e�̂͒��ڍ�p���鏉�߂Ắu�J���V�E����e�̍쓮��v�ł���B�r�^�~���c���܂Ŗ��ƂȂ錌���J���V�E���Z�x�̏㏸���N�������ɂo�s�g�̕����}������B
�R�D�p�@�@�@�E�J�n�p�ʂƂ��ẮA�P���P��Q�T�r��H���ƊW�Ȃ��o�����p����B�Ȍ�͊��҂̂o�s�g�y�ь����ba�Z�x�̏\���Ȋώ@�̂��ƂP���P��Q�T�`�V�T�r�̊ԂœK�X�p�ʂ������p����B�������APTH�̉��P���F�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�P��P�O�O�r������Ƃ���B���ʂ��s���ꍇ�́A���ʕ����Q�T�r�Ƃ��A�R�T�Ԉȏ�̊Ԋu�������čs���B����Ca�l�������肷�����ꍇ�́A���ʂȂ����x��B�K�v�ɉ����ăr�^�~��D���܁i�������͒��ˁj�Ƃ̕��p�Ŏg�p����B
�S�D����p�@�@�EPTH�̕��傪�}������邱�Ƃ����Ca���ǂƂȂ�A���̏Ǐ�Ƃ��Ĉݕ��s�����A���S�A�q�f�A�H�~�s�U�A�����A�s�����A�����ቺ�Ȃǂ��������₷���Ȃ�B
�y�@���z�@�z�@�����b��B�@�\���i�ǂɑ��A�V�i�J���Z�g���_���̓��^INTACT-PTH�ECa�EP�l�̈����}���Ă���{�݂��������ʂ��݂��Ă����B����p�Ɋւ��ẮA���^�J�n����P�J���̊Ԃɏo�����邱�Ƃ������A�w�Ǔf�C�A�ݕ��s�����Ȃǂ̏�����Ǐ�ł���A�ݖ�ɂđΉ����Ă���B���^���ꂽ�w�ǂ̊��҂͂P�J�����x�ŏ�����Ǐ�̕���p�͏�������B���^�ʂ𑝂₵�����ɂ́A���l�̏�����Ǐo������B���@�ł����݂P���̊��҂Ɏg�p���Ă���A���p�J�n�P�T�Ԓ��ŕ���p�Ƃ݂���ݒɁA�f�C���̏�����Ǐ��i���A���݂��ݖp���ł���B���@�̊��҂Ɋւ��ẮA���O�p�����p�ȑO���ݒ�ᇂƐf�f����Ă������Ƃ�����A���O�p�����p����ݒɂȂǂ̑i�����邪�A���O�p�����^�ɂ�镛��p�Ȃ̂��͕s���ł���B�����l�Ɋւ��Ă͖��炩�ɉ��P�݂��Ă���B�w��ł̏Ǘᔭ�\�ł́A������Ǐ�̕���p���o�����邱�Ƃ���A���@�ł����ヌ�O�p�����^�Ώۊ��҂������ꍇ�ɂ́A�ώ@���\���ɍs���Ă��������B�܂��A����̋Ɩ��Ɋ�������悤�ɓw�߂����Ǝv���܂��B�@����A�w��ɎQ�������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B
�@ |
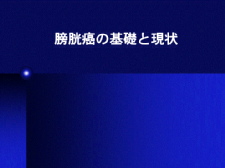 �@
�@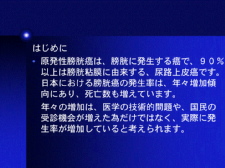 �@
�@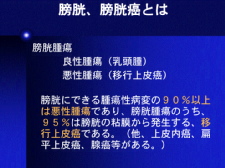 �@
�@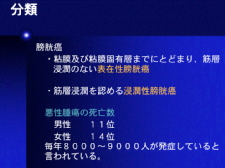 �@
�@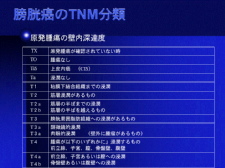 �@
�@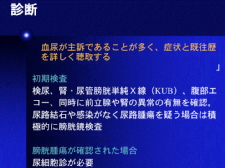 �@
�@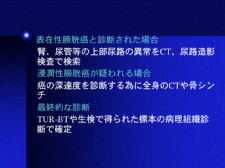 �@
�@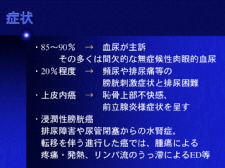 �@
�@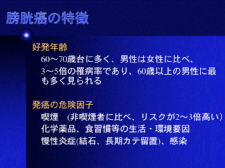 �@
�@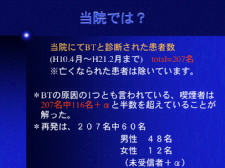 �@
�@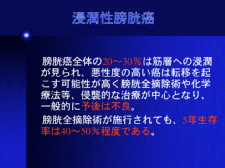 �@
�@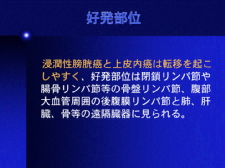 �@
�@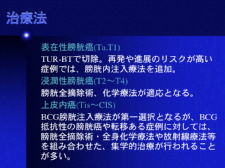 �@
�@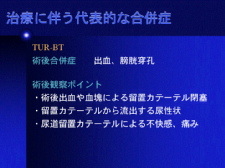 �@
�@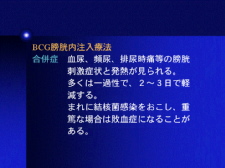 �@
�@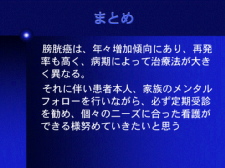 �@
�@